


秋澤月枝
essayist
日本人の夫と、2002年からオーストラリアに移住。
最初の半年は、単身、ニューサウスウェールズ州のBed and Breakfastで家庭料理を学ぶホームステイを体験。その後、夫が就職したクイーンズランド州のワイナリーに合流。
現在は、家族とケアンズに暮らす。
お菓子作り、編みぐるみや折り紙などの手仕事が趣味。
中学生と高校生の子どもを持つ母でもあり、彼らの描く絵の1番のファン。

12.10.2025
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
つながり

1・まち歩きライター講座
「滞在国でマイノリティーとして生きていくとき、慣れ親しんだ食は力になるし、文化交流の一端にもなる」
これは、私がなぜ「ハラール食材店」を取材先候補に挙げたのか、グループメンバーへ改めて説明する時に書いた文章の一部だ。
私は現在「ぎふ まち歩きライター講座」に参加している。
この講座は名前のとおり「岐阜のまちを歩き」「取材し」「文章を書く」というレッスン。
2021年から始まった「メディコス編集講座」第五期生として、20名で講座を受けている。

私は文章を書くことが好きなほうだけれど、ここでエッセイを書いているように基本的に自己表現の一環で、気の向くままに書き上げることが多い。
取材をして、情報を分類し、いくつかのプロセスを経てまとめる、という作業はあまり経験がない。
というか、少し身構えてしまう。
その自覚があったので、プロを講師に迎える「まち歩きライターの教室」に興味を持った。
運よく当選したこの講座では、現在、三つのグループに分かれて活動をしており、街歩きのあとの文章作成の段階。
私が所属するチームはハラール食材店を選び、「お店の紹介」「異文化理解」の内容で、文章を作り込んでいるところだ。

ハラール対応のカルボナーラを購入、作ってみた。やさしい味わい
2・メディコスという空間
講座はメディコスで受けている。
「メディコス」は正式名称を「みんなの森 ぎふメディアコスモス」といい、2021年に新庁舎になった市役所とは広場をはさんだ反対側に建つ。「メディコス」は市役所より6年ほど早い2015年に開館しており、中は木製の意匠が美しい、落ち着いた空間が広がっている。
「知の拠点」の役割を担う市立中央図書館、「絆の拠点」となる市民活動交流センター、多文化交流プラザ及び「文化の拠点」となる展示ギャラリー等からなる複合文化施設です。(公式サイトより抜粋)

私がはじめて「メディコス」に足を踏み入れたのは、スタバがあったからだった。
市役所で事務手続き中の昨年末、義父と娘と私の3人で、マイナカードを受け取るために60分以上の待ち時間をつぶしていた。とりあえず便利な場所だな、と思った。
次に訪れたのは、今年2月に行われた「災害時における外国人支援講座」に参加するためだった。ここには大小のスタジオがあり、こういったイベントに対応していることを知る。
この会には、各地域の班長さんや外国人を抱える企業の方などが主に参加しているようだった。個人参加の私は門外漢かと思われたが、防災以外に「岐阜市の人口3%が外国人」などの情報を知ることができ、純粋に勉強になった。『本帰国から2ヶ月の自分は、まだ外国人の立場だな』とも思った。
そして3回目はこのライター教室。
前回の講座ではどうしても堅苦しい空気がながれていたが、こちらはどちらかといえば生涯学習的な雰囲気だった。
メディコスのスタッフさんや講師の方々、集まった老若男女の参加者と、雑談もできる環境に身を置くのははじめてのこと。岐阜市民(近隣含む)の交流の場であることを体感し、メディコスにぐっと親近感を抱くようになった。
ホールには、アニメ「小市民シリーズ」の展示や、地元のスポット紹介が見られる設備がある。過去のライター講座卒業生はメディコス発のブログや出版物で文章を書いていたり、ZINEの作成、ラジオ出演もしているようだ。
この出会いが一度きりではなく、これからも続いていきそうな未来が想像できる。

3・マルチカルチャー
そういえば私がメディコスを訪れる時、ステージエリアでは「外国人の日本語スピーチコンテスト」やダンスの発表を目撃することが何度もあった。
ゆっくり見ていたいけど、別の目的で来ているのでいつも後ろ髪を引かれていた。
私が住んでいたケアンズでは、マルチカルチャーのお祭りが毎年行われている。
近隣に住む海外ルーツの人々が、自国の音楽、ダンス、食、アートなどを披露する楽しい祭典。
息子がまだ小学校低学年の頃に「日本人子供会」として太鼓の発表をしたなあ、と思い出す。大きい子たちは本物の太鼓を使って、フォーメーションを変えながら叩き、小さい子たちは座り込んで竹の太鼓を叩いていた。当時息子が所属していたサッカーチームの監督(メンバーのお父さん)が、わざわざ見に来てくれたのは嬉しかった。
在留国でも、自国の文化を披露できると誇らしい。
食べ慣れた祖国の食事を再現できると力が湧く。
二十数年ぶりに帰国した日本人の私が、いまだに住み慣れない日本で「できることはなんだろう?」と思ってきた。
メディコスで海外の方との交流現場に出会い、市民としての文化活動を後押ししてくれる環境に身を置いて、明るい光が見えた。
大きなことはできないかもしれない。
でも、できることが何かありそうと、少しずつ前向きな気持ちに変化している。

9.10.2025
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
浦島太郎の給与明細

1
今日、手にした給与明細は、昔ながらのものだった。
青色で印字した詳細部分を隠すように、半分に折って封がしてある。長方形の3辺をミシン目に沿って切り取ると、開けられるという造り。
用紙の両側に一列の穴があいていて、連続印刷ができる懐かしの印刷機を思い出すような紙なのだが、わかっていただけるだろうか? (連続帳票で検索すると、それらしき画像が出てくるはず)
オーストラリアでは、最近の給与明細はメールに添付されるか、専用のウェブサイトにログインして確認するタイプが多かったので、懐かしい気持ちになった。
そういえば、オーストラリアの給料の振込は、一般的に毎週か隔週ごとだった。
日系の会社だと月に一度払いの場合もあるが、地元企業ではあまり聞いたことがない。
週ごとの給与支払いのいいところは、とにかく、働き始めてからすぐに振り込みがあるという点だ。働いていることの実感を得やすい。
そして家計の予算を組み立てる時に、週単位で計算ができるのも便利だった。
必要経費の概算を、週単位のサイズにし、自分たちの収入で足りているかどうかの計算が容易だった。
私は、自作の家計簿を使いやすくアップデートするのが好きで、オーストラリア在住時終盤はかなり満足のいくものを使っていた。
現在は、日本版を改良するのに余念がないが、そもそも銀行口座のシステムが異なるので、一筋縄ではいかないと感じている。
日本にも、夫婦共同口座があればいいのに…。

2
日本へ本帰国してまだ半年ちょっとだが、受け取った給与明細は、ここが3社目になる。
私は就職でつまづいていた。
4月、娘の進路も決まったし、私も正社員になって「親らしく」稼がないと、と活動していた。ありがたくも、未経験ながら事務職の契約社員として採用され、働き始める。と言い終わりたいところだが、「働いていた」というのもおこがましいくらいのスピードでギブアップしてしまう。
なぜ? と私自身も思った。
日本にいなかった時期が長いアラフィフの私にとって、せっかく受かった条件の良い会社だったのに。
いざ自分が働くとなった時、恐怖心や不安が覆い被さってきて、「場違いな気持ち」や「世界がガラス越しの向こうの景色」に見えたらもうダメだった。夜もうまく寝付けなくなっていた。
自分が、「消費者」として日本で生活をするだけならそれなりに適応できていたと思う。旅行者や一時滞在者とあまり変わらない感覚でも大丈夫。
しかし働くことで「価値を提供する人」になろうとした時に、適応が難しくなった。
オーストラリアで仕事を探していた時も、採用されてから「無理だ」とギブアップしたことはある。それぞれの勤務先に対して、それぞれ不安に思うことがあった。
今回は、個別の不安以上に、「日本」に対する漠然とした何かだろうと感じていた。
そこで糸口を掴みたくて、私の気持ちをそのまま検索窓に入力すると「帰国うつ」「逆カルチャーショック」の言葉が、出てきたサイトに羅列されていた。
母国の文化を出て、新しい国の文化を吸収した後、ふたたび母国に戻った時に適応が難しくなることのようだ。時間が経てば、また馴染んでいくことが多いそうだが、それを待っていたら我が家の生活はどうなるのか。
不安は残ったままだが、子ども達の顔を見ていると、前に進まなければと思ってしまう。
あまり人と関わらない、短時間の仕事ならできるのではないか?
在住外国人も働くところだったら、簡単に辞めるのが恥ずかしくなって続けられるのではないか?
そう思って次の仕事を見つけた時に、三日間だけ働いた最初の会社のお給料が振り込まれ、今年度の源泉徴収票が自宅に届いた。勤務日から1ヶ月半後のことだった。
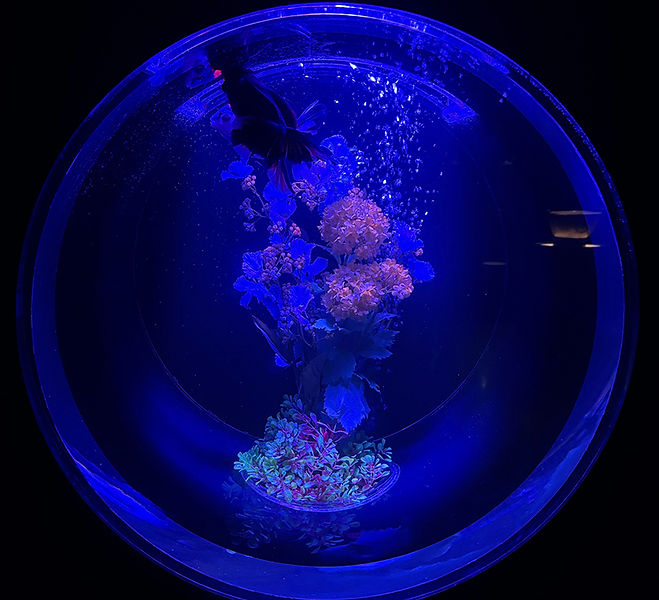
3
この条件なら働けるのでは?
と思って応募したのは、ショッピングセンターの早朝品出し4時間。
人に会わず、黙々と作業ができるのではないかと思った。
が、面接時に人手が欲しいのはレジスタッフだという話になり、不安ながらも受け入れてしまう。レジにはたくさんの在住外国人が働いている。
最初の会社同様、こちらも周りのスタッフは優しい人が多かった。
会社側に非があるわけではない。
初心者マークを見たお客さんからは「頑張って」と声をかけられた。
日本にいた時も接客業だったし、オーストラリアでも何かしら接客はつきものだった。
「一日4時間ならなんとか頑張れる」
「仕事に慣れてしまえば、あとで笑い話になる」
前向きな言葉を投げかけて自分を奮い立たせ、1日1日を過ごしたが、2週間ほど経った頃にぷつっと糸が切れてしまった。
結構、落ち込んだ。
この会社の給与明細は、ウェブサイトにログインして取りにいくスタイルだった。
中途半端に辞めてしまった私は、サインインをするタイミングも逃し、2ヶ月に分かれて給与が振り込まれて終わった。

4
最終手段を使うしかないのだろうか?
私は、オーストラリアではベッドメイクの仕事を長く続けてきた。
リゾートホテルで6年半、医療系宿泊施設で3年。
一日単位の派遣会社では、3件のホテルに出向いたことがある。
慣れているのなら、はじめからそれを選べばいいのにと思われるだろうが、肉体的にきついうえ、長時間働くものでもなく、ネットによる人類総評論家時代の昨今、客サイド・会社サイドからの実力テストを毎日受けているような、修行の場だった記憶があるのだ。
こまめに求人サイトを眺めていても、顔ぶれは変わらない。
「年齢」「日本」の条件で新しいことを始めるには、現在の精神状態ではたぶん弱すぎる。
そして、清掃業は常に人材を求めている。
勇気を振り絞って、ホテルの門を叩いた。(正式には、ホテルに清掃を業務委託されている会社に)

仕事を始めてから、もうすぐひと月になろうとしている。
日本で働くということに、まだ不安はあった。今も不安が消えたわけではない。
このホテルで一人前に働けるようになったわけでもないし、最初の半年は試用期間だ。
それでも、シーツを張ったり、バスタブを磨いている時
「この感覚を私は知っている」
「どういうことに気をつけるべきか、予測が可能だ」
という気持ちが起こり、それが精神安定剤になる。
今日受け取った明細は、初めの半月分のお給料。
来月の今頃は、まるまる1ヶ月働いた分の給与明細になっているだろう。
私が記憶している23年前の日本の空気を思い出すような、懐かしい紙の給与明細をもらいながら、私のいなかった日本に少しずつ馴染んでいきたい。
4.12.2025
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
エール!!

1・透明人間
自分が見ている景色が、
本当に存在している景色なのか、
本当に自分が見ている景色なのか、
不思議に思ったことはないだろうか?
私は未就学年齢の頃、もしかしたら年中さん以前の頃に、そのような感覚に落ちいる瞬間がたびたびあった。それはたいてい自宅の中を歩いているときで、差し込むように急に感じる違和感だった。訳がわからなくなって、周りをぐるっと見渡したり、自分の手を見たりしてみるのだが、やがて違和感を違和感として感じることをあきらめ、再び歩き出すのだった。
おそらく、自我を形成する過程で起こる何かなのだろう、ということで現在は納得している。
ただ、もし見えている景色が「現実」と呼べるものでないのなら、私は存在しているのだろうか? と、少しだけ不安になった。

2・なりたくてもなれない
オーストラリア滞在の初期は、英語も喋れないのに、夫と離れてホームステイ生活を送っていた。
単語と、カタコトの英語とジェスチャーでしのぐ日々。
はじめのうちは日本語のように話したいことがウチから湧き出てきたが、英語を持ち合わせていないので会話のテンポについていけない。
ステイ先は民宿を営んでいて、お客さんと話をする機会もあったし、ご近所さんや独立しているお子さんたちが尋ねてくることも多かった。ホストファーザーやマザーがそばにいてくれれば、私が喋れなくなってもサポートしてくれたが、そうでないときは自力でその状況を乗り切らなければいけない。
好意から話しかけてくれる人。
礼儀として話しかけてくれる人。
英語で流暢にコミュニケーションをとることをあきらめていた私は、笑顔で後ずさりして、無意識にかくれようとしていた。
申し訳なくて、私のことは気にしなくていいから、どうぞ皆さんで話しててくださいな、と思いながら。
自分がアウェーな環境に身を置いて、透明人間にはなれないことがわかった。
「自分がここに存在している」ということを強く意識する結果となった。

3・積み上げ
オーストラリアにいて良かったのは、自分の土台がない世界だったので、何をやっても自分が積み上げている感覚を持てたことだ。
友達を作った、
仕事に就いた、
仲間ができた、
子どもを産んだ・育てた、
趣味ができた、
住まいを借りた・買った・売った、
途中からは、「いかに英語が下手なままで、快適に暮らすことができるか」というネタのような感覚で生活していたが、それはつまり生活に余裕ができたということだったと思う。だからこそ昨年の後半、日本へ帰国するために断捨離をして、自分の周りからモノがどんどんなくなっていっても不安になることは少なかった。
いったんリセットされたとしても、また積み上げていけるだろうと思える。
逆かな?
一度すっきりした方が、次を迎えやすい状態にできる確信があったのかもしれない。

4・積み直し
そう言えば「実存主義」という言葉があったな、と文章を書きながら思い出した。
哲学用語らしく、私はその方面には疎いのだが、
「存在は本質に先立っているという基本的な教義である」とウィキぺディアに書かれていた。
また別のところで、次のような内容の文章を読んだことがある。
「過去のこれまでの出来事は、これから自分が何をするかによって意味づけを変えることができる」
これら二つの内容に、もしかしたら直接的な繋がりはないのかもしれない。
しかし私は今現在、無駄なことを考える時間を持て余しがちなので、自分へエールを送る言葉として受け取った。
「これから自分が何をするか」ということに適度に期待を抱き、もう一度「ああ、もう毎日大変!」
などと思いながら過ごす日々がきても面白そうだと思っている。

2.8.2025
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
日本の洗礼

1・日本の冬
2002年お正月以来はじめての、日本での年越しだった。
紅白を見たり、除夜の鐘をついたり、妹夫婦の杵つき餅をいただいたりと新春気分を味わえて嬉しかったが、寒かった。
そして現在進行形で、とにかく寒い。
別の部屋へ行こうとちょっと廊下へ出た時の冷気や、冷えた床、水道の蛇口をひねって出てくる冷水、体と脳がその冷たさに準備できていないのだ。慌てて身を縮める。
ケアンズにいた時は「北陸育ちだから暑さに弱い」とブーブー言いながら溶けていたが、近年の私の体が慣れていたのは暑さのほうだったことに、今更ながら気づく。
そりゃあそうだ。
熱帯雨林気候のケアンズに14年、その前に8年住んだイプスウィッチだって赤道からの距離は沖縄と同じくらい離れたところにある。
そんな場所で子育てもしてきて、完全に体は暑い環境に順応してしまっていた。
気温が十五度を下回ると「凍える」と感じていたのだから、雪まで降る日本の、岐阜の冬は間違いなく寒い。
娘と私が持っていた長袖の服は1、2着程度だったが、
「日本で買えばいいよ」と言って成田に降り立った。
足元がサンダルからスニーカーになっただけで、冬支度を終えた気持ちになっていた。
春・秋用の薄手の長袖に、奇跡的に持ち合わせていた薄手のコート二着。
寒さと、荷物の重さと、東京のホテルまでの移動3時間のおかげで、娘はしっかり風邪をひいた。ゆっくりとお買い物、どころではなかった。

2・事務手続き三昧
オーストラリアの家も、家財道具もほとんど処分してやってきた日本である。
まずは住民にならなければ何も始まらない。
今では自動ゲートになっている入国審査では、市役所での手続きのためにスタンプをわざわざ押してもらった。
娘もはやく中学校に転入し、日本式の学校に慣れ、受験に備えなければ。
携帯電話も、住民票とパスポートで契約できる会社を事前に見つけた。
と、準備万端のつもりだった。
岐阜へ着いていざ! というところで、パスポートを東京のホテルの金庫にしまい込んで忘れてきたことに気づく……。
予定より1週間ほど遅れての市役所内行脚はせわしかった。
「市民課」「国保年金課」「マイナンバーカード特急申請」「学校安全支援課」「子ども支援課」などを順に回る。
何年か前に新庁舎になった市役所はとても綺麗だったが、その中で行われているのは対面が基本の業務だった。
オーストラリアの事務手続きは、近頃は大抵オンラインで済んだので、改めて日本に帰ってきたのだなと実感した。
(息子の時のように)一年以上滞在の予定かを尋ねられ、一筆書くよう求められた。
(毎回の一時帰国で住民登録ができる市町村もあるので、判断の差、激しくないでしょうか?)
また、旅行ではなく生活する者として必要な手続きは、市民になることだけではない。
携帯電話、運転免許証の書き換え、銀行口座開設、猫2匹飼育可の賃貸物件契約、自家用車購入。
家電製品一式購入や、家具一式の購入も待ち構えている。
ケアンズの職場の仲間から「次の仕事の当てはあるのか?」とよく聞かれたけれど、新居での生活が整うまでは落ち着かない。お世話になっている借宿とこれから生活するアパートとの往復をして、少しずつ生活に必要なものを買い揃えている段階だ。
仕事に就いた夫と、学校へ行く娘はすでに日常生活になったと感じているようだが、私だけは一時帰国の感覚が抜けきれていない。
日本でもまだ、不思議な時間を過ごしている。

3・日本で車を運転するということ
ところで大学生の頃に日本で運転免許をとった私は、完全ペーパードライバーだった。
しかしオーストラリアに渡り子どもが生まれたら、運転が怖いと言っていられなくなった。車がなければ、どこにも行けないからだ。
乳児の息子を後ろに乗せて、両掌に汗をかきつつ運転を始めた。
朝夕と、夫を職場へ送迎することで同じルートを運転する練習になり、次第に1時間ほど離れたブリスベンのプレイグループにまで自分で行けるようになった。
オーストラリアは基本的に道幅が広い。道路の両脇には歩行者用の芝生もしくは舗装されたスペースが広く取られて、日本のように道路のすぐそばに住宅が建つことはまず無い。道路上の歩行者や自転車も少なく、運転しやすかった。
車に乗り始めた当初、そんな道路状況の違いのおかげで脱ペーパードライバーの私でも運転できたのは間違いない。
今回日本に戻って、いろいろな人の車に乗せてもらい改めて思った。
普段運転しているみなさんは意識していないだろうけど、日本の道路、特に住宅地の狭い道はスキルがないと走れない。
歩行者や、スピードが早く動きの読めない自転車などが道路に存在する確率がまず違う。
道路そばに立つガードレール、すれ違う時の車間距離の狭さ、そして走っている車が全体的に新しくて綺麗なのは、ちょっとプレッシャー。
地方で子を持つ親として車が運転できなければ、生活が大変になるのはここでも同じ。
また、汗をかいた手のひらを拭う日々になるのだろうか。

4・自分の居場所
私の日本での生活の記憶は、当然ながら20代で止まっている。
一時帰国の時はあくまで旅行であったから、生活者の視点は抜け落ちており、日本式のサービスを楽しむばかりであった。これまで国外からの在外選挙に参加していたものの、それでも自分は蚊帳の外的感覚でいた。
改めて日本に戻って、生活者として生きていこうと思った時、不思議なのだがなぜか非難されているような気持ちが発生した。
やたら「すみません」を連発した。
まだ仕事も始められないし、車も運転できていないし、自分の国に帰ってきたはずなのに、まるで子どものよう。
「一度ゆっくりしてもいいんじゃない?」と言われていても、今の私ってなんなんだと後ろ向きになりかけていた。
そんな折、私の地元に帰った。
家族のいえは暖炉のあるログハウスで、一度火をつけると家のほとんどの場所が暑いくらい快適だった。
ライフハックを教えてもらったり、亡き母の思い出を語り合ったり、寝る間を惜しんで喋りたおした。そして手作りの梅干しや梅酒、味噌などを分けてもらった。
完全帰国したあと、休んでいるつもりでも、整えたい次の生活を見ていた。また、猫たちの体調不良などにも忙殺されていた。
帰省という名目で「今は休憩の時間」と割り切ったとき、周りの繋がりのある世界に再び着地できた感覚だった。この時期に、観たいライブが金沢で行われていてよかった。
北陸土産を持って、また岐阜の家庭に戻ろう。

12.5.2024
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
本帰国までのカウントダウン

1・長い新婚旅行のおわり
学校の年度末にあたる12月中旬に、私たちは日本へ引っ越しをする。
これは海外在住者でいうところの「本帰国」であり、2002年から続いた私のオーストラリア生活も、残りわずかであることを意味する。
もともと英語も喋れないのにオーストラリアへやってきたのは、人生の1ページを海外で過ごして自分たちの視野を広げたい、という理由からだった。
「海外で数年過ごしても、私はまだ二十代だし」という楽観的な行動だったが、結果、子どもを産みティーンエイジに育て上げるまで滞在してしまった。
結婚式をしなかった私たちの結婚には、当然新婚旅行の予定もなく、したがって当初は「この海外滞在が代わりかな」と話していた。
つまりは、22年間の新婚旅行ってこと?
むかーし、オーストラリアのテレビコマーシャルで、銀行の列の順番を待つ間にロマンスが発生して子どもまで生まれる、という皮肉めいたものがあった。
ちょっとそれを思い出してみたりして。
(私たちが「待っていたもの」は、とくにないのだけれど)
終わりが近づいてきているので、センチメンタルに少しお付き合いいただきたい。

2・猫の国際間輸送
新婚旅行中(?)に増えたのは、二人の子どもだけではなかった。
体格の良い猫二匹も家族として迎え入れていた。
この子達も日本へ連れて行きたいが、どうしようか?
私たちを悩ます、最初の大きな問題になった。
引き取って半年後、彼らが一歳になる頃に一匹の子が泌尿器系のトラブルを発症した。何度か入院したのち、今でも時々血尿を出すし、知らない人が家にきたら絶対に顔を見せない。
彼の体調と精神面を考えると、飛行機で輸送するのは安全なのか? という議論になる。
猫と離れることは考えられない娘と、費用が高いのに輸送中にトラブルが起こったら散々だと不安になる私。
もう一匹の子は健康面では問題ないし、知らない人にも対応できるから、この子は大丈夫かな? 一匹だけ連れて行く?
しかし兄弟としてずっと一緒に生活してきた彼ら。
今さら引き離したくはない。
答えが見つからない中、今年初めの飛行機火災のニュースを見た。
搭乗者は奇跡的に全員無事だったが、荷物として預けられていたペットにまでは手が回らず、残念な結果になったのは記憶に新しいと思う。
ケアンズから日本への動物の移動は、一旦シドニーを経由する。
つまり最低2回は飛行機に乗らないといけない。
東京へ着いた後も、岐阜まで何らかの方法で輸送の必要がある。
ちょっと車に乗せるだけでもミャーミャー鳴きっぱなしなのに、そんな負担の大きいことを、猫たちに課していいのだろうか?
私たちのわがままではないだろうか?
こちらで引き取ってくれる人を探した方が、体調面では安心なのではないか?
獣医さんに相談したり半年ほど悶々としていたが、4歳と年齢もまだ若いし、家族として連れて行きたい思いが勝り「わがままになる」覚悟を決めた。業者にコンタクトをとり、獣医さんに報告をした。
選んだ業者さんは誠実で、途中経過もきちんと報告してくれた。
結果は、大成功。
羽田から名古屋までのフライトも追加された計3回の飛行機もやり過ごし、猫たちは何のトラブルもなく、セントレア空港で夫と再会できた。
健康面の問題も発生しなかった。
提案してもらった、「気持ちが穏やかになる」という乳成分のサプリメントが効果を発揮したのかもしれない。
猫たちのタフさに感心した。
一つ変わったことはといえば、彼らの性格だそう。
シャイで病気がちの子が社交的になり、社交的だった方が引っ込み思案になっているという。入院経験のある子は、その経験からイレギュラーな事態に強かったのかもしれない。
この性格逆転の現象が一時的なものなのか、それともこのまま継続するのかは、今後の様子を見ないとわからない。
とにかく無事に日本在住の猫として、初めての冬を経験している真っ最中である。

3・残された女子二人
ケアンズと岐阜の両方の気温が落ち着いている10月に、猫だけでなく夫も一緒に日本へ帰ってもらった。引っ越し先はひとまず彼の実家だし、日本での生活基盤を先に作れるのではないかと話がまとまったのだ。
息子はブリスベン。
つまり我が家の全ての「男子」が出て行き、娘と私の二人がケアンズの自宅に残った。
自宅は持ち家で、貸し出したりせず売却の方向で話を進めている。
夫と息子は事前に家のペンキ塗りをしてくれていたので、その後の諸々を私が引き継いで売るための準備をする。
午後の仕事は、このタイミングで退職した。
家の売り出しまでは、およそ1ヶ月。怒涛の住宅整備ラッシュが始まる。
電気、水道、フェンスの業者手配。
家の中を空にする準備。
庭の外構を見た目よく。
ゴミ出しのために回収ステーションに車を走らせたのは7回。
汗と日焼けと肉体労働。
立っているだけで熱中症になりそうな屋外。
そんな中でスコップを動かす。
枝を剪定する。
蟻と戦う。
スケジュールを気にしながら、自分が倒れないように休憩も挟んだ。
息子に会うために元々予定していたブリスベン旅行では、疲労回復のため、ただひたすらダラダラしていた。
その後、逆に息子を呼び寄せて相談相手になってもらったり、娘に夕食を作ってもらったりもして乗り切る。
おかげで家の中を空っぽにして、次の方が困らない程度に庭も整えることができた。
私の人生で出産後に次ぐくらい、常に何かを考え、行動しているような時期だった。
今もまだその熱は冷めていないので、ゆっくりしようとした時、ふと不安になる。
もう、休んでも大丈夫だよと自分に言い聞かせている。

4・シティライフ
最後のひと月は、車がなくても生活できる場所に、ホリデーアパートメントの部屋を借りた。ここに、とりあえず必要なものや時間がなくてまだ保留にしているものを持ち込んでおり、これを最終的にスーツケース二つ分の荷物にまで減らしていく。
学校や職場に歩いて行けるのが新鮮で、また、聞こえてくる音の種類が違うことを改めて思う。
無謀な運転をしているのであろうブレーキ音、人生に怒りを感じている人の叫び声といったネガティブなものが気になるが、相変わらず鳥の鳴き声もするしヤシの木の葉がこすれあう音もよく聞こえる。
朝の交通渋滞に巻き込まれずに通学・通勤できる快適さや、たくさんのカフェやレストランがそばにある誘惑。
ケアンズの小さな街では、「シティライフ」と言っても高が知れているのかもしれない。
それでも旅行者なのか生活者なのか、ちょっと不思議な気持ちになりながらの借宿での生活は、本帰国までの準備にはちょうど良いようなアンバランスさがあると思う。
「お別れ会」のための外食も増えているし、気を引き締めないと散財してしまいそう。
掃除道具もまだ残っているので、今までの感覚で、この借宿の部屋までついついキレイにしてしまう自分がいるが、このエッセイがStay Saltyに載っているということは、私のスケジュールが予定通りに運んだ証。
それは自分を褒めたいと思う。
街やショッピングセンターは、クリスマスの色が濃くなってきた。
昨年の12月は自宅のあるエリアが水害で大変な目にあったが、今年はこのまま、復興作業が進んでいくことを祈りたい。
娘の中学校転入と高校受験、運転免許証の書き換えや仕事探し。
日本へ戻ってからもやるべきことは盛りだくさん。
ならば今すこし、この不思議な時間を楽しみたい。

9.10.2024
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
料理の自由

1・体力
あいかわらず絶賛断捨離中である。
そろそろガレージセールを開くかと勇気を出して、まずは日本のコミックや雑貨を中心とした品揃えに決定した。
ガレージセールとは、自宅の一角に不用品を並べて買ってもらおうというオーストラリアではポピュラーなイベントで、たいていは近所の人や知り合いが来てくれる。
今回は日本のもの中心だったので、SNSで友人知人と日本語グループにだけ告知して、主要道路の脇に看板を立てる作業は省略した。
日本人の方のほかに、近所の方がふらっと立ち寄ってくださったり、日本人の義母のために日本語の本が欲しいというオージー男性が来てくださったりと予想外の来客もあった。
そこで残ってしまった(というか大半のものは残っているが)品物は、河岸を変えてオンラインに移行した。現在、興味を持ってもらえそうなセットを作っては、時間を見つけて商品登録をしている。
お友達のヘアサロンには小説を置いてもらっていて、私たちを知らない方にも見てもらっている(ありがとう)。
正直いうと、荷物整理の先はまだ見えない。
品物が収まっている棚や、壁の代わりに購入した独立型のクローゼットなどもこのお家から出ていってもらわないといけないが、どのように宣伝すれば、欲しそうな人にリーチできるだろうか? などのことを考えなければいけない(そんな時間も楽しくはあるが)。
肉体労働の仕事を続けながらの作業なので、体力つけないとなあ。
そんなことを思っていたら、雑穀を使った料理教室を開いている方がいる、と友人伝いに聞きつけた。
雑穀といえば、昔の日本でお米が高級品だった頃に庶民が食べていた物ではなかったか。力が湧くかしら?

2・雑穀のお料理教室
6年ほど前、お米に混ぜるだけの五穀米セットを日本で購入したことがある。
そのむかし新岐阜駅付近のどこかのお店で、二十代前半だった私は、可愛らしい雑穀米のランチセットを食べた。それが美味しくて記憶に残っていたのだ。
るんるん気分で五穀米を炊いてみると、当時の家族には白くないご飯は不評で、継続できずに終わってしまった。
そんな記憶を思い出して、作っても家族には食べてもらえないかもしれないが、でもやっぱり私が食べたいから参加しよう! と決めた。
雑穀料理の先生は、ヨガの先生として知っていたけど今までお話をする機会のなかった先輩ママさん。お子さんが生まれてから、健康的な食事を求めて様々な食生活を学習・実践されてきたという。
そんなストイックな方が、この雑穀食に出会ってからとても健康になったとおっしゃる。
私は、肉も食べるし白い物(精製された食品)も加工品も精進料理も、自分の好みであればなんでもいただくので、食に関しては節操がない人間だと思っている。
ヨガで体を鍛え、口にするものを厳選している方とお話ししても良いのかしら?
などと不安になったのも束の間、何事にも全力投球な先生から
『自分の生活に少しでも雑穀を取り入れてみて欲しい、知って欲しい』
というお気持ちがひしひし伝わってきた。
リラックスして料理の工程を学び、先生手作りのランチをいただくことができた。

3・罪悪感
ところで健康的な食事法の情報に触れていると、「Guilt Free Food - 罪悪感のない食べ物」という言葉がでてきたことはないだろうか?
オーストラリアが発祥の、砂糖も小麦粉も添加物も使用しない、フルーツとナッツのみで作られた「ブリスボール」が人気になってから認知度が上がった言葉らしい。
私の記憶でも、ブリスボールがお店に並ぶのを見かけるようになった時期に見知ったような気がする。
甘いものがやめられないことを気にする人向けの言葉かな? 程度の認識だった。
その後、自分の体に害を及ぼさない、という意味での「ギルトフリー」に疑問を持つようになった。食品がもたらす環境破壊や労働力搾取の話を聞くようになったからだ。
高カロリー、砂糖、グルテンなどに対しての「罪悪感の矢印」は自分の体にしか向けられていないが、口にしている食品が生み出した環境破壊の一因や児童を含む強制労働の問題などは、矢印が自分や家族以外に向いている。
そのことを意識するようになってから、
「砂糖や油脂を使わない罪悪感のないお菓子です」
という類の情報に触れた時、ものすごく困惑するようになった。
ただ自分の誘惑に負け、ダメだと思いつつ食べちゃった「てへぺろ罪悪感」の軽いノリに感じてしまうのだ。
自分のことだけ良ければ、それでいいのか?
その罪悪感は、自分以外の世界にも当てはめなければ、ただの自己中だ!
しかし例えば摂食障害など、これまで自分の体を労ることができなかった過去を持つ人もいる。自分を労わることができなければ、その周りの世界を心配する余裕もできないだろう。
さまざまな思考が脳裏をよぎった。
一時期は、その表現はもうやめて欲しいとまで思った。
時間が経ち、罪悪感という言葉が軽く扱われ過ぎているという視点は、あくまで「私から見た視点」なのかもしれないと思うようになった。その人にはその人の過程や過去があり、つまりは目を向けるべき「罪悪感」は人それぞれ違うステージのものなのだ。
そう感じるようになった時、ようやく落ち着くことができた。
罪悪感という言葉の羅列からは、各人の世界・段階を読み取ることが難しいというだけのことだ。

4・閑話休題
断捨離中の我が家ではあるが新しい仲間がお目見えした(旅行用バッグのことではない)。
料理教室で習った「雑穀たち」である。

ラッキーなことに量り売りのお店が近くにあるので、少量ずつ買っていろいろ試すことができる。保存容器は、今までキッチンに溜め込んでいた空き瓶だ。
改めて、いろんなものが棚の奥から出てくるなあと思う。
微妙なサイズだと思っていたこれらの瓶は雑穀のおかげで日の目を見ており、日本へ帰る直前まで活躍してくれることは間違いない。溜め込んでおいてよかったと言えるかもしれない。
いまのところ、雑穀入りスープと雑穀ごはん、雑穀ごはんを使った甘酒、その甘酒で作るキムチを作る程度にとどまっている。
心配していた家族の反応は、案外悪くなかった。
「白米をやめて雑穀ご飯に変えてほしい」という話ではなく、「雑穀ごはんはいつもあるから、食べたかったら食べられるよ」というスタンスでいるのがポイントだろう。スープなどの調理法の時は見た目が大事だなと、娘の反応から勉強した。
もう少し家のことが落ち着いたら、新しい料理にも挑戦してみたいと思う。
雑穀にはいろいろな種類がありそれぞれに特徴があるので、組み合わせや調理法などを考えるのは楽しそうだ。先生がワクワクしながら話をしてくださるのも、この自由さからくるのだろう。
私は極端な主義主張はあまり得意ではないが、生活の一部としてしれっと共存できそうな雑穀のことを知る機会があってよかった。
そして相変わらず、砂糖も小麦粉も米粉も、はちみつも乳製品も卵も、普段通りに使ってお菓子は作りたい。美味しいものが作りたい。
雑穀を食べ続けると食の好みが変わってくるという話も聞いた。
もし未来の私が変化するなら、それもまた面白そうだ。

7.1.2024
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
終活と呼べるもの

モノと向き合う
只今絶賛断捨離中、である。
そう、家にあるものを少しずつ売ったり捨てたりしている。
一般的にイメージされるように、子どもがいる家庭は荷物が多い。
周りにいるオーストラリアのお友達と同様、我が子にも一般的な書籍やおもちゃを買い与えたいし、また、私たちのルーツである日本の文化や行事も同時に教えたい。
庭にはトランポリンを置き、ガレージには自転車やローラーブレード、各種ボール類、家の中には楽器やコミック、クラフトグッズ、ぬいぐるみなどをところせましと並べてきた。学校からも勉強したテキストやノートや作品類が、毎年送り返されてくる。
一時帰国をすれば買い物三昧。
オーストラリアに戻る飛行機では、荷物の重さを100キロから120キロ分にしていたし、同時に船便も使っておもちゃやマンガ、昔話セットなどを送ったこともある。
お正月、節分、ひなまつり、こどもの日、クリスマスや誕生日。
日本の家族が気を利かせて定期的に送ってくれた季節の荷物は、届くたびにワクワクしながら箱を開けた。
イベントを祝いながら、家族みんなで楽しい時間を過ごしてきた。
最近はトラネコ兄弟も仲間に増えたので、キャットタワーやキャットウォークがリビングの一角を占拠している。
もちろん親である私たちにも歴史がありますからね、
荷物もそれなりにいろいろ。
我々の欲望を満たし続けた結果、家にはモノが溢れかえった。
でも、
モノがたくさんあるだけならば、たいして問題にはならない。
それぞれの品には思い出があり、自分を構成するものの一部と思えなくもないからだ。大切だと思う限りそばに置いておけばよい、よね。
それが、
物と向き合って処分を考えなければいけない状況に発展した。
我が家は、今年中に日本へ本帰国する。

地元のマーケット
昨年の5月から12月まで、月に一度開催される地元の日曜マーケットに出店参加していた。見取り図を確認するだけでも、プロアマ問わず180ものお店が一時的に立ち並ぶ賑やかなイベントだ。
編みぐるみ作品を販売する友人と共同して、お気楽な趣味の店を開いたのである。
私には少し前から、子ども達が描いた絵をグリーティングカードにして販売するという密かな野望があった。それで2022年のクリスマス・クラフトマーケットに出店したのだが、残念ながら売り上げはさっぱり。
そこで、次にマーケット出店が叶うなら、日本でキャラクターグッズや和風のものを調達して一緒に並べれば、目を引いて良いのではないかと考えた。家には子ども達が過去愛用したぬいぐるみなどもあるし、「ついでに家の不用品も売ってみようか」と話が進んだ。
当時はまだ、本帰国するから売るという訳ではなくて……。
子ども達が大きくなって、「モノ」よりも「スクリーン」で過ごす時間が増え、年齢的にもそろそろサヨウナラだろうかと思われるモノ達が、目につくようになっていたのだ。
初めは、小学生の頃に読んだ古本やおもちゃを店先に並べた。
子どものお得なものは足を止めるようだったし、アニメ好きな人々はグッズを手に取った。
中古であるにも関わらず、こちらで売られていない日本のアニメキャラクターのぬいぐるみを抱きしめて、「今年のバースデープレゼントはこれがいい」と親に交渉している高学年くらいの女の子を見た時は、少し感動した。
気をよくして、ちょっとずつ違う中古品も並べてみる。
反応が良くてすぐに売れたのは、ギターだった。
子供用大人用あわせて3本と付属品、アンプ。
それぞれに買い手がつき、あっという間にするするっと消えていった。
Nintendoのクラシックミニシリーズは、日本語バージョンだったにも関わらず、オージーのおじさんが「大丈夫、大丈夫。子どもは学校で日本語習ってるから」と嬉しそうに持ち帰った。
今や新品はプレミアム価格でしか買えない、7年ほど前に人気だった小さなプラスチックの着せ替え人形コレクションは、オンライン上に残っている情報をかき集めて名前とレア度を割り出し、中古とわかるパッケージを作って並べた。たくさん作ったので全ては売れなかったが、多くの人が楽しそうに選ぶ姿を見られて良かったと思っている。
余談だが、本当は手作りスイーツもマーケットで一般販売したかった。
しかし、認可されたキッチンと市の販売許可(有料)が必須だったので諦めた。5年ほど前の同じマーケットでは、さまざまな素人が好きな手作り品を売っていたのだけれど、近年は条件が厳しくなっていた。
さて一方で、全然売れないものもあってがっかりしたのだが、それらも含めオンラインに出してみることにした。
実は不用品を「譲る」のではなく「売る」ことに少し抵抗があった。
しかし、オンライン上では多くの人が思い思いの値段をつけて、中古品を販売している。
それらを眺めていると
「大切なモノを譲るのです」
という表現にも見えてきて、持っていた抵抗感はずいぶん小さくなった。
ビリヤードのキューと球、電子ピアノ、自転車2台、鯉のぼり、キャンプ用品やクラフトグッズなどがオンラインで売れた。知らない人とのチャットのやり取りがあまり好きではないので、少しずつ出しては様子を見ている。
売りたいものや処分したいものは、まだまだ山のようにある。

スーツケースひとつ
2002年にはじめてオーストラリアの地を踏みしめた時、私の荷物は大きめのスーツケースとリュックサックひとつだった。夫にいたっては、ドラムバッグとよばれるスポーツジムに持って行くような円筒状のバッグとリュックサックが、全ての荷物だった。
滞在許可証がワーキングホリデーからビジネスビザ、永住権と変化するに従い、増えていった我が家のモノたち。
再び日本に定住する時、持ち込む荷物は前回のようにスーツケース一つとリュックサックだけに戻りたいと思った。
実際には何箱か荷物を別で送ることになるだろうが、それでも引っ越しの規模ではないはずだ。
今回の断捨離は「ときめくかときめかないか」ではなく、
「本当に日本へ持ち帰る価値があるのか?」
で厳しく判断する必要がある。
まず、キッチン用品は日本でまかなえるので、ほとんど処分するつもりでいる。
大好きなお菓子作りの器具、とくに焼き型に未練は強いが、おそらくサイズが合わないだろう。
日本の環境にあった道具を揃えよう、と割り切る。
ガレージにあるもの、要らないな。
家具や寝具、洗面・掃除用品も無くて大丈夫。
化粧品や洋服は、旅行程度の量で良い。
本棚にずらっと並ぶ日本の小説やコミック類はどうだろう。
家族と最終的な話し合いが必要になるが、日本に行けばラクに手に入るものばかり。本当に必要なら、また買い揃えるだろう。
手元になくても、図書館や漫画喫茶で読むことができる。
オーストラリアで欲しい人を探した方が、有効活用といえる気がする。
日本のCDやDVDは悩ましい。
今やサブスクを利用すれば、多くのものが観れるし聴ける。
自分のコレクターアイテムとしてどうしても必要! と思うモノ以外は、あきらめよう。
私は「旅行より物」タイプの人間であったので、いいなと思って購入したものを手放すのはつらいが、ここは気合いだ!!
家計関連の紙の書類は、どうしようか。
大事そうなものはスキャンしてクラウドに保存するか……。
いつか、ひとつずつ向き合う時間を作る必要がありそうだ。
がんばれ、自分!
いちばん判断がむずかしいのは、プリントされた写真と手紙と子ども達の日記や作品(成長記録)。
ああ、、、、困った。

息子だけは、日本ではなく州内の都会へ引っ越すのだが、彼もまた、最低限の荷物しか持たない移動になるだろう。「オーストラリアの実家」は無くなるのだし、自分が管理できるだけの荷物と共に、新しい生活を築いてほしい。
私たちは、22年間に及ぶオーストラリアで過ごした生活の後始末をはじめている。
これってもしかして、
いわゆる「終活」なのではないか
と、思えてきた。
人生の折り返し地点を少し過ぎたタイミングの終活。
日本の小学校で行われているという「二分の一成人式」に少し似てるかもしれないな。
『立つ鳥跡を濁さず』
『来た時よりも美しく』
私たちは、
日本で新しい生活を始めるのにふさわしい、
一番身軽な人間になるのだ!

この文章を入力中のMacBookに、メールの着信音が響いた。
セールの先行案内だった。
6月はオーストラリアの会計年度末で、多くの企業が、年度内に売上を立てるための大規模セールを実施する。
サイトに飛び、 商品を、 クリック、 する。
いえ、あのね、
旅行用のカバンなんですよ。
スーツケースの取手に差し込めるタイプの、トートバッグなの。
飛行機の機内には、荷物二つまで持ち込めるんですよ。
リュックサックとトートバッグで、ちょうどよくないですか?
普段使いにもできる、便利な物なんですよ。
お小遣いで、買うんですよぉぉ…………
4.15.2024
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
お邪魔いたします

転入届
ハイスクールを卒業した息子が、現在日本に滞在している。
進学の時期を少しずらしたので、その間、日本での生活を経験しようという目論見だ。今までは旅行で、長くても一度に3週間程度しか滞在したことのない日本。
今回は3ヶ月近く、主に義両親宅にお世話になる。
彼は日本国籍があるので、とにかくまずは『市役所で転入届を必ず出すように』と伝えていた。そのため、日本に入国した際は、パスポートに入国のスタンプをもらうことを教えた。
現在、入国時は自動化ゲートを利用するのが一般的なため、入国を証明するスタンプはわざわざお願いして押してもらう仕様になっているらしい。これが、転入時に必要な書類となる。
スタンプが押されたパスポートを抱えて、息子は祖父母と共に市役所に出向いた。そして、残念なことに転入はできなかったという報告をくれた。
一年以上滞在する予定でなければ、転入手続きは受け付けられないのだという。
息子は「本籍は日本にあるが、日本の住所を一度も持ったことがない」状態だ。
現在、彼の身体は日本にあって生活をしているが、日本のどの場所にも所属していない日本人ということになる。現住所は出生届を提出したときの海外のままで、日本国籍保持者ながら、旅行者としてしか扱ってもらえないのだ。
「健康保険証はなくても良いから」と言っても、「アルバイトをすれば納税が発生するかも」と言ってもダメだった。(納税の必要がでるくらい稼げるかは置いておいて)
「予定」であれば、口では「一年住む」と言って「やっぱり予定が変わった」と転出すれば良いのでは? と思われるかもしれない。しかし、帰りのチケットを持っているにも関わらず、どれくらいの人がそのような行動を取れるのだろうか。
中核都市の市役所から「あなたは一時滞在者です」と告げられて終わった。
親知らず
住民登録できない。
それが何を意味するかというと、まず「国民健康保険」に加入できないということだ。
オーストラリアではかかりつけの歯科医院で定期検診を受けている。
少し前に受診した際、息子はハイスクール卒業のタイミングで親知らずを一度に抜いてしまうことをお勧めされた。
大きな病院(ホスピタル)へ出向き、全身麻酔をして4本抜くため日帰り入院になる。おおまかな見積りには、35万円ほどの記載があった。我が家が加入している任意健康保険を利用しても、なのである。
見積もりをもらった時に思った。
飛行機のチケットを買って、日本の歯科医にかかっても、きっとお釣りが来る。
今すぐ4本を一度に抜く必要がわからなかったし、親知らずで全身麻酔を受けさせることにも少し抵抗がある。
日本の歯医者へ行きがてら、そのまま少し住んでみたらどうかという話になった。
進学先はオーストラリアで、日本に住む予定はないのでいい機会だ。
住民票を入れて健康保険が使えたら、旅行保険はいらないし一石二鳥、とも。
結果、そんな楽観的な計画は実現できず、彼は実費で検診を受けることになった。
そして日本の歯医者さんから
「今はまだ、何もする必要がない」
と言われただけで終わった。
アルバイト
住民登録ができないと、就労体験をしたくてもアルバイトを見つけられない事態も発生する。
一般的に、本人の証明として住民票が必要な雇用先が多く、また息子の場合は17歳のため、年齢確認も必要になる。パスポートで国籍と年齢はわかるが、日本の住所は証明できない。
それから銀行口座の開設。
これが絶望的になる。
少し前であれば、パスポートの「現住所欄」に日本の住所を書いておけば口座が作れた。しかし、彼のパスポートは新しいもので「現住所欄」がない。その場合は、住民票を提出するわけだが、それが存在しないためどうにもならない。
今時、現金支給のアルバイトは少ないだろう。下手をすれば、指定の銀行に口座を作れと言われることもあるくらいだ。銀行口座がないと、給与の事務処理が大変になるだろうことは想像に難くない
息子はこの状況でもめげずに履歴書を送っているようだが、日本でのアルバイト体験はもはや絶望的になっている。
日本人でも
日本人なのだから、日本に住みさえすれば現在住んでいる人々と同等の権利が与えられると私は思っていた。
しかし、それには最低滞在期間という制限が設けられていた。
たとえば私たち夫婦は、永住権保持者としてオーストラリアに住んでいるが、あくまで永住権なので選挙権はない。
滞在期間が20年強と長くなってしまっても、日本へ帰るつもりでいるから「お邪魔してます」という感覚を持ちながら生活している。
一方、息子の場合は両国ともに国籍保持者なので、どちらに住んでも全ての権利が行使できるだろう、と私は思っていた。
だが、一筋縄ではいかないことを今回学んだ。
しょうがない。
そうであれば、せっかくの日本なのだから、楽しむ方向で過ごしてもらいたい。
などど書きつつ「ボランティア活動でもしたら?」と息子にうながす私がいる。
しょうがない。
母親は欲深いのだ。

2.10.2024
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
サイクロン・ジャスパー

豪雨による被害
お正月に発生した能登沖の地震より2週間ほど前、ケアンズにはサイクロンがやって来た。
サイクロンの規模自体はそこまで大きいものではなく、風雨が激しかったことと何度か停電があったことを経て、一旦弱まった。しかしそのまま雨雲は停滞し、100年に一度と言われる記録的な豪雨に見舞われる。
我が家のある海岸沿いエリアなどでは、浸水被害が発生した。
今の家に越してから10年が過ぎるが、これまでの豪雨被害といえば、主要道路が冠水したためこの地域が孤立した程度だ。しかも水は1日で引いたため、翌日はもう日常に戻っている。
ここに何十年と住んでいる近隣住人もそれぐらいの被害経験しかなく、今回も「大丈夫だろう」という楽観的予測に包まれていた。
ところが、歴代一位の降雨量を記録した今回のサイクロンは、道路だけでなく住宅をも水浸しにしてしまった。
避難をはじめた人々が出てきた頃、我が家の目の前の道路は川になった。
道路を流れる水は水位を徐々にあげ、我が家の建物に近づいてくる恐怖。
電気は止まり、スマホの電波を含むネット回線もほぼ壊滅状態。情報源のポータブルラジオからは、我が家のある地域名が連呼されていた。
しかし結果的に、我が家は住宅の浸水被害を逃れた。
その代わり、海岸沿いの道路の一部が海へ押し流され、河川からの新しい水路ができていた。おそらくこの抜け道ができたおかげで、道路を流れていた水が一気に海へ移動したのだろう。
私たちの家があるストリート(通り)が被害を免れたのは、この水路のおかげ。
住民はそう言い合った。

時系列
サイクロンにより身動きが取れなくなってしまったのは、12月13日(水)から18日(月)のおよそ1週間だった。簡単な時系列を記してみたい。
12月13日(水)14日(木)
ケアンズより少し北部にサイクロンが上陸。
何度かの停電があるも、その日のうちに復活する。
強い雨風のため、我が家からは出勤できない状態と判断した。

12月15日(金)
熱帯低気圧に変化し雨足が弱まるが、まだ断続的に降り続いている。
この日、クイーンズランド州では大学進学用テストの成績が発表されたので、息子の友人が他エリアから車を走らせて突然やって来た。
この日、特に高い大潮による水位上昇が心配されたが、災害のあった1週間のうち、この日は移動可能な条件だったようだ。
12月16日(土)17日(日)
「記録的豪雨」という言葉が使われ始める。
熱帯低気圧に変化したサイクロンは停滞を続け、この二日間に膨大な量の雨を降らせた。降雨量2メートルという、聞いたことのない単位を耳にする。
主要道路の閉鎖と開通が繰り返される。
避難する住人の話が出はじめ、同エリアに住む知人の家族は、屋根に登って救助を待ったという話をSNSで読む。
日曜昼には、浸水による漏電を防ぐ目的だろう計画停電が実施される。と同時にインターネットによる情報の取得も困難に。水道が糸の太さしか出なくなる。
そして日曜の夜、自宅の浸水に怯えていた頃、我が家から少し離れた海岸沿いの道路が決壊した。

12月18日(月)
雨はほぼ止み、曇り空に。
自宅の浸水から免れたことに安堵するが、様子を見にエリア内を車で進むと、浸水の跡が残る車両や家屋を目の当たりにする。
主要道路は甚大な被害を受けた箇所がいくつもあった。
我が家のあるエリアから街へ向かう道路はなんとか通れるようになっていたが、泥だらけ。復旧工事の都合だろう、「一旦外に出るとすぐに自宅へは戻れない」と関係者に告げられる。

12月19日(火)
街へ向かう幹線道路への出入りが自由になったため(住人限定)、私は宿泊施設である職場へ避難し、翌日からの出勤の準備をする。
夜には水道と電気が自宅に戻る。携帯の電波障害は改善するが、自宅のインターネットは年末まで戻らなかった。
また、夫の職場は街とは反対方面で道路が閉鎖されていたため、週末まで出勤することが難しかった。
脱出
雨が降り続いていた頃、「避難をするべきか否か」についてはずっと悩んだ。
緊急アラートはもちろん届いており、
安全に移動できるなら高台へ。
もしくは住居の高階層へ。
生命の危機を感じたら連絡を!
浸水が始まっていれば、どんどん水位が上がっているなら、生命の危機を感じて避難を求めるだろう。
しかし、まだ何も始まっていない自宅、家を出れば豪雨で道路は歩けないほどの濁流。
この条件では家にいる方が安全だと判断するしかない。
平静を務め、見守るしかないと思った。
そして結果的に自宅への被害は免れた。
停電、ほぼ断水の状態も3日間程度で解消した。
しかし、これはあくまでも結果論であって、不便を強いられている最中は「いつまでこの状態が続くのか」がわからない。
わからないための不安が常に付きまとっていた。
我が家には、ソーラーパネルも発電機も、貯水タンクも付いていない。
水道が出なくなり、浴槽に溜めていた水でトイレを流したが、どれくらいの頻度で流すべきか? そもそも一時は逆流しかけていたこのトイレを、どこまで信じて良いのか?
スマホの充電は車をアイドリングして行ったが、ガソリンはいつまで持つのか?
調理のためのカセットコンロのガスは、どれくらい慎重に使うべきか?
通電のない冷蔵庫にある食材と、食品庫にある食材をどのように食べていくべきか?
災害時の蓄えを準備していても、どのように計画的に使えば効果的なのかわからず、不安だった。
しかし同時に、すぐそばの別地域では、電気も水もインターネットも通常通りに使える環境が存在している事実が、心の支えになった。
いざという時、救助が期待できる安心感がある。
1週間の引きこもり生活の後、泥だらけの住宅地を超え、街へ向かう道路を車で走った。
何年かに一度浸水してしまうハイウェイ上の橋を通り過ぎ、ガソリンスタンドや動物の保護施設などがあるエリアまでやって来た時、急に景色が変わった。
そこには路面が茶色い泥に覆われていない、今までと変わりない日常が広がっていた。
避難生活の買い出しのために立ち寄ったショッピングセンターは、クリスマスの買い物客で賑わっていた。駐車場に停めた泥だらけの自家用車が、場違いに見えた。
被災した地域では忘れそうになっていたが、間もなくクリスマスを迎える時期だった。

自分にできること
記録的豪雨と時を同じくして、二台あった我が家の車が一台、全く別の理由で故障した。
長年加入しているロードサービスからは、我が家の住所は災害エリアのため侵入できないと言われ、1週間近く待たされた。夫の車が修理を終え使えるようになったのは、ラッキーが重なっても結局1月の半ばだった。
それでもインフラさえ戻ればすぐに住める家があり、一台でも動く車がまだある。
被害にあった住民と同じエリアに住む私は、ボランティアをする側に今すぐ回るべきなのではないかと強く思った。自分は大丈夫だったことが、逆にいたたまれない気持ちを生んだ。
しかしこの1週間、常に出勤できない理由を探しては自分を納得させ、申し訳ない気持ちでいっぱいだったため、自分の仕事を優先した(職場はさまざまな理由で人手不足だったので、結果的には良かったが)。
夫も私も、現在二つの仕事を掛け持ちしているため、車一台で出勤をやりくりするのは落ち着かなかった。子ども達の学校が夏休みで、送り迎えが不要だったのは助かった。
私たちができることは、すぐそばで配布されている救援物資を受け取らず、逆に物資を提供する側になること、自分たちで生活を回すこと、だろうかと割り切ることにした。
一個人としてできるサポートは、決して目立つことではなかった。
しかし、無理をして自分が倒れないことは重要だ。
宿泊施設の職場には、この災害で道路が閉鎖し、すぐには帰宅できなくなった宿泊客もいた。
予想外の速さで復旧したインフラも、そこで働く人がいるからこそ。
自分が自分の仕事をすることで、だれかの助けになっていると信じたい。

12.10.2023
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
ハイスクール卒業

先日、17歳の息子がハイスクールを卒業した。
オーストラリアの学年末は12月なのだが、息子の高校は、他校に比べると1ヶ月ほど早い10月の後半に卒業授与式を行って終了。
私たちはその会場で、一輪のバラと両親への手紙を息子から受け取った。
ご想像通り、私は、彼が初めて小学校の準備学年に通い始めた4歳の頃のことを思い出していた。
機関車トーマスが描かれた大きなリュックを背負って初登校した息子が、いよいよ自分の決めた進路に向かって歩み出すのかと思うと、なんだか感慨深い。
特に、いずれ日本へ帰る予定の私たち夫婦とは国が離れてしまう可能性が高いので、不安半分、信頼半分といったところ。
自分の人生、思ったように行動をしてほしいと思う。
今回は、日本で高校を卒業した私が、オーストラリアの高校生活に「これは違うなあ」と感じたことをいくつかご紹介したいと思う。
アルバイト
州によって多少の違いがあるようだが、13歳ごろになるとアルバイトが可能になる。
(日本は義務教育が終わってからだそう)
15歳にもなると、一時的でも多くの子が働いている印象だ。
特にファーストフード店のスタッフは、ハイスクールの子達とそれをまとめる年長者しか見かけないくらいで、一利用者として彼らにお世話になっている。
雇用形態はカジュアル(アルバイト)が多いと思うが、「パートタイムジョブを見つける」という言い方が一般的なよう。
日本みたいに学校側が禁止することはなく、学校関連の、たとえばシドニー旅行やニュージーランドへのスキー旅行など費用が高額になるイベントがあると「今からパートタイムで頑張って貯めて!」なんて言葉が、先生から投げかけられることも。
私は日本の高校に入学した時、スーパーマーケットで働けそうだったのに、学校の許可が出なかった。
(他の子は、上手にこっそり働いていたのだろうが)
今でもそれを悔しく思っているので、正々堂々と働ける環境が羨ましいと思ってしまう。
こちらの履歴書には、過去の勤務先の「推薦人」情報を記載することが一般的なので、早いうちにアルバイトをしておくのは将来の就職活動にも役立つ。
若いうちからの職業経験は、自分のスキルの一つとして考えられているようだ。
運転免許
日本では、高校卒業前に自動車の運転免許を取ることは稀だと思う。
しかし、こちらでは州が認める年齢に達すると、保護者の協力のもとで路上運転の練習をする子が散見される。
(ドライビングスクールもある)
クイーンズランド州では16歳になると路上練習に出ることができ、17歳になると本免許に挑戦できる。
つまり、早い子は11年生(高2)の時点で運転免許を取得してしまうということ。
免許を取ると車で通学する子も出てきて頼もしく感じるが、反面無事を祈りたくなる。
(想像してみて。学校帰りに複数人の友人を乗せ、ファーストフード店へわいわい乗りつける高校生たちを)
こちらも学校が禁止する話は聞いたことがなく(もしかしたら厳格な私立など例外はあるかもしれない)、本人(と保護者)の責任だと割り切りが良い。
若いドライバーは、初心者マーク期間が長く、任意保険も高額になりがちだが、それでも学校や習い事、アルバイトへの送り迎えをしなくてよくなり、楽になったと喜ぶ親御さんもちらほら。
卒業パーティー
ハイスクールの卒業パーティーはアメリカのプロムが有名だと思うが、オーストラリアでも「フォーマル」と呼び盛大に祝う。
今年は我が家も息子が参加するということで、先輩ママさんから話を聞いていた。
男女ペアで参加する時は、お揃いのお花のコサージュを男性側が用意するんだよ、とか
会場へ行くためのリムジン(LIMO)は、早いうちに予約しておかないと無くなっちゃうよ、とか
会場に入らなくても家族もドレスアップする、とか
どれだけ準備が必要なのか戦々恐々としていたところ、(親にとっては)ありがたいことに、ペアではなく仲良しグループで参加すると言う。
お花のコサージュは要らず、車もグループの親さんにお任せ。
息子はスーツと靴を用意するだけで済んだ。
息子の学校は国際会議なども開かれるコンベンションセンターを借り、生徒たちはレッドカーペットならぬ、スクールカラーのブルーカーペットの上を歩いて会場に入る。
このカーペットには運転手付きの車で乗りつけるのだけれど、それがまるで車の品評会のようで華やかだった。
実際、フォーマルで愛車を披露したいと思っている車好きな人もいるみたいだ。
飲酒可能な18歳も混ざっているがパーティー自体は学校のイベントなので、当然のことながらアルコールフリー。
保護者の我々は会場内を見ていないが、高校生活の締めの一つとして楽しい思い出を共有できたようだ。
仲間との二次会も終え、私が呼ばれて迎えに行ったのは夜中の12時になっていた。
普段ぼんやりしている息子が、スーツを着て凛々しくなったのを見て「馬子にも衣装」をリアルに感じた1日でもあった。
ギャップイヤー
高校を卒業して次の進学先が決まれば、同時期に一斉に入学というのも絶対ではないと知った。
進路先の大学やコースによるが、入学時期を最大1年間遅らせることができる。
「ギャップイヤー」と呼ばれていて、進学する前に思い切り働いてお金を貯めたり、旅行をしたり、ただ休んだりする期間を過ごせる。
大学などで勉強をするのは、高校を卒業したての生徒ばかりではなく、大人や留学生も多いので、それに対応するために、一年の間に入学時期が何度もあるのかもしれない。
こちらの大学は課題が大変で、入学一年目に離脱者が多いと聞く。
準備ができていない、と思う子には「優しい猶予期間」だと思う。
我が家も幾ばくかのギャップイヤー期間を取ることになりそう。
彼はケアンズではなくもっと都市での進学を希望しているので、住まいなどをゆっくり探していきたい。
我が家は息子が小学校に入る前年に、イプスウィッチからケアンズに引っ越した。
オーストラリアに永住するきっかけとなった「ワイナリー」の仕事から離れ、子育てを中心に暮らしていく方向に舵を切った瞬間だったと思う。
そもそも、この息子(第一子)が生まれる2週間前に私たち夫婦の永住権が降りたのは偶然だったのか?
日本人の子どもとしてオーストラリアで生きていく覚悟を決めて、生まれてきたようにも思える。
彼のこれからの人生を、ゆるやかに応援したい。

10.15.2023
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
秋の一時帰国

1 富山
残暑が厳しい9月に、再び日本へ舞い戻っていた。
今回は娘と私の女子トリップ。
訪れた場所は、飛行機の発着する大阪と私の実家の富山だけである。
私は高校を卒業後、進学のために実家を離れた。
北陸から東海へ南下しただけだが、間に挟む日本アルプスは思いのほか高く、カルチャーショックが少なからずあった。
曇り空が日常の日本海側から、明らかに晴れの日が多い太平洋側へ。
テレビのチャンネルは、転出時にようやく民放が3局に増えた県から、もともと全局見られる県へ。
市の端っこ、県の端っこにあった田んぼと工場しかない実家のエリアから、市の端っこでもなんだか賑やかな県庁所在地へ。
これまでオーストラリアからの一時帰国中に長く滞在するのは、決まって夫の実家であった。私たちが結婚をした地域でもあり、友人に会う予定を立てやすいから。
母が鬼籍に入った時に、1週間程度の滞在をした記憶はある。
しかし十日間も富山の実家に滞在するのは珍しい。
家族仲が悪いわけでは決してない。
むしろいい方だと思う。
今回は今までなかなか実践できなかった、私が生まれ育った自分の家族と長く過ごす貴重なチャンスだ。

2 精進料理
特に予定は決めていなかったが、富山で行きたい場所はあった。
その情報は、動画サイトを観ていた時に出てきた。
私たちが生まれ育ったのは、古い日本家屋。
大学生の頃に取り壊されているのでもう存在していないが、その家で、私たち家族は何度も仏事を執り行った。
仏事では、それなりの年齢になると、子どもでも一丁前に御膳が用意される。
提供されるのは肉っ気のない精進料理だが、その御膳にいつも出てくる三色のくずきりはタレが甘じょっぱくて印象的だった。普段の食事も精進料理に近いものではあったが、そのくずきりが食卓に出てきたことはない。
動画サイトではその三色くずきりをはじめ、いとこ煮やよごし、具の入ったがんもどきなどが並ぶ料理を紹介していた。それらの料理は、砺波地方独特の精進料理らしい。
それを古民家レストランで提供しているという。
法事に参加しないと食べることができないと諦めていた料理が、このレストランへ行けば堪能できる。このチャンスは逃したくないと思った。
妹たちも興味があるようだった。

3 農家レストラン大門(おおかど)
平日の昼時、休みを合わせてくれた妹二人と私は、散居村のなかにある古民家レストランに足を運んだ。
地図が示す場所は田んぼの真ん中で少し不安になったが、目的地の横に「大門そうめん資料館」が建っていたので、観光客が訪れるルートになっているのだろうと安堵して車を停めた。
一人暮らしを始めてから、母がよくこの大門素麺を持たせてくれた記憶がある。そのままでは長すぎるので、茹でる時に割る必要があるこのそうめんだが、砺波市の特産品だったということにこの時はじめて気がついた。
富山県には大門(だいもん)という地域もあるため、ずっと勘違いをしていた。
レストランに入ると、中は懐かしさを覚える住居を改装した内装。
畳の上にテーブルと椅子が並べられ、庭が見える席に座らせてもらった。
ランチタイムはお肉のつかない伝承料理がいただける。
お目当てだった三色くずきりのみならず、大門そうめんやゆべしなど、田舎で暮らしてきた私たち姉妹の楽しめる料理がたくさん並んでいた。
ゆべしは、我が家では「ゆうびす」と呼ぶ寒天料理。
溶き卵が入った醤油ベースのスープを寒天で固めたものだ。干し椎茸でだしをとり、そのまま具にもなっている。暑い夏の時期には冷蔵庫で美味しく冷やし、冬の時期は室内に置いたままでも大丈夫な料理。
母が作るゆうびすには千切りの生姜が入っており、それがアクセントになっていた。レストランのゆべしには入っていなかったので、母のレシピだったのだと改めて思った。
御膳には、抹茶塩の天ぷらもついており華やかさを添えていた。
法事の際に天ぷらはあっただろうか?
しかし野菜の天ぷらは母もよく作ってくれた料理のため、このランチは結果、母の料理を偲ぶような話題が増えた。
母が作ってくれた「ゆうびす」や「かぶらずし」「なます」などの伝承料理は、どうやら妹が引き継いでくれているらしい。
料理をいただきながら、いずれ、母の味を習いたくなった。

4 アズマダチ
古民家レストランは、私たちが生まれ育った日本家屋と間取りがとてもよく似ていた。
お客様玄関から家屋に入ると、左手側に広間や仏間がある。庭に面する部分は2から3畳程度の控えの間のような部屋が連なっており、実際、仏事の際はお坊さんに休んでいただく場所だった。
レストランのホームページを見ると、「アズマダチ」という言葉が書かれていた。
砺波平野に多く見られる伝統的家屋の形だそうだ。
ネット検索すると「となみ散居村ミュージアム」という施設があり、平面図が載っているのだが、こちらの伝統館1階の間取りがかなり似ている。
仏間には富山県らしい立派な仏壇が飾られ、その左側が床の間なのも同じだった。
実家には20畳ほどの広間があり、小さい時は室内運動場のように走りまわっていたことを思い出す。
私たちの「生家」はもうないが、このように現在でも存在している伝統的家屋を目にしたことで、懐かしい記憶が蘇った三姉妹のお喋りは止まらなかった。

5 日常
今回の旅行は、娘が日本の中学校へ体験入学をするのが目的だった。
四日間だったが、部活動の新人戦と14歳の挑戦(職業体験)の狭間という忙しない時期に受け入れていただいた。
学校までの道のりを娘と往復したり、ちょっとしたお遣いを父に頼まれたり、甥っ子自慢のパスタを作ってもらったり、妹たちと夕飯を作ったり。
「日常」に重きを置いた時間を過ごすことができた。
ラジオから流れる富山弁に改めて驚きつつ、私も努めて地元の言葉で喋った。随分忘れてしまったと思うが、それでも娘には新鮮そうだった。
「私の地元」の空気に触れ、自分のルーツを思い出していた。
日本の学校にも触れ、ちょっと緊張もした。
(歩行者は、道路の右側を歩くルールでしたよね?)
日本に住んでいた時、私はどんなことを思っていたのか?
そんなことを考えながら、やはり私は日本人だし、この国に戻ってくるのだろうと意識している。

8.5.2023
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
ハウスキーピングという仕事

1.
ハウスキーピング
この言葉を聞いて、
「ああ、宿泊施設のお掃除をする人のことね」
とすぐに理解できる人はどのくらいいるのだろうか?
少なくとも私が初めて聞いた時は家計簿のことかと思ったし、自分がホテルの客室清掃をする立場の人間になってはじめて使うようになった言葉だ。
(ケアンズは観光地なので、理解する人は多いが…)
そう、みんな知っているようで、案外知られていない仕事。
それがハウスキーピング。
ハウスキーピングは、基本的に繰り返し作業の仕事だ。
繰り返し作業のプロだと言える。
「お掃除が仕事です」
というと混同されやすい。
例えば賃貸の明け渡し時に業者がする清掃であれば、各個人がそれぞれの使い方で溜め込んだ汚れを次の借り手が気持ちよく引っ越して来られるような状態にまで回復しなければならない。状況に合わせて様々な薬品やツールや技術などを駆使して、設備への被害を最小限にしながら汚れを取り除く作業が多くなるだろう。
日本のYoutube動画で、時々見てしまうタイプの作業(私だけかも)。
しかしハウスキーピングの掃除はというと、「各個人がそれぞれの汚し方をした場所を清掃する」ところまでは同じだが、いつも同じ場所で、かつ介入する頻度が細かい。
ホテルであれば毎日だし、滞在者が掃除するタイプの宿でも、1週間に一度は定期清掃が入るはず。
この頻度を持ってして、汚れの蓄積を防いでいる。
時々、頑固な汚れなどに対する効果的な掃除方法を尋ねられることがあるのだが、あまり役に立つ返事をすることができない。
強いて言えば「いつも掃除していれば、まあ大丈夫だと思うけど」になる。
それができれば、みんな困らない。

2.
ハウスキーピングスタッフとしての私の経験は、専属のホテルで6年半、3社のホテルへ派遣スタッフとしてお手伝いを何度か、バックパッカー宿にてお手伝いを数ヶ月、そして現在働いている、医療を受ける人向けの宿泊施設で2年近くになった。
実際に作業をしたことがないと、おそらくピンと来ないと思われるので、ホテルで働いていた頃のある1日を簡単にご紹介しよう。
まず朝イチで、今日自分が担当する部屋の一覧を受け取る。
(私が勤めていたホテルでは、一人で掃除をするタイプだった)
1日に割り当てられる部屋数は上下するが12から14部屋前後。ホテルでは使用中の部屋も毎日掃除に入るため、この数はチェックアウトの部屋と使用中の部屋とが混ざったものになる(業界では12部屋で5時間が目安だと聞かされている)。すでにチェックアウト済みの部屋を優先的に、どんどん掃除を進めていく。
掃除には、汚れ物を処分し掃除機をかけたり埃を取ったり、バスルームを磨いたりするほかに、テレビなどの備品がきちんと使えるかの確認、ベッドメイキングや次のゲストの人数分のタオルなどを用意する作業も含まれる。手持ちのシーツやタオルが足りなければ催促し、部屋に備え付けの書類やコップの数が足りなければ走り回って調達する。
全ての部屋をあるべき姿に整えられたら、ようやく1日が終わる。
ゲストからのクレームが来ないように、綺麗に間違いなく。しかし管理者からのクレームもないように、指示された時間内でなるべく終われるように。
この相反した要求を一身に受けて、毎日同じ作業を部屋の数だけ繰り返すのだから、繰り返し作業のプロになるのも然り。
掃除に使用する薬剤は各ホテルで決まっているため、この汚れにはこの新しい薬品を試そうか、というタイプの掃除とは異なるのがお分かりいただけるであろうか。
家に持ち帰る仕事もなく、新しい気持ちで毎日を迎えることができる環境だが、繰り返しの作業は肉体を駆使するため、じわじわと身体にくる。腕や手のひら、腰、膝など慢性的な痛みを訴えない人の方が少数だろう。また、接客業でもあるので、ゲストから厳しい言葉を投げかけられる場合もある。
完全なるホテルの裏方でありながら、感じの良い接客も求められる、肉体も精神も使うそんな仕事であった。

3.
ホテルを退職した際、ハウスキーピングの仕事には戻るまいと思っていた。
時間内にどれだけ綺麗にできるか、日々できることを増やす挑戦を自分自身に課していたため、やれるだけのことはやったという気持ちがあったし、もう肉体労働は疲れたとも思っていた。
しかし、つなぎのために登録した派遣会社では、飲食の仕事に呼んでもらえるようにアルコール取り扱いの免許をとったにも関わらず、紹介されるのはハウスキーピングの仕事ばかりであった。
体を動かしていない時期は、いかに自分がなまくらになってしまったかということを考えた。ホテルの頃は親が心配するくらい痩せていたので、多少体重が増えることは問題なかったが、キビキビと動いていた頃を思い出すと自堕落になったように感じた。
そして、娯楽がメインのホテルとは異なり、医療系の宿泊施設はより公益性が高いのではと判断したため、結局ハウスキーピングの仕事に戻り現在に至る。
毎日、シャワーブースの掃除をしながら
「なぜ私はこの仕事を続けているのか?」
と考える。
私は自発的に体を動かすタイプの人間ではないので、「収入を得ながら運動ができるから」かもしれないし「繰り返しの単純作業が好きだから」かもしれない。
掃除の仕事は、やればやっただけ結果が目に見えるものであるため「やりがいが分かりやすい」し、「療養中のかたのお役に立てているかも」とも思える。
そして、ハウスキーピングの仲間はいつも優しい。
実際のところ1日3ー4時間程度の仕事量なので、ホテルに比べると肉体的な辛さは減ったが、これだけで生活をするのは難しい。そのため、別の仕事も週2で入っている。こちらも別の肉体労働で、なかなかハードだ。
しかしどちらも、だれかがやらないと社会がスムーズに回らない裏方の仕事であったりする。「だから私は働いている」と考えてしまう自分を、面倒くさいなあと自分で思う。
ホテルの頃は、窓のサッシを拭きながら「もう辞めなければいけない」という言葉が常に頭に浮かんでいたのだが、今のところ「なぜこの仕事を続けているのか?」という疑問ですんでいるので、現在のハウスキーピングの仕事はもう少し続けるだろうと思う。

6.10.2023
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
日本で出会ったハプニング

1. 横浜の出禁おじさん
3月末から2週間半、5年ぶりの日本を、中高生の子ども二人と一緒に家族四人で旅行した。
大阪・奈良、金沢・富山、東京・横浜、岐阜・愛知、そして大阪とぐるっと回ってケアンズに戻ったのだが、その濃密な時間の中いくつか面白い体験をした。
まずは横浜で出会ったおじさんについて書きたい。
私たち家族は東京から岐阜へ移動する途中、横浜に住む友人を訪ねた。
友人カップルはお酒を出すたこ焼き屋さんをやっており、私たちの到着時間に合わせ、いつもよりも早く店を開けて待ってくれていた。
「久しぶりだねえ」
「この川沿いの場所は落ち着くなあ」
などと談笑し、美味しいたこ焼きを頬張っているところに、自転車でふらふらとやってきた一人のおじさん。
「生ビール一杯いいかい?」
と注文すると、当たり前のように私たちに話しかけてきた。
はじめは横浜のこの辺りの話。
わたしは『地元の人とふれあえるなんて珍しい』と思って一生懸命に耳を傾けていたのだが、「戦時中はね、私の両親はね、兄弟はね」などと、だんだんおじさんの自分語りが強くなってきた。
横浜という土地柄なのか、昔は家族で海外にいたなんて話になったから、
「私たちも海外からですよ」
と伝えてみるも私の言葉への反応はなく、自分語りが止まらない。
はじめはみんなで聞いていたと思うが、気づいたら私一人が相手をしている状況。
「兄さん、姉さんはそれぞれ違う国で生まれて、自分の両親はどんな仕事をしていたのか、いまだにわからないんだ(ニヤリ)」
という話になってくると、いよいよやばいかな?
これは、解放してもらえないかもしれないぞと不安になった頃に、友人が「勘弁してください」と、割り込んでくれた。
聞くと、近所で有名な出禁おじさんだったらしい。
いろんなお店で嘘なのか本当なのかわからない話のワンマンショーを繰り広げて、拒否されてきたそうだ。
そうか、私は真剣に話を聞いていたから嬉しかったのだろうか。
とても生き生きと話していた姿が印象的だった。
珍しい人に会って面白かったけれども、友人との再会を喜ぶ時間がその分ぐっと短くなってしまったのは、やはり残念だったと言うしかない。

2. カプセルホテル
名古屋では、大学時代の友人達と会う約束をしていた。
岐阜の小さな大学に通っていた私たちは、仲良し6人組。
関東、中国地方、そして東海地方と普段はバラバラに散らばっている彼女達が、私の一時帰国をきっかけに集まってくれた。
6人もいると、それぞれのライフステージが異なったり、単純に予定がつかなかったりして、これまで全員が一度に集まるのは難しかった。
私も(当時お金がなくて)結婚式に駆けつけられなかったり、また、高山や香港旅行なども参加できなかった。
前回、みんなで集まったのはいつだっただろうか?
「別れるときは、また明日会えるような感じで、いつもサラッとさよならしてるよね」
なんて話していたのも、ずいぶん昔だ。
誰かが欠けてしまうのはしょうがないこと、今、集まれたことを喜ぼう。
そんな感覚だったと思う。
しかし今回は、念願の6人全員で会えることになった。
そして自宅が遠いチームは、名古屋で宿を取ることにした。
いいところがあると聞いたよ、と名古屋に住む友人が紹介してくれたのは「いろいろ付いたカプセルホテル」。
無料の「大浴場」「ソフトドリンク」「夜の時間はアルコール」「ご飯とお味噌汁」などなど、何も持ってこなくても様々なものが用意してあるタイプの宿だった。
カプセルホテルは、日本独自の珍しい形態の宿泊施設であるにもかかわらず、私たちの誰も泊まったことがなかったし、紹介してくれた彼女も然りだった。
「面白そう!」
ってことで3人分予約したのだが、当日、チェックインをして初めて知った事実。
カプセルのある眠る場所では、喋ってはいけなかったのだ!
他の利用客が24時間いつ眠っているかわからない場所です。
お静かにお願いいたします!
しかもカプセルを見たあとに「閉所恐怖症気味」なのよと告白しあう友人と私。(カプセルの中に入ってみると、案外大丈夫でした)
冷静になればなるほど、なんで予約した? ということに……。
「いい宿はないか」と探してくれた名古屋の友人は、自営業で各地を飛び回る生活をしている。そんな彼女に対して、便利だよと紹介してくれたのではないかと思っている。
予約の段階では、私も含め皆がバタバタしており
「宿が取れた? よかった、よかった、一安心」
という感じだった。しょうがなかったのだ。
居場所を求め、ドリンクや軽食のあるフロアに移動するも、お通夜なのか? と思うような静けさ。館内着を着てお目当てのドリンクなどを片手に持ち、うろうろ単独で行動する利用客。その中に3人グループの我ら。奥にある喫煙ルームからはタバコの匂いがうっすら漂う。
基本的に一人で利用するお客さんが圧倒的に多いため、賑やかなグループ客は敬遠されるようだった。蚊の鳴くような声で私たちは話す。
ロッカールームと大浴場は普通に話せる場所だったが、長居をする場所ではないよね。
尽きぬ話をするために集まっているのに、それを禁止された私たちは、一人旅以外でのカプセルルーム利用はないなと反省をし、翌日に予定していた「大人の遠足(ノリタケの森とプラネタリウム)」に期待を膨らませたのであった。

3. お土産
日本の旅の締めといえば、なんといっても荷物!
段ボール箱につめた衣類や本、食品などを、事前に夫の実家から空港の郵便局に送りつけ、飛行機に乗せるというのは、毎回の最重要ミッションである。
子ども達が小さかった頃はそこにおもちゃも加わり、合計10箱なんてこともあった。
今回も同じように、まずは段ボール箱5箱を用意し郵便局のサイトを一応確認すると、なんと空港の支店が消えていた。
今まで使ったことはなかったが、存在は知っていた民間の荷物受け取りサービスカウンター。
こちらは開いていたので、その住所を指定することができた。一安心。受け取りも無料で行えたし、最後、空港で買い足したお土産を入れるための余分な段ボール箱を購入することもできた。
よし、次は買い物だ! と勇んだところ「店」が無い!!
5年前にはあった目の前のコンビニ、お土産物屋さん、書店、100均ショップや各種専門店。
パンデミック期間中のあれこれで、
なんと、なんと、
ほとんどのお店が閉店していた。
新幹線の売店で、道中の荷物になるからとお土産物を躊躇するのではなかった。
荷物受け取りカウンターでは、梱包用テープも箱とセットになって売られていたのは、100均ショップがなくなったからか?
かろうじて見つけられたのは、工事中のエリアの間にコンビニと薬局ひとつずつ。
薬局にはお土産物がひっそりと少量、置かれていた。
空港でお土産物を買えばいいと油断していた私は、薬局でようやく光を見た。

4. 最後の最後
よし、荷物は準備OK。
預けるぞ!
ジェットスターのカウンターは、、、
どこだ?
ない。
電光掲示板を見ると、私たちの便はC2だかなんだかの表記。
あれ? 関空も、第2ターミナルができたんだっけ?
格安旅客機はそっち?
関空の第2ターミナルへは、無料の専用バスに乗る必要があった。
バス停まではエレベーターを使って地上に降りて少し歩く。
そこへ来たバスに、カートに積んでいた段ボール箱6個とスーツケース二つをおろして載せる。
バスから降りると、またカートを拾って荷物を積み直し、第2ターミナルの中へ。
女性「ここにジェットスターのカウンターは無いみたいですね」
「……」
第2ターミナルのバス停に戻った。長蛇の列。皆、荷物はコンパクト。
一つ目のバスには乗れないだろうと諦めていたところ、乗りなさい、荷物も載せなさいと世話を焼いてくれた職員のおじさんの存在があった。
ありがとう。
絶望の淵から救われました。
ここでは家族の団結力が試されていると思った。
誰も文句を言わず作業する。
荷物が置けるところに立っていた人には、場所を少し譲っていただく。
バスから降りる。
そしてまた、荷物をバスから下ろす。先ほど置いていったとおぼしきカートを拾って載せ直す。エレベーターに乗って第1ターミナルの出発ロビーへ再び戻る。
1時間近くロスをしただろうか?
その頃にはCカウンターにジェットスターの表記が出て、受付を待つ乗客の列ができていた。
しなくてもいい移動だった、ということを知る。
ただ、間に合ったことに安堵した。

今回の日本旅行では、有意義な時間を過ごすことができた。
降り立ってすぐに食べた日本食に感動し、観光地の外国人旅行客の多さに圧倒されつつも親近感を覚え、ドキドキしながらマスク無しで出歩き、桜の時期にもなんとか間に合った。家族4人がそれぞれ撮影した写真を共有アルバムにし、特急しらさぎにはやっぱり子ども達だけで乗り、ズワイガニを一杯ずつ食べ、ジブリ、秋葉原、推し活、家族、友人。
いくつかスパイスの効いた体験もしたが、あとになれば全て思い出。
さて、またケアンズでの日常を過ごしましょうか。

4.10.2023
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
ケアンズ国際空港にて

1. 一時帰国
ただ今、ケアンズ国際空港の搭乗エリアで、飛行機に乗る時間が来るのを家族で待っている。
今日は子どもたちの一学期の最終日だが、1日前倒しでホリデーを始め、2日遅れで二学期を始めると学校に連絡をした。
オーストラリアではよくある流れの、学校をあまり休まない頑張った予定を組めたと思っている。
2020年の一時帰国予定が幻となってしまったため、我が家にとっては約5年ぶりの日本!
ワクワクドキドキ、そしてうっすらと不安。

前回の帰国時は娘が小三、息子は中一だった。
5年経つと、当然ながら娘は中二で、息子はなんと高三になってしまった。
はっきりと記憶の残る年齢の時期を、ずっとオーストラリアで過ごしてしまったのだなと、少し悩ましく思う。
日本の情報はインターネットを通して知ることができるので、そこまで浦島太郎ではないと思うけれど、肌で実感することはできないので「ようやく」という気持ち。そして息子の年齢を考えると、もしかして、この旅行は4人での最後の日本旅行になるかもしれない貴重な時間。
そういう訳で、あまり色々と周遊しない我が家にしては珍しく、今回は奮発して関東と関西の両方に宿をとった。
おじいちゃんおばあちゃんの住む地域は北陸と東海なので、日本のまんなかをぐるっと回る予定だ。
2. 搭乗エリア
搭乗手続きを済ませ、手荷物検査、そして出国手続の流れにしたがう。
機械化された出国手続きに驚きながら、すでに一人でも手続きの作業ができるようになった子どもたちの成長を改めて感じた。
息子の友達は、飛行機乗り継ぎの国内旅を一人でしたり、別の子はイギリスに留学中なので一人で国際線に乗ったりしている。
特急「しらさぎ」を子どもだけで乗れたね!
なんて褒めたりする年齢でもないだろうが、なにげに箱入りな子どもたちなので私の感動の沸点が低いのはご容赦を。
出国手続きが終わると進む方向は免税ショップの中にある。
そこを通り抜けると、あとはお土産もの屋さんが三つとカフェが一つしかない待機場所。
以前は巻き寿司のお店もあったような気がするが、あれは主要都市の空港だっただろうか……?
たまにしか来ない私の記憶はあやしい。
唯一のカフェには、コーヒーや軽食を求める人の列が絶えず、我々もまずはその列に並んだ。

国際間の移動が再び活発になったとはいえ、閉まったままのお土産物屋さんを見ると、間にパンデミックを挟んでいたことを実感する。
羊の皮のマットやアグブーツ(羊毛で作った暖かい長靴)を販売していたお店には、今まで足を踏み入れることすらなかったけれども、ないのかと思うとわがままなもので、商品が見てみたくなる。
子どもたちがまだ幼かった頃は、ここにある本屋さんで絵本や児童書、お絵かき帳などを購入し、機内での時間に備えた。
離着陸時に、耳抜きがうまくできるようキャンディを用意してなめさせたり、搭乗直前まで人気のない場所で走ったり体をうごかして疲れさせ、機内で眠りやすくなるように工夫していたのもはるか昔のこと。

今は、皆がそれぞれのスマホやデバイスを駆使して、自分で時間を潰す準備をしている。
ちなみに私はこの通り、エッセイを書いたり、写真を撮ったりしているのである。
3. 他国のコイン

空港へ来たら、いつも決まってすることがある。
それは他国のコインを寄付すること。
ホテルでハウスキーピングの仕事をしていた頃、自然と集まってくるのが海外のコインで、その扱いに困っていた。
お金なのできちんとしたいし、でも有効利用の方法がない。
それぞれの国の出身者を探して譲るというのも面倒な作業。
そんなとき、コインの行き先を空港で見つけたのだった。
それは搭乗エリアにある募金箱。

オーストラリアドルのみならず、各国のお金が普通に入っていた。
日本へ帰るたびに、ここへ入れることにした。
今回は5年ぶりの国際旅行のため、行き場に困ったコインがまだ私の手元にあった。
パンデミック直前に、ホテルの仕事自体は辞めているので大した量でもない。
さきほど募金箱に入れてやっと肩の荷が降りた。
募金の行き先を見ると「フライングドクター」と書いてあった。
病院がそばにないリモートエリアの急病人などを、空のルートを使って運ぶサービスを行なっているものだ。
コイン程度ではたかが知れた額だと思うけれど、ほんの少しでも誰かの役に立っているなら嬉しい。
旅のついでに有益なことをしたという気持ちにもなれておトク。
オーストラリアドルが余った旅行客のかたも、旅の締めにちょっとした募金をするのも良いかもしれませんね。
さて、そろそろ搭乗時間が近づいてきた。
「気をつけて行ってきてね」
と送り出してくれた、友達や職場のスタッフに良い土産話ができるよう、これから楽しんでまいります!
日本の桜がすでに満開だという話は聞いているので、間に合うかどうかは到着してからのお楽しみ。

2.8.2023
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
裸足

1. Easy Going
先日、スーパーに来た女性が「寒いわねえ」と言って買い物をしていた。
真夏のケアンズであるから外は暑く、食品を扱うスーパーの中はそのぶんエアコンが効いている。
我が家の子ども達は寒がりで、夏でも買い物の際は長袖を持参するタイプだ。
彼女もそうなのかと思って何気なく足元を見ると、裸足だった。
申し訳ないが、冷えた床を直に感じるなら寒くても仕方がないだろう。
指摘したいところをグッとこらえた。
オーストラリア、特に常夏のケアンズにおいて裸足は文化かもしれない。
街の中心部に無料プールがあることもあり、水着や上半身裸などラフな服装で街を歩く人がいるのはごく一般的な光景で、足元も多くの人はサンダルだ。
裸足の人もいる。靴を買うお金がないわけではないと思う。
なぜ?
と問われても専門的な知識は持ち合わせていないが、Easy going(気楽にいこうよ)気質があると言われているこの国なら、全くおかしくはない。
裸足の人、靴を履いている人、サンダルの人が入り乱れる光景は、肩肘を張らなくても生活できる場所の象徴のように見える。
裸足なのがそんなに気になるのか? どちらでもいいじゃないか。そんな声も聞こえてきそうだ。
裸足で外を歩く人は、大人も子どもも性別も関係ない。
ためしに「オーストラリア 裸足」で検索してみると、たくさんの記事や画像がヒットして面白い。
多くの日本人が驚き、そして「へぇー」となっている。
一方就業時間中は、常時履き物をはいていることが規定されている場合がある。
身の安全を守るためのワークブーツ着用が筆頭に挙げられると思うが、かつて私の職場で「靴を脱いでいた時の事故は、勤務中の保険の対象外になる」と明言されたこともある。
それはホテルでハウスキーピングの仕事に就いていた時で、それほど重いものを運ぶ仕事ではなかったが、靴下はだしでの転倒などを懸念されたのかもしれない。
仕事で脱ぐなと言われている履き物であればなおさら、フリータイムになったら脱ぎたくなるのは性だろう。
日本ではどうだろうかと思い返してみた。
ベランダであろうとちょっと外に出る時に、必ず何か履き物を用意するなぁ。
私の記憶している20年前までは、少なくともそうだった。
私の育った家は古い日本家屋で、トイレが家族用玄関の向こう側にあった。
なのでトイレに行くときは必ずサンダルを履いたし、トイレ繋がりで言うと、大学生になって引っ越した一人暮らしのアパートにある狭いトイレですら、私は専用のスリッパを用意していた。
足を汚したくないという意識が、知らず知らずに染み付いていたように思う。
スーパーに裸足で買い物に来ても、誰も気にしない寛容なオーストラリアとはいえ、入店を拒否される場所はある。
ドレスコードのある高級レストランなどはまず無理だろうし、安全のためだろう、DIYショップでも弾かれる。
どういう経緯だったろうか海へ行ったわけでもないのに、夫が珍しく裸足で車を運転、そのまま降りてDIYショップに入ろうとしたことがある。
そして、入り口に常駐するスタッフに「履き物をはいて出直すよう」入店を断られた。
急いで近くのスーパーに行き、ビーチサンダルを買って事なきを得たが、休日の油断した頭に喝を入れられた瞬間だった。
在豪歴が長くなったと感じた瞬間でもあった。

2. 子どもの場合
お友達の家など、子ども達が遊びに行った先で忘れる筆頭が、履き物だ。
水着や水筒、デバイスなどの入ったカバンは忘れないようにいつも注意するが、最後の最後にちょっとだけ遊んでしまって、裸足で車に乗り込んでしまうことがよくあった。
今日は忘れないぞと思っていた日は、今度、別れ際に親同士で話し込んでしまって、気づいたら子どもが裸足に戻っていた時なんかは、さすがにせめられない。
「靴履いた?」は受け入れ側も、お迎えの側も合言葉のようになっている。
学校から直接お友達の家に遊びに行った日などは、それを忘れると「明日の学校にはいていく靴がない!」事態が発生する。
そんな時は玄関先に忘れた靴を出しておいてもらって、通学時に寄り道して履き替えた。
親側のやりくりも楽ではありませんよ、ほんと。
子ども達にとって裸足で外遊びをすることはごく一般的な感覚で、公園や庭などで初めは履いていたとしても、気付けば脱いでしまっている。
公園などに忘れてしまうとまず見つからないので、高価なものを買い与えないのは生活の知恵であると私は思う。
娘の通った幼稚園でも、あらためて写真を見返すと裸足で遊んでいた。
しかしこれが小学校に入ると事態は一変する。
朝9時ごろから3時ごろまで、ずっと靴を履くように指導されるのだ。
一番若い子はまだ4歳半。
学年が低いうちは、教室の椅子に座るより地べたに座って活動する時間が長いこともあり、靴を脱ぎたくて癇癪を起こしてしまう子もいると聞く。
入学準備学年というのは、こういったルールに少しずつ慣れていく期間でもあるのだなとしみじみ思う。
私だって仕事の時は靴を履いているが、帰宅の車に乗り込むや否や常備しているサンダルに履き替えてしまう。
裸足とまではいかないが、仕事が終わったという解放感を足からも味わえて良い。
そういえば私が小学生の頃は、暖かい季節になると「はだし運動」の期間が設けられ、校内や砂利の敷き詰められた中庭でも裸足で過ごすことができた。
砂利の上を歩く時は足ツボマット並みに痛かったけれど、楽しかった記憶がある。
裸足の解放感は時に、大地と繋がっている「アーシング」も感じることができるだろう。
感覚が敏感な子どもの頃に裸足で過ごす恩恵は、日本の学校教育でも認知されるものだったのだな。
ただし、我が家では街中を歩く時、子どもが裸足になることは禁止してきた。
割れたお酒の瓶の破片など、危険なものが落ちていることがよくあるからだ。
ちょっと過保護に思えなくもないが、危機意識を持つきっかけにもなるだろうと信じている。

3. 裸足じゃないの?
サンダルを履いていたために、嫌味を言われたことが一度だけある。
それは某プレイグループ(未就学児向けの遊びグループ)での出来事だった。
月曜から金曜まで日替わりで異なったプレイグループが使用している施設があり、普段私はそこの日本人プレイグループに参加していた。
あるとき知り合った女性が別の曜日のリーダーをしていて、遊びに来てよと誘ってもらった。
自然派を謳う教育方針に共感する人たちのグループで、遊んでいいのは木など自然素材のおもちゃだけ。
はじめにパン生地をみんなでこねて、ランチに焼けたパンを食べるというのが楽しそうなグループだった。
私は自宅でパンを焼いていたので親しみも感じた。
遊びに行くと、プラスチックのおもちゃがある場所を知っている娘はそこを開けたがり、私はそれを阻止して頑張って外遊びに誘うはめになった。
そうこうしていたら「ここは誰でも来ていいグループなの?」と、明らかに私を意識した様子で質問している女性の声がした。
その場では親も子どもも裸足になって過ごすのが決まりだったようで、それを知らなかった私はずっとサンダルを履いたままだったのだ。
裸足になり自然と繋がることを拒否している人間が、そのグループに紛れ込んだように見えたのかもしれなかった。
私の興味で参加したけれど、我が家には厳しいなということは早々に気づいていたので、彼女の質問は良いきっかけになり、ランチになる前にお暇することにした。
このグループの共感する教育方針の書籍は以前から持っていたが、実生活に落とし込むことはできずにいた。
私が裸足にならなかったことで拒否反応を示された唯一の経験は、いわゆるおもちゃに囲まれてテレビを見せる暮らしをしていた我が家とは、方向性が少し違うグループだったのかもしれないという再認識の経験にもなった。

4. 足の皮の厚さ
日本へ一時帰国して、友人のお子さんと一緒に遊ぶ機会に恵まれると
「ほんとに裸足になるんだねえ」
という話になった。その場には、靴のまま遊具で遊ぶ友人の子2人、裸足になって遊ぶ我が子2人の面白い対比だった。そのうちみんな裸足になって遊んでいた気がする。
ケアンズの公園で遊んでいるお子さんが、履き物のまま、特に靴下とスニーカーのフル装備だったりすると「旅行客かな?」 とまず思ってしまう。
最近は我が子の年齢が上がり公園に行く機会も激減したし、パンデミックの制限でしばらく旅行者を見かけることもなかった。
これからまた、現地の子ども達と旅の子ども達が交差する機会が増えるのかと思うとほっこりした気持ちになる。
などとまあ、しかし偉そうに言っていますが、こちらの生粋の(?)裸足族のみなさんは、暑い道路を歩けたり少々の障害物も平気な様子なので、私たちはそこまでの境地には至っていないことを白状しておきます。
実は足の皮の厚さが、これからの生存競争を勝ち残る要因の一つだったりして。
だとしたら、庭の人工芝の上を「熱い! あつい!」と飛び上がって歩く私はまだまだ修行が足りませんね。

12.15.2022
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
実感する師走

1. 二つ目の仕事
一年前の今頃は、時間が余っていた。
当時新しく始めた仕事は、ケアンズで医療を受けるために遠隔地からやってきた人やその家族のための宿泊施設の清掃。
ホテルのお部屋を6年半掃除してきた経験から、清掃の仕事はいつも人手が足りないイメージをもっていたが、この職場では3ー4時間も働けば1日の仕事が終わる。
仲間の清掃スタッフも、基本的に3時間で帰ってしまう。
もちろん仕事量が多い日もあるが、翌日に持ち越したりと工夫して短時間で終える。
オーストラリアでの1日の最低労働時間は、3時間と決まっている。
確かに面接時に「3時間は確保する」と言われたが聞き流していた。
集中して体を動かす仕事のため、時間が短くても疲労するので、そういった配慮があるのかもしれない(皆の年齢は私よりも高い)。
しかしランチタイムの街中に開放されると、稼ぎに行ったはずが出費のほうに傾いてしまうので困る。
そんなこんなで今年の前半は、平日の午前中は不可という条件で二つ目の仕事探しに奔走し、最終的にスーパーの青果部門でのお仕事を得た。
こちらの仕事では、一度に6ー7時間というまとまった時間がもらえる。
勤務日は週2、3日で、清掃の仕事もある日は合計10時間勤務を超えることになるが、週末があったりどちらかだけだったりとバラエティがあった。
この仕事の組み合わせだと、働いていてもまだ空いている時間に友人とランチを食べに行く予定を立てられたり、髪を切りに行く都合もつけやすいという利点があった。収入が増えたので、こういった出費も安心してできる。
やっと落ち着いたと思った。

2. 加速
安定を感じていた頃、スーパーの部門責任者が変わった。
オーストラリアではよくあることだが、仕事が理由ではない引っ越しや、単純にキャリアを変えたくなったという理由で退職する人は多い。
特に管理者サイドに多い傾向があると感じている。
ヒラのスタッフの場合、時々同じ職場に舞い戻る人もいる。
そしてまた辞めたり戻ったりを繰り返すなんて話も聞くが、それはさすがに稀か……。
そのあたりから人手が少しだけ手薄になり、私の勤務日数が週3、4日に増えた。
急な病欠の人が出れば「今日働けないか?」という問い合わせや「出勤時間を前倒ししてくれないか?」という連絡も増えた。
朝、目一杯働いている日が多いので、地味にきつい。
しかし、その後出勤して仕事量に困るのは自分なので、また悩ましいところなのである。
最低賃金が世界でもトップクラスのオーストラリアで、雇われ仕事があるだけよいのですがね。
話は変わって、ここのエッセイを読んでいただけたからなのか、今年の初めに「書くお仕事をしませんか?」というお誘いを知人から受けた。
対象者を探してから話が進むお仕事で、ずっと探していた候補者がようやく見つかったのが奇しくもこの時期。
応募書類を作成したり、そのためのインタビューのスケジュールを組むなど、それまでの空いた時間はMacBookの前で思考をすることが増えた。
実は、書くお仕事というのはぼんやりとだが「いいな」と思っていた。
20年前に来豪してから自分のウェブサイトを作ったり、日記サイトやブログなどに文章を書きなぐってきたこともあり、書いたり表現することは好きだ。
中学生の頃、将来のなりたい職業を発表する授業があって、編集者を選んだことがある。
子どもの頃は、アイドル雑誌やバンド系音楽雑誌を読むのが大好きで、特に音楽雑誌では、通常のアーティスト記事のほかに編集者の発言もよく載っていたのが楽しそうに見えた。
しかし「編集者」を選んではみたものの「競争率が高い」という一文を見て、発表には使ったが実際に目指すのは辞めた。
基本的にそういう競争は、好きではなかった。
なので、書くお仕事に誘っていただけた時は嬉しく、また、その内容も楽しいものであったため取り組みたいと思った。
もちろん、昨年このStay Saltyにエッセイを書きませんかと誘っていただいた時も、大変嬉しかったし同時に緊張をした。
なにぶん、ほかの方の領域に私の文章が載ることなど、これまでほとんどなかったし、デザインをお仕事にされている方に、私が撮った写真を渡すのも勇気が必要だった。
それでも掃除や品出しで肉体を使い、書くことで頭を使うというのは、努力の方向が分散していて面白いと思っている。

3. そして、グリーティングカード
もう一つ書くと、私は地元の週末マーケットで、ブースを持ってみたいと思っていた。
そこで販売するのは、子どもたちが描いた絵を印刷した、お手製のグリーティングカード。
「Happy birthday」や 「Merry Christmas」「Thank you」などと書かれていたり、また文字のないオールマイティーなものを中心に考えている。
種類が少ないかなと思ったので、これまで私が撮ってきた写真でも作ることにした。
カードの活動は、2年前からできたらいいなと考えていて、でも実行できなかったことだった。
それがさまざまな勇気の後押しをいただき、実際に行動に移せたのは、やはり忙しくなったこの時期。
週末マーケットでの販売ブース予約はなかなか取れず、手元には出番を待つカードの種類が増えるばかりだったけれど、ついに今月半ばに開催される『クリスマス・クラフトマーケット』に出店が決まった。
先月も行われたこのクラフトマーケットを視察した際、週末マーケットにいる人々より素人感が強いブースも少なくないと感じた。
プロのようなディスプレイは無理だと不安だったので、敷居が低くなった分、趣味の一環であるこの活動を単純にたのしめる気がしている。

現在は忙しさの佳境で、今月のエッセイもそのことを書くしかない状態なのだけれど、私がこの状態でいられるのはすべて家族のおかげ。
子どもたちはそれなりに自分のことができるようになり、多少の家事も頼める。
とりわけ感謝をしているのは夫で、フルタイムの安定した仕事を続けながら、毎晩美味しい食事を作ってくれている。
私の体調も心配してくれる。
私が言う「忙しい」には、肉体労働からの体力を回復させるための時間も含まれているので、なおさら時間がないのだけれど、そういったことに罪悪感を感じなくても「忙しい」に集中できる現在が有難いなと思う。
ちょっとした無理がきくのも今のうちという意識があるので、それを楽しんでおきたい。
そして、
年が明けたら私のホリデーだ!
HAVE A WONDERFUL FESTIVE SEASON!!

11.7.2022
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
マンゴーの季節

1. 初めて食べる
有名ギフトショップによる日本への宅配マンゴーの予約販売が、今年も始まった。
この宣伝文句を見かけると
「ああ、もうお歳暮のシーズンか」
としみじみ思う。
時を同じくして、スーパーにも早稲の品種が並びはじめた。
そして近所の大きなマンゴーの木には、これでもかというほど青い実が鈴なりにぶらさがっているので、野生の小動物たちは、熟れるのを今か今かと待っていることだろう。
私がオーストラリアに越してきた当時、まだ日本では、マンゴーもアボカドも一般的に出回るような食品ではなかった。
そのため、こちらの八百屋さんで見かけたとき、恐る恐る手に取ってみるという感じだった。
それこそアボカドをフルーツだと思い買ってみて
「甘くない」
と、食べ方がわからず途方に暮れた経験もある。
当時はまだ、納豆や巻き寿司に入れるとおいしい、ということを知らなかったのだ。もったいなかったなあと、今になっては思うけど。
マンゴーに関しては、幼い頃にドライマンゴーを食べたことがあった。
家族のフィリピン土産で、肉厚な半生タイプ。表面には白い粉が吹いており、ハズレにあたると筋ばかりで悔しかった思い出がある。
私はその甘酸っぱいドライマンゴーが好きでよく食べたけれど、生のマンゴーを食べる機会は日本ではついぞ訪れなかった。
こちらで初めて食べた時の記憶はもうなくて、でも格子状に切り込みを入れて、プリンっとひっくり返して食べたのは間違いないと思う。
美味しかったと思う。

2. 自宅にあるマンゴーの木
イプスウィッチの家に住んでいた頃、裏庭にマンゴーの木があった。
金婚式を迎えたご夫婦が住むお隣の木は、彼らの歴史を象徴するかのように巨大で見事だった。
並んで、我が家のものは植えてからまだそんなに経っていなかったようで、私の背丈ほどの小ぶりな木に、実が二、三個つく程度だった。
しかしとても美味しそうに生っていたので、ポッサムやコウモリに食べられないように、熟すまでビニール袋をかぶせてみたことがある。
そのままおいしく熟した実もあったし、袋ごとかじられた実もあったはず。
美味しいものへの執念があるのは、人間だけじゃないんだなと思ったと同時に、硬いプラ容器を使って入れば食べられなかったはず、と悔しくなった。
私の方が執念がすごい。
ケアンズでは、メゾネットタイプの家に住んでいたときに、裏庭のフェンスの向こう側に大きな木があった。
我が家の屋根を覆うように茂っていたので、夜寝ていると
ゴン、ゴンっ
とマンゴーが落下して屋根に当たる音が聞こえる時期があった。
翌朝裏庭に出ると、落ちた時の衝撃で潰れているものからきれいな形をそのまま保っているものまで、さまざまな状態のマンゴーが転がっていた。
私にとっては宝の山。
これは幸いとばかりに、状態の良いものを厳選して収穫した。
ダメなものはフェンスの向こう側へ投げた。
もともと向こう側に木があるのだし、市が管理している雨が降ると川になるシーズナルクリークで問題はないので、念のため。
食べきれない量を収穫した時は、皮をむいてから冷凍する。
冷凍したものはそのまま食べるというより、マンゴープリンなどのスイーツを作るときに重宝するので便利。スムージーに入れる人もいるだろうけど、一瞬で無くなるのがもったいないという気持ちになり、スイーツにしてしまう。
まあ、スイーツにしたところで、瞬殺なのは変わらないか……
しかし、スイーツにしてもしなくても、我が家でマンゴーを食べるのは私だけ。
子どもたちはもともと興味がなかったところに、学校でマンゴーの木の下の掃除を手伝わされて嫌いになってしまった。つぶれて、発酵した時の匂いが強烈すぎたらしい。
ケアンズに住んでいれば、いたるところにマンゴーの木があるので、このような経験から嫌いになってしまった子が一定数いるのではないか? と私はにらんでいる。
マンゴーは、独特な香りを放つ開花の時期も、実がなる時期も存在感が強い。

3. 日本にて
ところで屋根にマンゴーが落ちる家に住んでいた頃、日本へ一時帰国した際にマンゴー売りのお兄さんに出会った。2011年ごろだと思う。
近視の手術をして病院を出た直後に、路上で声をかけられたのだ。
「国産の高級マンゴーを売り切らないと帰れない。買ってください」
などと言いながら近寄ってきた。商品保証をすると言われたような気もする。
要は押し売りなんだけど、扱っているフルーツがマンゴーだというのに心ひかれた。しかも日本産は食べたことがなかった。
ひとつ三千円ほどしたと思う。
「オーストラリアの自宅には、マンゴーの木があるんですけどねえ」
と言いながらも、二つ買ってしまった。
高額な手術をしたあとというのが、普段とは違う状況だった。
おそらく売り手はそれを狙っていたんだろうと思う。
しかし重ねて言うが、扱っていたのが日本産マンゴーだったから買ってしまった。
義両親家での夕食後のおやつに、ちょうどよさそうだった。
幸運なことにとても美味しかったし、ちゃんとした商品でよかったと胸を撫で下ろした。
(商品自体に罪はないけれど、今売りに来たなら絶対に買わない)
現在の自宅には、残念ながらマンゴーの木はない。
お店で購入するか、誰かからのお裾分けをもらえたらラッキーという感じだ。
特に誰かのお家でとれたマンゴーは、地産地消というと大袈裟かもしれないけれど、地域のパワーが宿るような気がする。
そろそろまた、マンゴースイーツが食べたいなあ。
今度は何を作ろうか?
そんなことを考えるのも、楽しいひと時だなと思う。
10.7.2022
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
日本行きのチケット

1. 幻の2020年9月
子どもたちが学校に通いはじめてから、日本へ一時帰国するのは決まってスクールホリデーのシーズンだった。
3~4月のイースターホリデー(秋休み)、6~7月の冬休み。
9~10月の春休み、もしくは12~1月の夏休みのうちのどれか。
そのなかでもクリスマスシーズンは、私たち親の仕事の都合でむずかしく、また、寒いのが嫌だという理由もあって、常に却下されてきた。
「そのうちに!」と思っているのだが、来豪以来、日本で年末年始を過ごしたことはない。
このシーズンにしか食べられない故郷の味「かぶらずし」を食べられるのは、いったいいつなんだ?
そんなことを思いながら、暑いケアンズの夏に溶けている。
日本のお花見シーズンにも重なるイースターホリデーは、いつも人気で、航空券の安売りはなかなかお目にかからない。ケアンズにいるオーストラリア人にも
「サクラ!」
「ハナミ!」
と言わせる時期のため、セールに出すまでもないのだろう。
我が家は安い時しか購入しないので、選べる日付は、いつもオーストラリアの冬休みか春休みばかりだった。
2020年1月末にセールが出た時も、購入したのは、春休みである9月のチケット。
しかも今までで一番お値打ちな金額で、家族4人で約1400AUD。一人当たり350ドルで日本を往復する計算になる。
「よい買い物ができた。帰りは100キロの荷物もつけたし~」と浮かれていたのもごくわずかのあいだ。
みなさまもご存知の通りの、パンデミック宣言。
国際線の運行は軒並み運休となり、2年ぶりの一時帰国は泡と消えた。

2. バウチャー
約1400ドル分のチケットは、航空会社のバウチャーになっていた。
使用期限は一年だったので、なんとか使いたい。
もったいない。
日本へ帰るはずだった時期、代わりに近場の旅行を計画した。
そういえば、航空会社のウェブサイトでは、ホテルやレンタカーの手配もできる。
だったら、ケアンズ近郊にある高原、テーブルランドエリアの宿を予約する時に、バウチャーが使えるかもしれない!
一縷の望みをかけてコンピュータに向かったが、航空券とセットにしてくださいという案内が出て撃沈。
宿は、普通に予約して、普通に支払った。
同じように、海外に行けなくなった人々が、近場の国内旅行に切り替えて発散しているようだった。それまではすいていたキャンプ場も、パンデミック以降、ホリデーシーズンは満室で、予約が取りづらくなったと聞いた。
私たちが利用したのもキャンプ場のキャビンで、1LDKタイプだった。
美しい湖畔を眺めながらも、
「本当なら日本にいて、家族や友人と会っているはずだったのに」
という思いが頭をかすめたりした。
それでもまだまだ不安な時期に、カモノハシを探したり、湖の周りを散策して、家族でリフレッシュできたのでそれはよかった。

3. 2021年6月のブリスベン
ステイホームが推奨されたり、ロックダウンが何度かおこなわれるなか、バウチャーの使用期限は迫ってくる。
依然として日本への国際線は運休を続けており、そちらに使うことはできない。
そもそも出国するためには、国の許可が必要な時期。
「親族が危篤」ではダメで「死亡が確認されて、はじめて許可が降りる」という話を、多方面から聞かされていた。
やはり国内旅行か。
そのうち「一度はスターバックスに行ってみたい」と娘が言いだした。
ケアンズにスタバはないので、ブリスベンへ行く必要がある。
そうか、ブリスベンならユニクロやH&Mもあるぞ!
子どもたちは洋服を買うのに中途半端な年齢で、試着の必要がある。
日本にいる間に、まとめて洋服を買う習慣になっている我が家は、そのチャンスを逃してしまい、ちょっと困っていた。
問題なのは、ブリスベンはこの時期、スクールホリデーのたびロックダウンになっていたことだ。
つまり、学校のある時期に旅行へ行くしかない。
ただし、息子は学校を休みたくない人間。
その結果、土曜の朝にケアンズを発って、日曜の早朝にブリスベンのホテルを出るという強行スケジュールが組み上がった。
日曜の真夜中にケアンズに戻るという選択肢もあったけれど、さすがにそれは現実的ではないという判断で。
猫を飼いはじめたこともあり、夫が留守番を申し出てくれたので、私と子どもの3人分を予約した。
バウチャーをなるべく使い切ろうと、飛行機の座席指定を少しグレードアップしたり、五つ星ホテルを予約して、なんとか1360ドルまで積み上げた。
40ドルほどまだ残っていたが、さすがにもうあきらめた。
息子用の追加ベッド台とほぼ同額だったが、それだけは現地払いと表示されたので、募金の気持ちであきらめた。
一泊半日の短い旅行のなか、スタバ、ユニクロ、H&M、そしてラーメン屋さんという、日本に帰っていたら通ったであろうお店をハシゴすることができた。
締めはクリスピークリームドーナッツを空港で受け取ったことで、こればかりは田舎に住むオージーっぽい行動だなと思った。
ミッション・コンプリート。

4. 期待の2023年4月
募金だとあきらめたバウチャーの残りは、知らないうちに使用期限が延長されていた。
それに気づいたのは、つい最近のことである。
今年に入ってから、ケアンズ・日本間の直行便が復活し、いよいよ我が家も日本へ一時帰国する計画を立てたのだ。
来年の4月のイースターホリデー。
その2週間滞在できるチケットを、確保することができた。
現在の最低価格の日付で選んだのだが、支払った金額は、前回バウチャーになった分の3倍ほどにふくらんでいた。
それでも、日本の桜のシーズンに、良い日付で予約できたのはラッキーだったと思う。
実は、日本のマスク人口の高さや、入国時におけるワクチン証明書もしくはPCR検査の結果を求められることなど、帰国するにはまだ敷居が高いと思っていた。
それでもチケットを買う気になったのは、日本に住む家族から、遠い親戚が若くしてお亡くなりになったという話を聞いたのがきっかけだ。
「会えるうちに会っておかないと」
「チャンスのあるうちに帰国しておかないと」
と強く思った。
実際に帰国する半年後は、日本側の入国の条件がゆるい方向に変わっているかもしれないという期待を、ほのかに持っている。
そうならなかったとしても、5年ぶりに家族と会えるのは単純に嬉しい。
実家にいるあいだに、世界一美しいと称されるスタバにも足を運べるといいな、なんて思ったりしている。
夫側の実家にいるときは、やはり金華山だろうか。
薄墨桜は、まだ散っていないだろうか。

9.5.2022
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
バナナを買う

1. オーストラリアの無人販売所
野菜の無人販売所。
日本人だったら
「あーあ、見たことあるよ」
「畑の片隅に小屋を建てて売ってるとこでしょ?」
って、自分の記憶をたどる人が多いのではないかと思う。そして、
「日本は平和で真面目な人種だからできるけど、他の国にはないでしょ?」
なんて思ってしまうことも。
日本には、あらゆる自動販売機がさまざまな場所に設置されている。
そして、売上を立てることができるのは、壊そうとする人がいないからだ、なんて聞く。
オーストラリアでは、屋外で自動販売機を見かけることがほぼ無いので、『そんなものかな?』と思っていた。
『無人販売所も無いよね』とも。
いつの頃からだろうか、私がほぼ毎日通るハイウェイの脇に、トレーラいっぱいのバナナが置かれるようになった。
そこは、ハイウェイを運転する人が、大型車でも停まって休憩できるような少し広めの場所になっている。
ケアンズの街中から、北へ向かって進む側にあり、この先の主要な町の名前が記された大型の看板も立っている。
11年前に私たちが引っ越してきた頃は、そこに小さなフルーツの有人販売所があった。
バナナ、マンゴー、パイナップルなど南国のフルーツが並ぶ。
ケアンズ近郊ではフルーツ農園を見かけることが多く、その販売所はそういった農家のメインビジネスなのか、
お小遣い稼ぎなのか、とにかく、直販っぽい感じがいいなあと思っていた。
しかしそのうちフルーツの販売所は消え、気づいたら、バナナがいっぱい詰まったトレーラが無人でぽつんと置かれるようになっていた。

2. 無人で大丈夫なのか?
比較的治安が良いとはいえ、軽犯罪自体は少ないとは言い難く、近年子どもたちによるゲーム感覚の車の窃盗・破壊が深刻な社会問題になっているケアンズ。
ハイウェイ脇にも、乗り捨てられた車を見ない日がないような状態である。
そんな中で、無人のバナナ販売?
悪さをする人はいないのか?
無人販売が長く続いている理由について、私の勝手な主観になるが、少し考えてみたのでおつきあい願いたい。
まず、基本的に車でなければ来られない場所であるということ。
ハイウェイと言っても日本の高速道路と違い、一般の道路と縦横無尽に繋がっている。
それでも人口が密集しているエリアから少し離れており、頑張って自転車で来られるかな? という感じだ。
ハイウェイとは反対の側に、歩行者・自転車専用道路が通っているが、太陽の日差しがきついことが多いので、体力的にどうだろうか。
ちなみにハイウェイの時速は80km/h。
そして、ここはハイウェイの両側からも見晴らしの良い、開けた場所である。
バナナを購入する人は、基本的に走っている車に背を向けた状態になるので、誰に見られているか、わからない。
それから、バナナの入ったトレーラは夜になると回収される。
朝、通勤通学の時間帯には、すでにそこにある。
しかし、夜少し遅い時間に通ると、トレーラは回収されてなくなっていた。
夕方にはトレーラ内のバナナが見えなくなるくらい売れていることがあるので、補充と料金回収を毎日行なっているようだ。
また、この場所にはオーストラリア名物のビーフパイを売る移動車が、いつも停まっている。
単純に休憩目的の大型車なども停まるが、パイを購入する人も停まる。
それよりなにより、このバナナ販売所、とっても人気だ。
何台も車が止まっていて、トレーラに向かって行列をなしている光景は一般的。
パンデミック禍でも、行列は消えなかった。
これだけ人気なら人目があるので、お金を入れずにバナナを持っていく人は少ないだろう。
あるSNSで「私は先にお金を入れてからバナナを選んだのに、支払いをしてないと後ろの人に言われて嫌だった」という投稿を見た。
誤解はあっても、とりあえずお互いに監視の目が働いているのだなと思った。
最後に、売っているのが重くて安いバナナだというのも、無人販売にできる条件なのかもしれない。

3. ここでバナナを購入してみた
さて、我が子どもたちはバナナを食べないため、私はいつも素通りするだけだったが、先日勇気を出して(!)車を停めた。
季節が冬のケアンズでは、大手スーパーでもバナナの価格が現在$4.50/kg前後。
しかし、この販売所では$2.00/kgと表記されていた。
シーズンになったら、もっと安かったような気がする。
私は、午後の仕事として、スーパーの青果コーナーで品出しをしているので、普段からバナナがよく売れるのを体感している。
金額がその半分以下だったら、合流が面倒なハイウェイ脇でも、車を停めて買いたいと思うだろう。
私がここを訪れたのは、子どもたちを学校に送った帰りで、朝9時にならない時間帯。
反対側はまだ渋滞しているが、私の進行方向の車はまばらだった。
それが「停まってみようかな」と思う後押しになった。
ただ、ほんの気まぐれで立ち寄ったので、現金の持ち合わせが車の小銭しかない。
2ドルを握りしめてトレーラに向かったら、その手前で、パイナップルを売るおじさんも見てしまった。
奥には、いつものビーフパイを売るおじさんが座っている。
パイ屋さんではカードが使えるのを知っているけど、いやいや、今日はフルーツだけなんだ。
わざわざ停まったからと、欲が出そうになるのを抑える。
1ドル分のバナナ2本と、格安1ドルのパイナップルを入手した。
そして、気さくなパイナップルのおじさんの写真も!
ここでは、バレンタインや母の日などのシーズンにお花を売る人もいて、ローカルのちょっとした憩いの場所になっている。
最近は、観光客のかたも再び見かけるようになってきたので、このような場所で、ローカル気分でフルーツを買うのも楽しいだろうと思う。
7.11.2022
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
在豪21年目の文化理解

1. 非営利団体での仕事
このStay Saltyではエッセイストという肩書きを使用しているが、私が現実に収入を得ている仕事は、清掃と店員である。
私たちは21年前に「文化交流」を名目として夫婦で来豪し、そのまま住み着いてしまったのだが、現在でも私の二つの仕事両方で、いまだ、文化交流というか、少なくとも私の視点からの文化理解を継続しているように感じている。
店員の仕事の方は、オーストラリアの他に、インドネシア、韓国、ミャンマー、フィリピンなどさまざまな国からやってきたスタッフと共に働いており、現在のオーストラリアを象徴しているように思う。
もう一方の清掃の仕事については、少し歴史に踏み込むような文化交流かもしれない。
平日の午前中、非営利団体の宿泊施設にて、キッチンなどの共有スペースと各個室をきれいにするのが、私の清掃の仕事だ。
この施設は、遠方に住み、医療にかかる必要のある本人やその家族が利用するという特徴を持つ。料金も安く、政府のサポートと組み合わせると、無料になる利用者もいるそうだ。
ケアンズという場所柄、トレス海峡の島々、北端や内陸、果ては近隣の国からの利用者も過去にはあったと聞く。
この仕事は昨年9月に採用され、オンライントレーニングを受講した。
そこで大きく時間が割かれていたのは、人権を蹂躙する違法行為に加担しない、それに気づくということに始まり、オーストラリア先住民に対する知識と理解などであった。
オーストラリアでは、国内に住んでいた「アボリジナル」、北端からニューギニアの間に位置する島々の「トレス海峡諸島民」の二種類のルーツを持つ人々が、先住民と呼ばれている。それぞれに象徴する旗も存在する。
以前住んでいたイプスウィッチ(クイーンズランド州・州都ブリスベンの西隣に位置する市)では、西洋人の文化であるワインの仕事に関わっていたためか、先住民と呼ばれる人々との縁はなく、せいぜいブリスベンの観光施設で関わる程度であった。
ケアンズに引っ越してきてからも直接の交流はなかったが、街で先住民らしき人々を見かける率が、イプスウィッチの頃よりもぐっと増えた。すぐそばには、ヤラバー(Yarrabah)というアボリジナルのコミュニティ地区もある。
そもそも、私が採用された求人募集欄には「先住民優遇」の文字があり、私はダメ元で応募していた。
雇用はタイミングやご縁の要素があるため、現在スタッフの一員として働いているわけだが、なぜ、上記の但し書きがあったのかについては、実際に働き始めてから理解することになる。

2. 先住民優遇の理由
この施設の利用者の大半は、先住民系の人々だ。
私が以前、ホテルで清掃員として働いていたことや、同僚に先住民系のスタッフが少なくなかったことなどを面接時に話したため受け入れられたようだ。ホテルで一緒になった仲間のルーツが、この仕事とのご縁を繋いでくれた。偶然とはいえ、彼らに感謝したい。
清掃業務には4人のスタッフがおり、2人が先住民系、1人が白人、そしてアジア人の私という構成になっている。
ここで働いていると、この施設はホテルよりもスタッフと利用者との距離が近いように感じる。
宿泊予約も担当するフロントスタッフと利用者の人々は、体調について話すことが多い。その流れでだろうか、清掃スタッフに対しても利用者のかたから話しかけられることがある。定期的に利用する人がいることも、距離が近くなることの一因だろう。
病気・ケガの話や医療用語などがでてくると、日本語でも知識が少ない分野であるところに苦手な英語が相まって、私はうまく返事ができず、お恥ずかしいところだ。
他のスタッフは長く働いていることもあるだろうが、『よくわかるよ』というスタンスで話しているのを見ると、同じバックグランドを持つからだろうかと想像してしまう。掃除スタッフの中で私が一番若いから、というのも病気などの知識が少ない原因かもしれないが。
それから、男性利用者の部屋に女性スタッフだけが入ることや、その逆は好まれない文化のコミュニティがあるようで、それぞれに独特な風習があるかもしれないことを知った。
実際には、男女混合のチームで清掃をすることが多く「入らないでほしい」
と言われたことはないが、そういった文化的背景を理解するのは、同じルーツを持つ人々の方が、話が早いだろうと思う。また、医療に受診しなければいけない体調のかたが多いわけだから、気持ちも不安定になりやすいだろう。そんな時は、同じ文化圏のスタッフに対してのほうが、親近感がわきやすいかもしれない。
もちろん、先住民系の人々の就職先として門戸を開いておきたいという部分は、大前提としてあるだろう。

3. 他人を理解するということ
アボリジナルコミュニティに関しては、グループが細かく分かれており、それぞれに異なった言語や習慣などがあるという。そのような地図も存在する。
例えば子どもたちが通うハイスクールでは、校長先生が「Kurrinyala!(Welcome!)」という言葉をニュースレターの冒頭によく使うが、これはケアンズエリアのアボリジナル・Yidiny peopleの言葉だそうだ。
職場の別部署にも先住民系のスタッフが何人もいて、ある男性の出身コミュニティは、ケアンズエリアとは別で離れた所だという。
引っ越し先のこちらのコミュニティをリスペクトしながら生活し、利用者の出身コミュニティに対しても理解を深めていると話してくれた。
それぞれのコミュニティに、大切に思っているルールなどが存在する。
ケアンズの街を歩いていると、時々、大声を張り上げて叫んだり喧嘩をしている先住民らしき人たちを見かける。
当然のことながら、そういうラフな態度の人ばかりではないと頭では理解しているが、どうしても目立ってしまうのは否めない。そして、普段の生活ではそのような人々ばかりに目がいく。
しかし、悪目立ちをする人ばかりが先住民ではないだろう。
実際、この仕事でさまざまな人々に会う機会を得て、少しずつ体験が伴ってきた。
宿泊施設利用者の方々が、私が一般的だと思うおだやかな生活をされていたり、部屋をきれいに保とうとしている痕跡を見ることがある。
妊娠中のお母さんが、幼児を引き連れている様子。
ご年配の夫婦が、お互いに労っている様子。
共用キッチンから漂う美味しそうな食事の匂いや、のんびりテレビを見たり、話しをしている様子。
私が仕事をしていて、「嫌だなあ」と条件反射で思ってしまうことはある。
体調が悪くて部屋を汚してしまうのは、よくあること。
でも、ただ面倒くさくて汚す人、掃除をする人にも感情があることなど気にしない人もいるだろう。それはおそらく、どの国でも人種でも同じ。
掃除をするという立場なので、ひどく汚されるとガッカリするし、「なぜ?」という気持ちも湧く。ただ、汚しかたが独特だと、そこにも文化の違いがあるのだろうかという発想は起こる。
私には私が育ってきた文化圏の常識があり、それを受け入れてほしいという気持ちがある一方で、別の文化圏の常識を持つ人々が存在し、それによって行動しているのだろうとも思う。
アジア人の自分は、この職場ではマイノリティに当たると思うが、だからこそ「理解しよう」という気持ちが働きやすくなっているのかもしれない。
まだまだ、私の文化交流・理解は続く。




5.5.2022
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
ビスコッティ

1. バースデイ・パーティー
子ども達が産まれたイプスウィッチからケアンズに引っ越し、上の子が小学校に入ると、年に2回ある子ども達のバースデイ・パーティーをどうすればよいか、ということにいつも頭を悩ませていた。
オーストラリアでは大人になってからでも、特に区切りの良い年齢の年は盛大に祝うなどと見聞きしていたので、これは「重要任務」だぞと思っていた。
それまで呼ばれたことのあるパーティーといえば、職場の仲間の娘さんが成人になったお祝いも兼ねて、自宅で賑やかに行われる大人向けのものだった。
庭仕事や大工仕事を主に請け負っていた職場の仲間は元ドラマーで、楽器を鳴らしたりミラーボールが回るなか踊ったりしていた。みな、大いにお酒を飲んで「うえーい」と盛り上がって、そのまま雑魚寝して朝を迎えるといった感じ。
彼らの自宅は、隣家が離れたところにしかない田舎にあったため、騒音公害の心配はない。私はいつも、そのノリに完全には乗り切れないタイプだったけれど、十分に楽しんでいた。
当時はワイナリーで働いていたこともあってか、お酒があって、夜は適当に雑魚寝だったり寝具を持ち込んで、といったパーティーが多かったように思う。
子どもが産まれてからは、ワイナリーにある旗立てを利用して鯉のぼりを飾り、こどもの日パーティーを開催したことがあった。それ以外にも、日本人プレイグループでバースデイを祝うこともあった。
ワイナリーは、オーストラリアにおける私たちのホームグラウンドだったし、プレイグループはみんなで協力し合う雰囲気が強かったので、個人的なプレッシャーは少なく、楽しみながら準備ができた。
ところが、もともと知り合いのいなかったケアンズに来てからのパーティー開催は、全てが自分で、しかも英語で小さい子を仕切るという不安もある「重要任務」。
初めてお友達を呼んだパーティーは、近所の公園で、とにかく食べ物だけは子どもにも大人にもたくさん用意することにした。
ディップとクラッカー、ひとくちソーセージなどのつまめるものから、唐揚げや、海老のサラダ。
ロリーと呼ばれる甘いグミや、クッキー、ポテトチップスなど定番の菓子も並べた。
子ども向けのバースデーケーキは、アイスクリームをケーキの形にデコレーションしたものだったが、それとは別で、小さな子の子育てにいつもお疲れの保護者のため、マロンクリームを使ったロールケーキを焼いた。
トッピングには、コーヒーフレーバーの地元産チョコレートを乗せると、予想以上に私好みに仕上がった。
このパーティーから何年も経ったある日、当時参加してくれたママ友であるNさんから
「あの時のビスコッティが美味しかった」
というコメントをいただくことになる。
私は、パーティーにビスコッティを焼いていたことすら忘れていたので驚いた。
マロンクリームのロールケーキのことばかり思い出しては、いつかまた作りたいなと思っていたからだ。
彼女からの一言で、「私のビスコッティ」作りが始まった。


2. お惣菜屋さん
ビスコッティが美味しかったというコメントをいただき、それならばまた焼いてみようと、手元にあるレシピ本を久しぶりに開いた。
ビスコッティはイタリア生まれのとても硬いお菓子だ。
紅茶やコーヒーにひたして食べるのも一般的だろう。
ただ、私の持っているレシピはオーストラリアのもの。
ワーキングホリデー時代の友人が、プレゼントしてくれた本に載っていた方法で作っている。
だからだろうか、私が作ると、クッキーよりは硬いけれど普通に噛める程度に焼きあがってしまう。
それでもおいしいと言われれば嬉しいので、一度焼いて、ママ友Nさんにお裾分けをした。
すると彼女の口利きで、日系のお惣菜屋さんで販売したらどうかという話が持ち上がった。
お惣菜屋さんは、別のママ友Mさん1人で切り盛りしていたお店である。
お食事や単品の他に、デザートも置いていた。
しかし、1人でできる作業量は限られている。
ビスコッティは管理が簡単で長持ちするし、ちょっとしたプラスアルファになるということで置いてもらえることになった。
私は別に仕事があって、お菓子作りをビジネスにする予定ではなかったので、材料費と光熱費の分をいただいて、時々お菓子を卸した。
作る機会が増えると、作業の手順も安定していった。
ママ友Mさんから、フィードバックがもらえたりして勉強にもなった。
また、本場イタリア人のお客様から「ビスコッティではない、別のお菓子にこのようなものがある」というコメントがあった、とも教えてもらった。
どのお菓子のことだったのかは気になるけれど、どちらにせよ、イタリアのお菓子に変わりはないようで安心した。

3. マーケット
ところで、地元にはいくつかのマーケットがある。
我が家に程近いビーチで、毎月一回日曜日に行われるマーケットは、参加費が安いうえ素人にも敷居が低く、日本で言うフリーマーケット的な出店が可能だ。
ビジネスで出店しているところもあるし、非営利団体の活動資金稼ぎや、趣味のクラフトグッズを販売しているブースもあり、賑やかで楽しい。
週末はマーケットを覗いて、屋台の食べ物を食べたりのんびり過ごす、というのもオーストラリア人の一般的なスタイルだと思う。
都会で行われる大規模なものから、田舎の小さなものまで様々で、観光用のパンフレットにもマーケット情報がまず載っている。
ある時また別の友人から、着なくなった服を売りたいが、一緒に私の手作り菓子も売らないかと声をかけられた。
もともとワイナリーで働いていた頃は、出張試飲の許可がおりる野外イベントを手伝っていたし、マーケットで自分が売る側に回るのは楽しそうだな、と思って参加した。
マーケットでは、使って良いスペースを与えられるので、自分たちでテントとテーブルを用意して、売りたいものを並べる。
友人は、商品に値段のタグをつけ、テントの骨組も利用してディスプレイしていたし、私はケーキ用のスタンドに、見本品を並べて準備した。
あまり目立った感じに飾り付けできなかったので、ほとんどは知り合いの方が購入してくださったが、時々それ以外の方にも購入していただけたのも、また、嬉しかった。他のストールの方とも交流できたりして、それもよかった。

4. 日豪イベント
現在、お惣菜屋さんは閉店しているし、マーケットでの販売も2回で終了した。
私は相変わらず、趣味でお菓子を作っては自分で消費している。
ごくたまに、依頼されて作ることがある程度。
そんな折、再びママ友Nさんからお誘いがきた。
今度はこどもの日の木曜日の夜、日豪イベントとして「Taste of Japan」と題した居酒屋スタイルの企画に、一緒に参加しようというのである。
当日は、本職の日系ビジネスの方々が、日豪のお酒を販売したり、おつまみになる食べ物を色々と用意する。
そんな場所の端っこの方にスペースをいただき、友人のクラフトやイタリアンなおつまみ、そして私のビスコッティを置かせていただく予定になった。
素人の私にとっては場違いな気がしないでもないが、そんなことを言っていては何事も始まらないので、ありがたく挑戦させていただこうと思っている。
これまで作ってきたフレーバーは、バニラ、コーヒー、抹茶、ココア、クランベリー味。
日本っぽい味が少ないので、今、きなこや黒糖なども試し焼きをしている。
オーストラリアで、日本人がイタリアのお菓子を焼いているというのは不思議な感じがするが、ケアンズではおかしくないのかもしれないと思っている。
なんといっても、家庭で話されている英語以外の言語は、ケアンズにおいてはイタリア語と日本語がほぼ同率首位である、という国勢調査の結果を読んだことがあるからだ。
友人が私のビスコッティを褒めてくれてからというもの、私の活動範囲は確実に広まった。
ケアンズに越してきて12年になるが、いまだに自分の立ち位置が掴めない。
それでも、このように様々な体験ができていることに感謝したい。
友人が贈ってくれたレシピ本から始まり、自分の焼いたビスコッティを通じて、多くの方と繋がれるご縁を感じているところだ。

4.5.2022
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
オーストラリアの助産師主導型出産

1. オーストラリアで子どもを産む
子どもは2人いる。
現在、それぞれ12歳と15歳。
オーストラリアの同じ公立病院で出産した。
共に同じ病院を利用させてもらったけれども、その体験は大きく異なる。
第一子は、いわゆる通常のステップを踏んだ出産。
最初にGPと呼ばれる一般開業医の妊娠検査を受けて、病院へのレターをもらい、専門医にかかる。
初産のため、来院から出産まで9時間かかった、というのはよくある話だろう。
第二子の時は、来院から出産までは1時間半だった。
2人目以降は予想外のスピードで出産が進んだという話もよく聞くため、こちらもまあ、特別な話ではない。
大きく違ったのは、第二子の時は「ミッドワイフリー・グループ・プラクティス(MGP)」と呼ばれる、新しいプログラムを利用したことだ。
私たちの住む地域では、利用できるようになってからまだ一年も経っていない、新しい取り組みだった。
日本では助産院で産むという選択肢も一般的だが、こちらでは聞いたことがなかったので、「参加を希望しますか?」と医師から尋ねられた時、私は諸手を挙げて同意した。
妊娠13週の頃、正式にMGPが利用できるという手紙を受け取り、利用メンバーになることができた。

2. 助産師さん主導型の出産
「ミッドワイフリー・グループ・プラクティス(MGP)」は、助産師さんが主導となって妊婦の面倒を見るというプログラムだ。
通常は、定期的に医師と面会して体調を管理するところ、MGPでは、担当の助産師が産後までサポートしてくれる。
いつも決まった助産師さんに体調を診てもらうため、医師と面会するのは最低限で済む。
利用できる妊婦にも条件があって、
健康で出産に特別な問題がない。
自然分娩で産む予定である。
無痛分娩など特殊な方法を利用予定ではない。
という希望が一致しないといけない。
第一子の時は、出産時に笑気ガスを吸わせてもらったけれど、MGPではまず、医療介入を減らすための努力を妊婦側に求められる。
まあ努力と言っても、マタニティヨガをしてみる、出産時はバランスボールを使ったり、重力を利用した赤ちゃんが出てきやすい体勢をとってみるというような話で、特別大変なことではない。
私たちの担当助産師は、第一子の時に参加した「両親学級」の講師をしてくれた男性だった。
ご夫婦共に、助産師の仕事をしているそうだ。
このプログラムを率先して進めている人物のようで、医療介入の少ない出産、母乳育児推奨などの情報を共有してくれた。
確かに、「彼の両親学級」ではそのような話を聞いていたのだが、第一子の時は、ずっと分娩台の上で寝ていたし、母乳の与え方を病院で習うこともなかった。
母乳クリニックというところは、ヘルスプラザに存在したが、実際に参加できたのは産後2週目に入っていた。
今回は私がイメージしていた出産に近づくのか、と楽しみな気持ちになった。
通常4週間に一度の健診は8週間に一度、妊娠後期になると2週間に一度の健診でよい。
その代わりに困ったことがあったら、夜中でも担当の助産師さんに繋いでもらえる。
それも心強いことだと思った。

3. 第二子の出産
頼れる人がいる、という安心感からだろうか。
妊娠中の私の体調は比較的安定しており、出産時も、病院に着いてからわずか7、8回の息みを経て第二子は生まれた。
水中出産だった。
娘は、途中まで羊膜に包まれたままだったという。
生まれてきた娘は、夫がへその緒を切り、すぐに私の胸で2時間ほどカンガルーケアで過ごす。
さまざまな医療介入は、その後に行われたと記憶している。
これらのことは、第一子では果たせなかった「夢」となっていたので、それが現実になったことで「尊重されている」と感じた。
3歳半の息子も、一緒にそばにいた。
出産から4時間半後、帰宅許可が出て、4人になった私たちは家に帰った。
そういえば1人目を産んだ時、同室になった女性が立て続けに2人、当日退院を希望して帰っていった。
オーストラリアではよくあることなのだろう。
しかし、日本では1週間程度入院するというではないか。
私も1人目の時は、4泊ほどさせてもらっている。
それが今回は、病室にすら足を踏み入れることがなかった。
2回目の出産後は、お産が軽かった分、体力が余っていた。
出産に付き合ってくれた息子に、その場で絵本の読み聞かせをしてあげられたくらいだし、自分で歩いて車に乗ることもできた。
第一子の時は、車椅子を使って病室まで運んでもらったので、これは大きな違いだった。
家に帰れば、助産師さんが自宅訪問で我々の様子を確認してくれるのも安心だ。
しかしその2日後、私と娘は病院へ舞い戻ることになる。
授乳のため、長時間抱きすぎたせいで、娘の体温が39.3℃まで上昇してしまったのだ。
暑い日に、エアコンを使っていなかったのが災いしたらしい。
体温自体は自宅で用意したぬるま湯のお風呂で落ち着いたのだが、念のため病院へむかうことに。
すると娘は、黄疸治療、低体温、再び黄疸治療という理由で、病院に7泊の足止めを食らってしまった。
授乳をしなければいけないので、私も娘と離れた病室で入院をした。

4. 担当助産師さんの活躍
入院8日目、帰れそうなのに許可が出なくてしびれを切らした私は
「まだ退院できないのか?」
と医師に尋ねていた。
すると朝イチで採血したばかりなのに、「採血をしなければ」と言って、医師は娘を連れて行ってしまう。
『何度採血をするのだろう』と不安になっていた時に、かの担当助産師さんが様子を見にきてくれた。
4日間の休暇を終えても、まだ私たちが入院していることに驚いた彼は、現状を聞きに医師の元へ行ってくれた。
そして、娘を取り返してくれたのだった。
「もう退院できますよ」とも言ってくれた。
この時は、彼から後光が見えた気がした。
そして、特定の人が面倒を見てくれると、このようなサポートもあるのかと感謝した。
未熟児だらけの特別看護ルームの中、娘は3kgと大きく、黄疸の数値以外は問題のない子だった。
言葉は悪いが、後回しにされている感があった。
娘のかかとの採血の傷跡を見ては、不憫に思っていた私は、家に帰れると聞いて本当に安堵した。
お産が軽かったとはいえ、産後の体調が万全とは言い難い状況で、自分の味方と思える人がいるのは心強いと実感した。
次回妊娠をしたら、「まず自分の携帯に連絡をしてほしい」という申し出までいただいており、将来にまで気持ちのゆとりを提供してもらえた。
ただ残念なことに、その半年後には飛行機で2時間半も離れたケアンズへ引っ越すことを決めてしまったので、次回はこなかった。
当時、MGPサービスがまだ始まっていなかったケアンズでは、もう出産は無理だと思ってしまったので、子どもは2人のままである。
贅沢を覚えてしまったのかもしれない。

3.6.2022
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
永住権前後
.jpg)
1. 永住権取得の先にあったもの
私たち夫婦は、当時日本で貯めたお金の全てを使ってオーストラリアへやってきた。
ワーキングホリデービザなのだから、働けば何とかなるだろうという発想だった。
かつて夫が、カナダのバンクーバーで3ヶ月間の語学留学をしていて、日本人の友人たちがアルバイトをしているのを間近で見ていたため、海外で働くイメージが想像できていたのだと思う。
ワイナリーと民泊(Bed & Breakfast)と別々に分かれて、6ヶ月間の文化交流体験をこなしたあと、夫の研修先が、そのままビジネスビザまで請け負ってくれる就職先となった。
ワイン醸造は高給取りの職業だという噂は、単なる噂だった。
大手にでも勤めていれば話は違ったのかもしれないが、金銭面においては、長らく自転車操業のような生活をしていた。
しかし若かったこともあり、お金を得る以上の経験をしているのだという意識を持っていて、生活できているから大丈夫という安易な気持ちで生きていた。
また「お給料には反映できないが、色々とサポートはしてあげよう」というオーナーの気持ちを感じていたので、住んでいる家から放り出されるような不安も少なかった。
実際、途中からオーナーが購入した住居に移り住み、家賃も我々が払えるくらいの金額で固定してくれた。
この時期、周りの家賃相場はどんどん上昇していたので、これはありがたかった。
四年間のビジネスビザの終わりが見えかけてきた頃、オーナーから永住権の話が出た。
この時期、オーストラリアはまとまった人数の移民受け入れを発表しており、我々ももれなく申請したのは言うまでもない。
地方在住の雇用主指名ビザだったが、ワイナリーの建つ場所が地方と地方でないギリギリの場所に存在しており、普段使用している郵便番号が地方であるからとの判断で受け入れられたのはいい思い出だ。
結果、2006年の半ば、私たちは永住権を取得した。
そしてその2週間後に、私は1人目の子どもを出産している。
ビザ申請に詳しい方なら「あれ?」と思うかもしれない。
健康診断のX線検査は、妊娠中であれば受けられないのではないか?
しかし今回は「出産後に受ける」という約束のもと下りたビザだった。
私たちを担当した移民局の方が融通を利かせてくれたようだが、そのおかげで生まれてきた息子は、自動的にオーストラリア国籍を取得することができた。
永住権を持って出産で病院に滞在したのは、3泊ほどだったか。
その間に「医師からの出産証明書をもって、センターリンクへ行くように」と促された。
促してくれたのは、ナースだったのか、それとも事務の人だったのだろうか。
いつまで経ってもわからないことだらけの中で、言われた通りに足を運んだ。

2. センターリンクという所
それまで、「自宅」「職場」「スーパーマーケット」のほかに、出産のための「病院」が増えただけの地味な生活をしていた我々だ。
センターリンクが何をするところなのか、よくわかっていなかった。
身近な職場のオーナーは子どものいない共稼ぎで、縁がないようだった。
センターリンクは政府の機関だ。
さまざまな状況の人へ、金銭的なサポートを行う。
「失業手当」「ひとり親家庭へのサポート」「子育て世帯へのサポート」「老齢年金」「若者へのサポート」「大人になって学生に戻った人へのサポート」など、書き出すとキリがないくらい種類がある。
そのせいか様々な人が利用しており、自分の順番が来るまで、それなりに待たされた。
生まれたばかりの乳児をあやしながら、正直、少しストレスを感じていたのだが、我々の順番が来て話を聞くと、どうやら手続きをすることで定期的にお金が振り込まれる、ということがわかった。
そして我々は「低所得者むけの子育て世帯への追加補助」を受け取る資格のある年収かもしれないと言われたが、永住権取得から2年以上経過している必要があり、こちらの申請は叶わなかった。
渡したばかりの出産証明書を秒で無くすという、不可解なミスをしたセンターリンクの職員だったが、それでもさまざまな情報と金銭的なサポートをくれた。
しかも出生率の増加に力を入れている時期だったようで、出産一時金として3000豪ドルほどの金額をもらえるという。
数年前なら桁が一つ少なかったと聞いたので、偶然だが、タイミングも良かった。
少し前、永住権の申請費用を払ったその瞬間から、この国の健康保険が使えることになっていた。
それまで実費だった出産前検診が無料に、そして出産入院費用までもが全額カバーされている。
それに加えて、子どもがいるだけで、国がもっと金銭的サポートをしようというのだ。
オーストラリアで子どもを持つということは、金の卵を産む鶏を持つことなのか?
一瞬頭がクラクラしたが、素直にサポートを受け取ることにした(受け取らない理由を知りたい)。
残念ながら、上記の通り我が家は裕福ではない。
国からのサポートのおかげで、日本の家族へ孫の顔を見せに帰ることが、より早く実現した。息子が5ヶ月の頃だった。

3. 恩返し
政府からのこのようなサポートに対して、お金が出るから子どもを産むというカップルも一定数いたようだ。
しかも、乳児にかかりっきりの母親を出し抜いて、一括で支払われた出産一時金を持ち逃げした父親がいるらしいという噂も出ていた。
2009年に娘を出産した際は、一時金の支払いが分割に変更されたいたので、あながち嘘でもないのだろう。
現在は制度も変わり、金額も一桁少ない額に戻っている。
あの頃、移民を受け入れたり、出産を奨励したりと、国は人口を増やしたかったのだろうと思われる。
さて、これまで我が家がセンターリンクからサポートを受けたものは以下の通り。
「出産一時金」
「子育て世帯補助金」
「賃貸家賃補助」
「低所得者証明カード(ほとんど利用した記憶はない)」
「保育園の費用補助」
「学資補助(一時金)」
これ以外に災害時の一時金など、子どもがいなくてももらえるものもあった。
初めに案内された「低所得者むけの子育て世帯への追加補助」は利用していない。
一時期、私が週5でホテル勤務をしていた頃、夫とのダブルインカムでさすがに補助の対象外になった。
サポートには世帯収入に上限があるのだ。
夫と2人で「ようやく独立した感じだ」と言い合っていたのだが、私のわがままで、また収入が減ってしまった。
子どもたちが中高生になった今、残念ながら再びセンターリンクのお世話になっている。
子どもが中高生の方が、補助額がより高いというのはオーストラリアの特徴なのではないかと思う。
ハイスクールでは、個人のコンピュータやデバイスが勉強に必須となっているので、支出がどうしても大きくなるのを見越してのことだろう。
それでも、お世話にならずに済むのが本当は良いのだが…
オーストラリアの財政が厳しくなって、市民権保持者ではない永住者に、同じだけのサポートを与えるのはいかがなものかという意見があるのだという。
日本人は重国籍が認められていないので、どうしても永住者にとどまる人がほとんどだ。
出生地によって国籍を得た子どもたちと違い、我々夫婦も永住者止まり。
こちらでの選挙権もなく、よって自分の意見を投票することもできない。
しかしまあ、今までこの国にお世話になってきた分くらいは、質の高い労働力と納税と子育てでお返しができるといいなと思っている。

2.5.2022
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
State-of-the-art とは

悩む
State-of-the-art
この言葉を初めて知ったのは、ワーキングホリデーで滞在していたオーストラリアに残る、そのきっかけとなったワイナリーでのことだ。
私たち夫婦が勤務していたワイナリーの宣伝用パンフレットに 、State-of-the-art winery と書いてあった。
勢いで海外に出てみたものの、英語に興味が薄く触れる経験の少なかった私にとっては、初めて聞く言葉。
はてさて、どういう意味だろう?
artとつくからには、きっとなにか優美でエレガントな意味があるに違いない。
stateは、州という意味しか思い浮かばない。
この二つの単語を合わせているのだから、そうだな『芸術的に素晴らしい代表的な場所』みたいな感じで使われているのだろうか。
ちょっとお上品でお洒落な場所であることを、印象付けたい時の言葉なのかもしれない。
もしくは熟練したものの持つ素晴らしさが、芸術的ということかもしれない。
ワインは、味わいを例える時に様々な表現をするし、それ自体が作品として扱われることもある。
だからアートなのか。
私は勝手に、そのような解釈で自己解決していた。
パンフレットにこの言葉を使ったワイナリーのオーナーに、言葉の意味を尋ねれば手っ取り早く理解できたのだろうが、なぜだろうか、聞くような事ではないと感じ、調べようとも思わなかった。
なんとなく、心で理解しなければいけない言葉なのだという気がして、自分の中に仕舞っておいた。
ただ時々思い出しては、
この事象は、State-of-the-artという表現がふさわしいだろうか?
という検証は時々していた。
あまりしっくりくるものはなかった。


閃く
話は、その後私がケアンズに引っ越し、ホテルのベッドメイキングをしていた頃に飛ぶ。
私が働いていたホテルの部屋の造りは、スイートルームを除けばほとんど同じで、掃除をする手順は、どの部屋でも違いは少なかった。
ホテルという性質上、お客様視点から、見るからに美しく部屋を仕上げることを要求されるが、それと同時に、事業者視点からは、決められた時間内で仕上げるようプレッシャーも与えられている。
ちなみに、12部屋で5時間というのが業界の基準だと言われていた。
これはペアではなく1人で掃除を行う時の基準で、綺麗にするのに時間のかかるチェックアウトの部屋も、お客様から「今日は掃除は要らない」と言われるかもしれない使用中の部屋も含めた混合の数である。
短時間で、美しく、そして抜かりなく。
これらの相反する要求に応えるためには、自分の体の動きを『半自動化』するしかない。
どのような順番でどのような動作をすれば、見逃しを防ぎ、効率的に掃除ができるのか、ということをいつも考えていた。試行錯誤を繰り返し、考える前に体が勝手に動くように努力した。
そのうち私が担当するフロアーが出来、毎日だいたい同じ部屋を掃除するという条件が整った時、私は客室のドアを開けた後、踊るような感覚でいつも同じように体を動かしていることに気がついた。
自分の体の動きだけではない。
部屋をセットアップするのに必要な、アメニティやシーツ、タオルなどを運ぶワゴンも、自分好みに整理整頓していて、コントロールできていると思った。
その時、私はいまState-of-the-artの状態なのではないか、と感じた。
State-of-the-art housekeepingとでも言おうか。
さて、自分に都合の良いことばかりを書いてしまったので、時間に関しては、綺麗さに重きを置くあまり、どうしても遅れがちであったことは告白しておきたい。
しかしそれを差し引いても、掃除をする私の動作は、自分史上、かなり理想的に感じられた。
私の中で、State-of-the-artというのは『理想的』という日本語に変換されていた。

真実
さて、それではState-of-the-artの本来の意味は何だろうか。
実は先ほど、初めて調べた。
State-of-the-art = 最先端、最新の(技術、設備など)
artは芸術ではなく技術という意味で、stateは状態を表すそう。
theはひとつしかない物の前につける冠詞なので、この使い方では唯一無二という意味合いを持つらしい。
「最先端」が「理想的」なら、私の解釈もあながち間違いではないが、思ったよりもエレガントではなかった。
どちらかというと、シャープで尖った感じがする。
言葉だけを見て、勝手にロココ朝の雰囲気を感じ取っていたが、テクノロジーが似合うような意味合いであった。
英語脳になれない自分を披露しているようで、なんだか少し恥ずかしい。
さて、今回の答え合わせをするのに、20年近くの時を経ている。
私たちがオーストラリアに足を踏み入れたのは、2002年2月。
私がワイナリーで冒頭の言葉にはじめて触れたのは、その1ヶ月後のことだ。
あまり目にする機会が少ない言葉とはいえ、調べることなく、よくここまで想像だけでやり過ごしてきたなと思う。他にも、調べてみると想像とは全く異なる意味だった単語は少なくない。
高校生の頃から、英単語の暗記を脳が拒否してきた代償だろう。
20年というオーストラリア滞在年数に対して、それに見合う英語力が全くついていないため、申し訳ないような気持ちをいつも感じる。
普段、私のよくわからない英語に付き合ってくださる皆さんには、本当に感謝しかない。
20年といえば、人ひとりが成人になるとされる年数だが(今年から18歳が成人に変わるけれども)、私の英語に関してはいつまで経っても成人になる気配はない。
しかしそれでも、State-of-the-artという単語を付けられるような、最新の何かに触れることができたら、人生は楽しいだろうと思う。

12.5.2021
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
街のベーカリー

2010年、ケアンズに引っ越してきて嬉しい誤算だったのは、おいしいケーキやスイーツがいろんなお店で簡単に手に入ることでした。
観光地なので、おしゃれなカフェもたくさんあるし、いろんな国出身の人が各自ルーツの甘いものを提供してくれます。
ですから「自分で作らなければ…」と思わなくても、そういったお店に出向くことで満足できてしまいます。
私の場合は、ケアンズ以前で過ごした日々の積み重ねもあるので、買うだけでなく自分で作る楽しみもやめられませんでしたが、そのための「勉強」という名目で、ケーキ屋さんに出向くこともやめられません。
ただこれは観光地ケアンズだからであって、そうではない地域の人は、みんな自分で作って、甘いものへの欲求を満足させているのかといえばそういうわけでもなく、甘いものが欲しくなったら立ち寄るお店があります。
それは、ベーカリー(パン屋さん)。
2002年に半年間ホームステイしていた場所は、ニューキャッスルから車で30分、シドニーからだと一時間半のドライブを経て到着する、湖と山に囲まれた田舎にありました。
そしてそこに住むホストファミリーはほとんど外食をせず、毎晩できたてのおいしい夕食を食べていました。
デザートも、結構な頻度で一緒に作りました。
それでも一度、お友達の家に持参するために、地元のベーカリーで甘いお菓子を見繕ったことがありました。
こういう場所で甘いものを買うのかということと、そのスイーツがとても甘かった記憶が残っています。
アップル・ターン・オーバー
ホームステイが終わった後に引っ越したイプスウィッチは、州都ブリスベンの西隣に位置していました。
しかし、都会のそばにあるエリアの割に、スイーツが並ぶおしゃれなお店は見あたらず、砂糖の塊のようなチーズケーキを出すカフェが、繁華街にようやくあるような感じでした。
ブリスベンに気軽に行ける距離のため、逆に発展を逃していたのかもしれません(今は人口も随分と増え、様変わりをしているはずですが)。
そんな地域でも、いわゆる「近所のベーカリー」にはスイーツが置いてありました。
駅前にあったお店で、見た目で選んで買ってみたのは「アップル・ターン・オーバー」というお菓子。
丸い形のパイ生地を半分に折って、中に煮りんごを挟んだものです。
アップルパイのように、縁をぎゅっと閉じることはせずに焼いてありました。
そのままの状態のものと、生クリームを間に絞ったものとが選べます。
甘いもの好きのオーストラリア人ですが、驚いたことにここに絞られていた生クリームは無糖でした。
甘くないと逆に塩味を感じてしまい、とても不思議な気持ちになります。
さくさくパイ生地と、甘酸っぱい煮りんご、そして生クリームの濃厚さがクセになる一品でした。

ラミントン
また、イプスウィッチ在住時は知り合いが家族でベーカリーを経営していて、新店ができたと聞いて寄らせていただいたことがあります。
その時に買ったのは、ラミントンでした。
ラミントンは四角いスポンジケーキを、チョコレートやココアアイシングでコーティングして、ココナッツをまぶしたお菓子で、オーストラリアのスイーツとして有名。
ベーカリーで買うラミントンはいつもふわふわの口当たりで、どうやったらあんなに軽くてきめの細かいスポンジを焼けるのだろう、と羨ましく思いながら食べる一品です。
ケアンズに来てからお友達と一緒に作ったことがありますが、あのふわふわ感は出せませんでした。
残念。
いつか、もう一度挑戦したいと思っています。
このラミントン、実は発祥が我がクイーンズランド州で、一説によると「ブリスベンでできた」「いやいやトゥーウーンバだ」などと言われているそうです。
それを知った時、私は中間地点にあるイプスウィッチで初めて食べたのかと、しみじみしてしまいました。

ベーカリーのスイーツ探訪
ケアンズに来てからは、目を引くケーキ屋さんやカフェに心を奪われ、街のベーカリーでスイーツを買う機会はほとんどありませんでした。
ある時、時間調整のために立ち寄ったショッピングセンターにチェーン店ではないベーカリーがあり、友人宅へのお持たせをそこで買ってみようと思いました。
ショーケースにはカップケーキや、コッペパンの上にアイシングがたっぷり乗った甘いパンなど、お決まりの品が並びます。その時は、お持たせの条件に合う手軽で手頃なミニタルトを選びました。
そうだった、そうだった、
ベーカリーのスイーツも忘れちゃあいけませんでした。
派手さはあまりないけれど、確実に国民のお腹を満たしてきた甘いものがそこにはあります。
せっかくなので、今まで行ったことのないケアンズの街のベーカリーで甘いものを探そう! と思い立ちました。
職場のスタッフがよく行くというお店を訪れてみると、なんだか懐かしい雰囲気の店内。
奥の棚には食パンやディナーロールなど、日常的に食べられるパンが並び、手前のショーケースには、サンドイッチや惣菜パン、スイーツなどが並んでいます。
想像以上に、いろんな種類の甘いものが置いてありました。
ラミントン、アップルターンオーバー、バニラスライス、ドーナッツ、ヘッジホグスライス、ロッキーロードスライス、キャラメルタルト、ミンスパイ、マッドケーキスライス、エクレア、カップケーキ、フィンガーバン(アイシングを載せたコッペパン)、クリームバン(生クリームを挟んだコッペパン)などなど……
ワクワクしていたので、値段を見ずに4つほど甘いものを選んだところ、合計がなんと10ドルを切っていました。カフェでケーキを頼もうものなら、一つ8ドルは平気でとられるこのご時世に、です。
その後、欲が出た私は、別の場所にあるチェーン店のベーカリーにも突撃し、新たに3つ、手に入れる有様。甘いものには目がありません。
これからのクリスマスシーズン、オーストラリアでは定番のフルーツケーキやジンジャーブレッド以外に、普段は手に取らないスイーツを食べてみるのも悪くないなあと思う今日この頃です。

11.5.2021
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
小学校で最後のお祭り

1.ロックダウン
8月のお盆の時期、娘の通う小学校ではフェイトと呼ばれるお祭りが行われるはずだった。
これまで私がどのようにフェイトに関わってきたのか、今年はいつ行われるのか、ということは8月号に書いている。しかしその記事を寄稿した後、開催予定日のちょうど1週間前に、ケアンズはロックダウンになった。
3日間のロックダウンが明けて小学校は再開されたが、送り迎えの保護者が2週間は学校施設内に立ち入れない制限がかけられたこともあり、その状況下でのフェイト開催は難しいとの判断がなされた。
1週間前であったから、当然さまざまな準備は進んでおり、企業・団体からの寄付やラッフルチケットの販売、当日やってくる移動遊園地のフリーパス券販売などもすでに行われていた。
よって、中止ではなく延期。
ただでさえ忙しい最終学期である4学期、10月後半の土曜日、午後3時から8時までが新しいフェイトの日付となった。
2.仕切り直し
フェイトの数ある出し物の中で、私は「巻きズシ」ストールの共同責任者を担当している。
8月のフェイト延期が決まった頃、スシストールは一体どのような状況だったのか?
各家庭からの炊飯器、前日の仕込み・当日朝のスシ巻き・当日午後の販売スタッフを募り、人数調整や追加募集を行っているところだった。
食材に関しては、長期保存の効くものは既に入手済みで、そろそろ野菜を購入しようかというタイミング。おかげさまで、10月に延期されても食品に関してのロスは出なかったが、日をあらためたことによる新たな問題が発生した。
現在、世界的なムーブメントになっている「脱プラスティック」。
我々の住む地域では、9月1日から食品を販売する際の使い捨てプラ容器が原則禁止となったのだ。
元々の開催日時であれば、確保済みのプラスティック容器を使用できたのだが、日を改めたことで新しく紙の容器を購入するはめになったのである。
現在手元にある容器は使用できず、新たな製品を購入するという、エコとは言い難い状況になったのは皮肉なことだ。

3.参加者を集める
新しい日付のフェイト1週間前。
今回はロックダウンなどもなく、無事に準備を継続することができた。
昨年からのパンデミックが引き続き世界を賑わしているせいか、フェイトのボランティアは例年になく集まりが悪いようだった。
感染者が1人出ただけでロックダウンになったケアンズでも、人数が集まるイベントには参加を躊躇する人が多いのかもしれない。
娘のクラスの担当ストールは古本販売だったが、責任者と話をすると人手がまだまだ足りていなかった。
私はスシの責任者だが、販売の時間帯はほとんど体が空いているため、2時間参加することにした。娘は最上級生で、お祭りの間の付き添いが必要な年齢ではない。
そして私は、ケーキストールに寄せられた各家庭からのケーキを見ることができさえすれば、あとはボランティア仕事であっても構わない。
午前中にスシ巻きをしてくれた人で、自分の子どものクラスが担当しているストールにも参加している保護者は多い。それを見ていると、特定の人々の善意で成り立っている、とつい言いたくなってしまう。(やる気はあっても、家庭や仕事の都合で参加できない方も当然いるのだが)
今まで参加したことのない人も、時々しか参加しない人も巻き込んで作り上げるのが理想だろうが、我々だって一介の保護者であって、イベント開催の特別なスキルを持ったスペシャリストではない。普通に告知をして、参加を募ることしかできない。
スシストールでも、スシ巻き・販売・炊飯器は改めて募集しなおしたが、希望する数になるまでに時間がかかった。フェイトの主催者にも手伝ってもらい、Facebookやニュースレターで募集をかけてもらったところ、今年は例年になく日系以外のボランティアの方からメッセージをいただくことができた。
そのため今年は、当日の作業内容の手引書を、日本語だけでなく英語でも書き足すことにした。
4.フェイト当日
当日がやってきた。
前日から仕込みは始まっており、照り焼きチキン調理や荷物をスシ巻き会場に移動する作業を終えていた。
朝8時、もう1人の責任者と私で、スシ巻き会場である学童の施設のセッティングから開始。
テーブルを移動し、各電源に2台ずつ計12台の炊飯器を設置。
それから8時半には最初の参加者のかたがやってくるので、それに間に合うように、サインしてもらうタイムシートや手引書、衛生管理に関するパンフレットをわかりやすく並べる。
最初にお願いするのは、スシに巻く具材の準備。
ツナマヨを作り、野菜(きゅうり、にんじん、アボカド)を切る作業だ。
この野菜、実は購入後に我が家で管理していたため、嫁に出すような気持ちで今回持参した。
きゅうりは、購入後すぐ冷蔵庫に入れておいたら、危うく凍りかけていたのを発見。
すぐに取り出して、表面に結露する水分をとりつつ室温に戻し、クーラーボックスに入れたり冷蔵庫に戻したりを繰り返し、様子を見ていた。
購入時の見た目が良かったアボカドは、袋から出してみると、まだ硬いものが多かった。
バナナを入れると追熟が促されると聞いたので、家にあった熟れすぎているバナナを、とりあえずアボカドの間に差し込んでみた。
毎日硬さをチェックしていたが、土曜日になっても、まだベストな状態とは言い難いものが半分近く。
切ったら良い感じでありますように!
野菜のその後は、参加者のかたにお任せすることにして、私は、全体の進行が滞りなく進むことに意識を向ける。
お米は無事に炊けているか?
次々とやってくる方に、わかりやすいようなテーブルセッティングか?
朝から一緒に連れてきた子ども達(15歳と11歳)にも仕事はあるか?
スシ売り場に保管用の冷蔵庫は届いているか? 冷えているか?
今、どのくらいスシができている?
「あ、今仕事がないんです。何をしてもらいましょうか…」
「では、そろそろ売り場に運びますか」
このような感じであたふたしていたら、あっという間に予定数の寿司が出来上がっていた。
私が実際に巻いた寿司は、5本くらいだっただろうか。
材料が余っていたので、まだ数が足りていないと勘違いした私は、
お米が足りない!
と騒いでしまったが、すでに十分足りていた。事前に1合2本で計算・準備していた、米の量を信用して良かったのだと思った。
過去のスシ巻きでは、何かしらのトラブルがいつも起こっていたので、スムーズな進行に慣れていなかったように思う。
余った食材で、みんなのランチを作った。

5.スシ完売!
スシは完成してしまえば、後はこっちのものだ。
販売は、お金がわりのスティックとスシを交換すれば良いだけ。
「ツナマヨ&きゅうり」「照り焼きチキン&アボカド」「きゅうり、アボカド&にんじんのベジタリアン」から選んでもらえる。
私は子どものクラスのお手伝いに抜けてしまったが、もう1人の責任者のかたが何かと気をかけてくださり、つつがなく売れていた。
300本以上作った年は、最後の1時間を売り子が練り歩いたこともあるが、今年は200本と数を控えめにしている。
そのおかげで、売り切った後に片付け・解散となっても、まだ祭りは終わっていなかった。
今年は私にとって11年目のフェイトで、そして小学校の保護者として関わる最後のフェイト。
日系の保護者、スシストール担当クラスの保護者、担当クラスの先生(偶然にも日系のかた)、学校の日本語の先生、そして、学校からの参加者募集の呼びかけを見て参加してくれた保護者の方々、おまけにそれぞれの子ども達まで。
人が足りないと騒いでいたが、結果、こんなにたくさんの方々の協力を得て、スシストールは無事に終わった。
余った食材で作ったスシを食べていると、薄く切られたアボカドがまだ少し硬かった。
薄く切って食べやすくしてある工夫に感謝しつつ、どこかちょっと抜けのある、これぞフェイトのスシだなとしみじみ味わった。
10.5.2021
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
ペットを飼うということ

1.ペットが欲しい
「うちにも犬か猫が欲しい」
娘からいつも言われていた言葉だ。
そう言われるたびに、
「猫はお父さんが好きじゃないし、犬はうちのフェンスをしっかりして、日陰になる場所を外に用意してあげないと無理」
と断っていた。
オーストラリアで、ペットを飼っている家は多い。
私が初めてホームステイをした家には猫と馬がいたし、夫のステイ先には犬が2頭いた。
現在住んでいる家の近所を見渡しても、首輪をつけた猫が道路を歩き、散歩をすればフェンス越しに吠えてくる犬、勝手に抜け出して歩き回っている犬もいる。飼い主の車(トラック)の荷台に繋がれて、一緒に出勤する犬も時々見かける。
お友達の家から
「鳥を飼い始めたよ」
「ギニーピッグ(モルモット)を育てているよ」
なんて声もちらほら。
周りにはこんなにたくさんの人がペットと一緒に暮らしているのに、なぜ我が家はダメなのかと不満タラタラの娘だったが、今年のお正月に夫が
「猫なら飼ってもいいかもしれない」
と言い始めたので私はびっくりした。
娘は大喜びだ。
白状すると、私がどこまでの負担に耐えられるのかというのが、ペットを飼う時の1番のポイントだと思っている。
我が家にはすでに金魚がいる(実はもう「ペット」はいた)。
朝晩2回のえさやりと、時々水槽の掃除をすれば良いという、お世話の簡単なペットだ。水質もあまりこだわらなくてよい。
金魚は5年ほど前の息子の誕生日に五匹買ったもので、「これはおれの金魚にしよう」と夫が言っていた黒い出目金一匹だけが、現在も生き延びている。
しかし気がつけば、毎日のお世話をしているのが息子でも夫でもなく、母で妻の私だというのは、まあ、よくある話だろう。
犬にしろ猫にしろ、我が家でなにかを飼うのであれば、最終的には私の責任感が最後の砦となる。
そんなプレッシャーを感じつつ、それでも猫を飼えるとなって嬉しかった。
私は生まれた頃から、家に猫がいた。

2.猫を迎える
我が家からそれほど遠くない場所に、動物の保護施設RSPCAがある。私たちは、将来家族になる猫をそこで探した。
保護施設で希望を伝えると、まず、猫を迎える条件が整っているか、スタッフの人に確認される。
子どもがそれなりの年齢になっていること、ペットの飼育に制限のない持ち家であること、完全室内飼いができることなどの条件を満たし、晴れて我が家にやってきたのは、生後六ヶ月のキジトラの兄弟猫が二匹。
飼うのは元々一匹のつもりだったが、兄弟で一緒にいるところを見てしまうと、そこから一匹だけを選ぶことはできなかった。
私たち人間が家を留守にしている間、生まれた時からの兄弟と一緒なら、お互いに寂しくないかもしれないという算段もあった。
私たち家族は大人二人、子供二人。そこに猫も二匹なら、バランスが取れているではないか!
兄弟たちは実際に、ケンカしたりシンクロしたり運動会を始めたり、人間がいなくても楽しそうにやっている(ように見える)。
生後六ヶ月だと、来た時から体もそれなりに大きく、トイレの場所も勝手に覚えてくれて手がかからなかった。
初めに液体状のおやつを舐めさせてあげたら、どことなく緊張していた二匹もリラックスしたようだった。
私たちが、エサと新鮮な水ときれいなトイレを提供しておけば、あとは好き勝手に過ごしてくれた。
私たち人間は、喜んでたくさんの写真を撮った。
猫を飼うことについて昔と違うと感じたのは、完全室内飼いであるという点だろうか。
気ままに外を歩く近所の猫も少なくないのだが、野生・飼い猫の区別なく、猫はオーストラリア固有の野生生物を殺し過ぎてしまう観点から、完全室内飼いを推奨されている。
確かに、猫たちがやってくるまでは家の中にヤモリがいたが、今や室内には見当たらなくなってしまった。いつものんびりしているように見える猫だが、なかなかのハンターであることは間違いない。
外に出して誰かに捕獲されてしまうのも困るので、小さな家の内側で過ごしてもらっている。

3.ペットの病気
猫を譲渡された時の書類に、誕生日の記載があった。
誕生日がわかっているということは、妊娠中の母猫が保護されていたのかもしれないが、まあそれはともかく、7月の半ば、家族でお祝いをすることにした。
普段はドライフードとウェットフードを半々で与えていたが、その日は値段の高い缶詰を買い、そのうえに液体状のおやつで名前を書いたものが祝いの膳。
私たち人間は猫のアート大会を行い、本人たちは知るよしもないバースデーカードを作って楽しんでいたのだが、片方の猫に異変が。
急にいろんな場所で少しずつおしっこをするようになり、それに血が混じっていたのだ。
楽しい誕生日のはずが、嬉しくない出来事の記念日にもなってしまった。
予防接種でお世話になった動物病院で診てもらうと、排尿がきちんとできていないことを指摘され、緊急入院となってしまう。
尿石が疑われたが、強制的に排出した尿から見つかったのは、バクテリアだった。抗生物質を処方されたあと、経過がよくて一泊で帰ることができた。
しかしその2週間後、また同じ症状が起こり、今度は入院せずに注射を打たれただけで帰った。
それからは少し落ち着いていて、病気のことを忘れかけていた先日、今回は完全に尿が出なくなってしまった。血尿はなかった。
これらはいつも予期できず、突然発生する。
同じ条件で育ち、同じ餌を食べて育った二匹だが、一歳になってからはいつも片方だけが体調を崩す。
今回もかかりつけの動物病院での入院予定だったが、検査結果を診たドクターから、緊急動物病院への移動を促され、そちらで一泊をした。
幸いなことに、今回も尿を強制的に排出したあとは経過が良く、一泊の入院だけで帰宅を許されている。
ただし一泊とはいえ、残された健康な猫も、私たちも心配な夜を過ごした。
初めての入院の際は「一泊が1週間に感じた」と娘は言った。

4.現代の常識
ペットの突然の病気は、年齢に関わらず他人事でないと、今回実感した。
何より、まだ一歳になったばかりでも起こりうるのだ。全くイメージできていなかった。
私のイメージは、30~40年ほど前に実家にいた猫たち。
彼らは外にいることが多く、そのうち帰って来なくなった。交通事故に遭っていたのを大人が隠していただけかもしれないし、本当に雲隠れしたのかもしれない。
猫の寿命はそれなりに長いようだが、彼らは一桁の年齢で消えてしまっていたと思う。
捨て猫や飼い主を探している猫を譲り受け、「餌を世話してあげるから、家のネズミを取ってくれ」という関係性の付き合いだった。餌はもちろん、ご飯に味噌汁をかけたネコまんま。今なら塩分過多で、動物虐待に問われそうな対応が日常。
ペットに対する、時代のアップデートができていなかったことに気づいた。
現代は完全室内飼いが主流となり、そうであれば、目の前から消えるということはまずないし、目的も愛玩動物の要素が強くなる。
そうであれば、人間が完全に責任を持って対応するのは必至だろう。
「猫と一緒に育った」というセンチメンタルを持っていたが、現代においてペットを飼うということは、おそらく国を超えて、私の「知っている」時代より飼い主の責任が増している。
今まで
「ペット保険ってなんだろう? 必要なのか?」
と思っていたが、考えるべき項目だった。
目の前に体調の悪いペットがいたら、放っておくことはできない。
その際、全てが実費になる。
気持ちは人間と同じように家族であっても、国の健康保険などは人間にしか適用されない。マイクロチップを埋め込んで、ペットとして登録済みでも、去勢手術を済ませていても、国からのサポートはない。
ペットである犬や猫の野生化を認めないことや、それ以外の野生生物は絶滅から守られるべき存在であること。
これらは人間が作り出した「考え方」であると言えるが、そういった御託を抜きにしても、目の前の生命が助けを求めていたら、なんとかしたいのは人情ではないか。
とりあえず、家族として迎え入れた猫たちは、私たちと運命共同体だ。
私たちは頑張って働いて、いざという時のために備えたいし、猫たちにはのびのびと暮らして欲しいと思っている。
9.5.2021
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
ケアンズの賃貸空室率

ケアンズのロックダウンと空室率
8月中ば、ケアンズにも二度目のロックダウンがやってきた。
一度目は昨年の前半、はじめに感染が出た時だった。
それ以降、感染ルートがはっきりしたごく僅かな陽性者は時々出たが、これまでロックダウンにはならなかった。
タクシードライバーがひとり、検査で陽性反応が出たための三日間のロックダウンだったが、終わってみると、他からは誰も陽性反応が出なかった。
現在は再び、基本的にマスクなしで許される生活に戻っている。
ケアンズは、オーストラリア国内でマスクが要らない・ロックダウンが少ない拠点都市として人気が出ているらしい。
住宅事情がそれを物語っており、賃貸空室率が1.1%(2021年4月)で、家が見つからないと嘆く家族の記事が新聞に載った。ペットも一緒だった。
当然のように賃料もじわじわと上がっており、気の良いお隣さんが金額の安い田舎へ引っ越してしまった時は、とても悲しい思いをした。
リタイアしたお父さんと娘さんのコンビで、お父さんはいつも共有のドライブウェイに落ちた枯葉を掃除してくれたし、娘さんとは一時期職種が同じだったことから、とても親近感を覚え、お菓子やオリーブをお裾分けしたりした。イースターやクリスマスには、彼女からカードと共に子ども達へチョコレートのプレゼントをもらった。
今、近所の相場を軽く検索してみたが、以前はたくさん出てきたアパートタイプの賃貸物件はなりをひそめ、高額な一軒家が目立つようになっている。
また、売家にしても人気のようだ。
100人を超える人が見学会に訪れた6000万円台の物件があると小耳に挟んだし、日本語の不動産ニュースレター最新号には「ケアンズでは、販売中の物件よりも買主の数が多いという状況が続いており成約価格も上がっています」とあった。
金利が史上最低という要因もあり、市場が活発に動いているようだが、一方でロックダウンが続く地域の裕福な人々が、自由を求めて北に引っ越すというケースも、もう当たり前の光景なのかもしれない。


我が家の引っ越し履歴
住宅価格高騰真っ最中のケアンズで、それでは我が家はどんな状況かというと、ホームローンを返済中の持ち家に住んでいる。
滞在初期のホームステイを除くと、オーストラリアに来てから五軒目の住まいになる。
一件目は、不動産会社を通して契約したイプスウィッチの一軒家。
六ヶ月間バラバラにホームステイ生活を送っていた私が、夫のステイ先へ合流した1週間後に、この家に越した。
床の隙間から地面が見えるような、シンプルな造りの2ベッドルームハウスだった。
仕事にかまけて庭の草を放置していたら、「警告文」が届いたため急いで草刈りをしたことや、隣の家の犬二匹が勝手に上がり込んでいたので追いかけ回した思い出がある。
ワーホリ友達やワイナリーで研修がしたいとやって来た日本人が、セカンドベッドルームに泊まったのはこの家だった。
二軒目は、勤務先であるワイナリーのオーナーが投資用に物件を購入したので、個人的に借りた。
年季の入ったクイーンズランダーと呼ばれる高床式住居で、1000平米の敷地の中に建っていた。
ここでは子どもが二人増え、ご近所さんとも仲良くなれた。
金婚式を迎えたお隣の老夫婦は、いつも二人で広大な庭の手入れをしていたし、反対側のお隣は小学生のお子さんがいるご家庭で、英語の苦手な私たちを歓迎してくれた。
息子は一歳から、家の斜め向かいにある保育園へ通い、裏庭の向こうにはオーナーが住んでいたので、安心して暮らしていた。
三軒目はケアンズに飛ぶ。
イプスウィッチにはアパートらしき建物はほとんどなく一軒家ばかりだったが、ケアンズはレゴブロックエリアと呼ばれるアパートだらけの地域が存在した。
私たちが最初に引っ越したのは、不動産屋さんに勧められた「現在販売中」の賃貸物件。
オーストラリアの集合住宅は、一戸ごとにオーナーが異なり、自分が住むこともあれば賃貸に出すこともある。
3階建てのアパートの2階で、子ども達が通うことになる学校の真横にあった。
当初、海に近い物件を希望していたが叶わず、およそ1700キロ離れた遠距離から住宅を決めなければいけなかったため、言われるがまま「おすすめ物件」にサインした。
しかし怪我の功名というかなんというか、引っ越した地域はいわゆる人気エリアだった。
実はそれまで、ケアンズの治安や人気の場所などについて調べたことはなかった。
二人目を産んだばかりのタイミングで、夫は職探しに忙しく、そんなことを考える余裕がなかったのだ。
そんな私たちだが、図らずもケアンズの人気エリアに住み、子ども達は人気の小学校に通うことになった。
ところでアパートの2階では、地面がない。
入り口に広めのベランダがあるだけで、そこからパン屑のこぼれたテーブルクロスをはたくと、一階の住人のベランダに落ちてしまう。
子どもがいる家庭なので、どうしても地面が欲しくて半年待たずに引っ越した。
四軒目は、やはり小学校のすぐそばにある、ちいさな裏庭がついたメゾネットタイプ(二階建ての集合住宅)。
毎日の散歩の時、ここに住めたらいいなと密かに目星をつけていた物件だった。
先のアパートよりも体感的に室内は狭い物件だったが、全体的にきちんとした作りで、住みやすくて嬉しかった。
二階へ続く階段があったので、子ども達はよく登り降りして遊んだ。
もちろん時々転げ落ちた。
裏庭は雨季に川になるシーズナルクリークに面しており、一度そこからフェンスの隙間を通り抜けてゴアナ(オオトカゲ)が入り込んだ時は、慌ててしまった。
サイズが1メートルほどあるので怖いし、安全な動物なのか確認したくて近所の人を呼び、フェンスの隙間を広げて逃してもらった。
ここでは子どもの友達もでき、お菓子もたくさん作った。「狭いキッチンからおいしい料理」を心の合言葉にしたし、家が狭いので外遊びに出かける基地のような感覚で過ごした。
しかし、
賃料は上がっていく。
人間関係も良好、学校が近くて住みやすいこの住まいは楽しかったが、私が就職したことを機に住まいを購入することを決めた。
それが五軒目、現在の住宅だ。
小学校そばの人気エリアからは少し離れたが、念願だった海の近くに引っ越した。

ジェントリフィケーション
オーストラリアの賃貸では、「借りている」ことを意識させられるイベントがある。
半年ごとに、不動産屋の室内チェックが入るのだ。
こちらには、ひどい住み方をする人がいるらしく、それを防いだり確認するのだろう。
「〇月〇日〇〇時に訪問するので、在宅していてください」
というレターが届くのできれいに掃除して準備するのだが、待てど暮らせどやってこない、なんてことはよくあった。
仕事で留守にした時は、友好的なコメントが残されていたのに、私が在宅で立ち会った時は「窓のサッシが汚い」というお小言を頂戴したので、これからは留守にしようと誓った。
また、次に住みたい賃貸物件の見学を希望した際、指定された日時に、不動産屋がやってこないこともあった。
所詮、借主はそのような扱いなのだと身をもって実感した。
ひるがえって、家を購入しようと見てまわった時は、不動産屋の対応の丁寧さを感じた。
やはり賃貸の借主は立場が弱いのだろうかと、思わずにはいられなかった。
冒頭の賃貸空室率1.1%という数字。
貸主は賃料を上げて、貸し出す人を選びたい放題だろう。
最近、バックパッカー宿の掃除を時々している。
現在は州をまたぐ旅行者はやってくることができないので、住む家を失った人が、次の住まいが見つかるまで、こういった宿やキャンプサイトを利用することもあるだろう。
それでも次の住まいが見つからない人は、今までの仕事や学校や諸々をあきらめて、家賃の安い地域へ行くしかないのだろうか。
これをジェントリフィケーションと呼ぶのだろうか。
8.2.2021
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
小学校で巻き寿司を作る日

スクールフェイト
ケアンズに越してきた翌年、2011年に息子は小学校に入学した。
一年生になる前の、日本で言うなら年長さんにあたる学年で、クイーンズランド州ではプレップと呼ばれている。おもに四歳から五歳の子が通う。
私たち夫婦は日本で生まれ育っているので、オーストラリアの小学校は知らないことばかり。
入学して少し経つと、「スクールフェイト(School FETE)に協力してください」という情報が飛び込んできた。
どうやらフェイトというものは、学校をあげての大きなお祭りのようだということを知る。
子ども達が通う小学校では、毎年8月上旬から中旬の土曜日の午後に行われることが多い。
仕切っているのはP&C(Parents and Citizens’)という日本のPTAのような組織。
ステージ設営と司会進行、食べもの屋台ブース、ケーキ・スイーツ・ジャム・植木・おもちゃ・お楽しみグッズ・セカンドハンド商品などの販売、アヒル(のおもちゃ)すくいやお化け屋敷などのアトラクション、オークション、ラッフルチケット抽選会などのイベントがあり、すべてボランティアの手によって運営される。
そして、移動遊園地の業者もやってくる。
私たちにとってはじめての年、Over 18’s BARというお酒を出すブースの責任者を募集していた。
小学校のイベントだが、なんと、保護者やスタッフ向けにお酒を飲めるスペースを確保しているらしい。
「お酒を提供しても、今まで問題が起きていない」コミュニティであるというのが、実は自慢だったようで、そんな言葉をちらほら聞いた。
「何年か前に、やるか辞めるかの熱い議論が交わされた」という話も聞いた。
お酒の販売には厳しいオーストラリアだからこその、自慢だったと言えると思う。
オーストラリアではお酒を販売するスタッフはRSA(Responsible Service of Alcohol)という免許が必要だが、夫は酒屋という仕事柄、常に保持している。
また、ワイナリーで働いていたときにたびたび出張試飲販売を行っていたため、そういったブースに何が必要かということは、それまでの経験からだいたい想像がつく。
「私たちのテリトリーだな」という匂いがした。
お酒ブースの責任者がなかなか決まらない様子を見て、私たちは手を挙げることにしたのだった。
「ありがとう」という言葉とともに、P&C会長の男性が笑顔で説明をしてくれた。
ここは単に責任者がいなかっただけで、すでに全て手配済みの楽なブースだと教えてもらう。
実際に、当日の販売スタッフを見つけることだけが、私たちの最大の仕事だった。
通常は、各ブースに担当クラスがつき、クラスの保護者を中心にボランティアを募るのが一般的だ。
しかし、お酒ブースはその性質上クラスがついておらず、人を集めるのに難儀した。
なにせ、私たちは引っ越して来て間もないうえに、まだプレップの子供の親なのである。
フェイトの時間中、私たちがずっと販売に張り付いていても構わなかったが、みんなで協力して作り上げるイベントなのだからと気を取りなおし、知り合って間もないお父さんなど、狭い範囲だが声がけをした。
当日は、ベテランの男性もヘルプしてくれ、新人の私たちをかなりサポートしてくれた。
このブースを担当するにあたり、「お酒を売っているなんて」というクレームを受けるかもしれない、と身構える気持ちも準備していた。
だが蓋を開けてみると、スマートに飲む人ばかりで拍子抜けだった。
小さかった子ども達も、頑張って私たちに付き合ってくれた。
それでも「小学校」と「お酒」という組み合わせに難色を示す人がいるためなのか、毎年存在するブースではなかった。
そして私たちがこのブースの責任者をしたのは、結局このとき一回きりであった。
「日本人である」保護者には、もっと別の大きなミッションが待っていたのである。


スシストール
はじめての年、私たち夫婦はお酒ブースを担当したが、日本人だということでスシストールからも声がかかっていた。
スシストールは、そのむかし日本人保護者有志が立ち上げたブースで、こちらで人気の巻きズシを販売する。
ちなみに中身は、照り焼きチキンとアボカド、ツナマヨときゅうり、そしてベジタリアン用となっている。
スシを作るのは基本的に日本人ということなのか、担当クラスがついておらず、ひたすら日系の保護者に声がけをして人手を集めていた。
お気づきかもしれないが、ケアンズは在住日系人が多いため、その子どもである日系生徒の数も多い。
学校によって数にばらつきはあるが、子ども達の小学校では息子の学年は10%が日系の生徒、娘の学年もそれに近い数字だった。(学年によっては数人のみという場合も、もちろんある)
保護者手作りのスシ巻きとその販売は、下準備からそれなりの作業量があり、かつ呼びかけた保護者すべてが参加するわけでもないので、特定の小学校でしか実現しないブースと言える。
また、この小学校で習う外国語が日本語であり、日本語の先生も巻き込むことができるという条件も整っていた。
とにかく「日本人ならフェイトではスシストールに参加!」という流れがあり、土曜日の午前中は息子がプレップの時から、私は毎年スシを巻いている。
そして2017年、息子が6年生の最終学年になったときに、私はこのスシストールの責任者になった。

ケーキ or スシ
それまでの私といえば、毎年スシは巻いてきたが、それ以外のブースで販売するホールケーキやカップケーキを作ることを何よりの楽しみとしていた。
考えてみてほしい。
自分が作りたいと思ったカップケーキを一日中、大手を振って好きなだけ焼いて、デコレーションできるのである。
たくさん並んだケーキを写真に収めて、ニンマリできるのである。
そして、これらをストールに持っていけば喜ばれて、それをお客さんがワイワイ言いながら選ぶのだ。
こんな楽しいことがあるだろうか?
またケーキストールと呼ばれるブースでは、ホールケーキなどを入れるケーキの箱に子ども達がアートを施す。
学年ごとに子ども達のデザインを競うコンテストとなっており、参加するためには中に手作りのケーキが必須。
ある年は、息子と娘用の箱の他に二つ追加して、計四つの箱にケーキを収めた。
普通にホールケーキを入れたこともあるし、和風にカステラとどら焼きを並べたこともある。
日本のケーキ屋さんをイメージして、クッキーとケーキの詰め合わせにした時は我ながらワクワクした。
しかし2017年からは、必要最低限のケーキを焼くだけにして、スシストールの責任者を引き受けることにした。
歴代の保護者のみなさんは、お子さんの卒業とともに学校を去ってしまう。
誰かが引き継がなければ、ストールは残らない。
そして、この学校のフェイトにスシはつきものだ!
以来、フェイト自体が開催されなかった昨年を除いて、メインになったりサブになったりしながら、責任者として参加している。

コンベナー
責任者(コンベナー)から見る景色は、土曜日の午前中だけスシ巻きに参加していた時とはまったく違った。
新しく入学してきたお子さんの保護者の方を中心に、新しい人材を集める。
使わせてもらう各施設に使用許可をもらう。
前日の下準備では、学校でランチや軽食を販売するタックショップと呼ばれる施設を、当日のスシ巻きは、OSHC(Outside School care)という学童のような施設をお借りしている。
そして、当日必要なテーブルなどの備品の申請や、食材の注文。
責任者が集まるミーティングに参加するし、ご飯を炊くための炊飯器も各家庭から貸していただかなければいけない。
しなければいけないことが山積みだった。
ありがたいことに、私が責任者になった2017年から、スシストールにもクラスがついた。
販売スタッフの募集を、クラスにお願いできるようになったのは大きかった。
ついでに食材の寄付も募るようになった。
「スシは作れないけれど、何かできることはないか」と、協力的な保護者の方がたいてい何人かはクラスにいらっしゃる。
クラスだけでなく「今年のコンベナーになってくれてありがとう」と日系の方から言われることもある。
このようなお声がけをいただくと、本当に報われるような気持ちがしていて、年齢によってゆるみはじめた涙腺が、ますますゆるくなりそうだ。
実は今年、下の学年の保護者の方から責任者に立候補がなければ、私はコンベナーをするつもりはなかった。
誰かのやる気がなければこのストールは続かないが、私が無理にやる気を見せるもの違うような気がしていた。
しかし、実際は立候補をしてくださった方が現れて、担当クラスの先生も、日本語の先生もとても協力的だった。
私はこの現状にすっかりやる気を取り戻し、新しい保護者の方と共同責任者となり、協力して動いている。
今年は、8月14日、15時から20時がフェイトの時間で、まさにこの文章を書いている今は、準備にてんてこまいのタイミングだ。
フェイトの売り上げはすべて、子ども達の学校の備品や遊具など、就学環境の改善・向上に使われる。
いちストールの責任者でも大変だと思っているのに、運営側の責任者は本当にやることだらけだと思う。
子ども達のためではあるが、皆で楽しい時間を共有できれば、また来年以降につながっていくのではないだろうか。
このご時世でも、フェイトが開催できることに感謝したい。
7.2.2021
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
コルクスクリューとオーストラリアの日々

2002年 勤務先・ワイナリー
オーストラリアに来たのは2002年2月。
6ヶ月のホームステイ生活を終え、夫の働くワイナリーに合流した。
夫はもともとお酒が好きで、日本では酒屋で働いており、アルバイトの子に少しでも知識を増やしてもらいたいとミニクイズを出す立場の人だった。
ワイナリーに合流したての私は、そんな話を聞きかじっていたものの、お酒の知識はほとんどなかったし、あまり強くもなかった。
そんな状況だったから、ワイナリーで知るさまざまな知識は新鮮で、また、それを日本ではなくオーストラリアで経験しているということ自体が刺激的だった。
販売エリアであるセラドアーから、製造エリアにあるステンレスタンクや樽を見ながら、お客様が試飲ができる環境は、あるべき姿だなと誇らしく思っていた。
ワインの基本的な作り方や醸造酒と蒸留酒の違いを知り、ブドウを育てることとワイン醸造は、必ずしも同じワイナリーで完結しないということを理解した。
ブリスベンの農業祭・エッカなどで行われるワイン品評会で、オーストラリアワインのムーブメントを体感することもあった。
お祭りなどでは出張試飲販売に出向き、ワイナリーではワイン樽に囲まれた中で各種パーティーを開く。
そして市販品から製造途中のものまで、日常的にワインを飲み、味を覚えていく生活。
ワイナリーの雑用係として、さまざまな裏方作業を手伝いながら、同時にオーストラリアのカルチャーをも垣間見ることができた期間だった。
ある時、私たちの生活は「自宅、職場、スーパーマーケットの往復」だけだと気づいたことがある。
しかし取り立てて不満に思えなかった。
職場に行けば、(必要に迫られた)さまざまな体験をさせてもらえたし、現地の少数の日系コミュニティーも居心地が良かった。
ワイナリーのオーナー夫婦はカナダからの移民だったので、お互いに自国にしか家族のいない仲間のような感じで、イベントごとに集まってお祝いをした。
私には保護者のような存在であり、とても心強かった。


2010年 ケアンズへ
ワイナリーに籍を置きながら、私は二人の子どもを産んでいた。
そして二人目の子どもを産んですぐ、夫はワイナリーを退職しようと決断していた。
折しもオーストラリア全土でワインが生産過剰となり、その影響を受けてワイナリーの経営が厳しくなりつつあった。
私は子育てにかかりきりで、月に一度、書類の整理をするためだけに数時間出勤するような状態だったし、ワイン醸造スタッフも少しずつ削られているところだった。
いずれ自分のワイナリーを持ちたいと公言していた夫だったが、自分に子どもができたことで、家族をメインとした生活を送りたいと考えたようだ。
日本に帰りやすいケアンズへ、移動することを決めた。
無職の状態で引っ越したからかもしれないが、ケアンズは完全にアウェーの土地だった。
一番ショックだったのは、スーパーなどで日系の人を見かけても、みな目をそらすことだった。
それまで住んでいたイプスウィッチという町は、人口の規模はケアンズと同じくらいだが、日系の家族は数えられる程度でほとんどが知り合いだったので、スーパーで見かけない日本人を発見したら、とりあえず声をかけてしまうような地域だった。
ケアンズは日本人観光客やワーキングホリデーの若者も多く、誰が旅行者で、誰が地元の人かの区別が難しい。
日系人は3000人ほど住んでいるという。
日本人を見かけること自体、全く珍しくないし、わざわざ日本人のお友達を増やす必要のない人ばかりなのである。
それでも、私がこの地に馴染むことができたのは、当時もうすぐ4歳になる息子と5ヶ月の娘のおかげだった。
予防接種を受けに行った保健所で日本人プレイグループの存在を知り、少しずつ顔見知りのママさんが増えた。
夫は醸造業をあきらめて、再び酒屋に就職し、店舗スタッフとクリスマスパーティーを開くまで仲良くなっていった。

2021年 今現在
必死にふたりの子育てをしながら、考えるよりもまず体を動かす仕事である、ホテルのハウスキーピングを6年半勤めたのち、現在はちょっと立ち止まったような時間帯を過ごしている。
子ども達もそれぞれ、15歳と11歳に成長した。
ほとんど、手がかからない。
昨年はじめ、昨今の事態に落ちいる直前に、10年ぶりにイプスウィッチを訪ねている。
3泊4日の強行スケジュールだったが、1泊ごとに違う友人のお宅にお世話になって、再会を喜ぶことができた。
そして、子ども達の生まれた病院、通った保育園、住んでいた家などをまわり、ワイナリーのあった場所を訪れた。
ワイナリーは2011年に倒産しているが、現在は、元オーナー夫婦が住んでいる。
また同僚だったスタッフは、ワイナリーの一部を使って蒸留所を立ち上げ、高品質なジンやブランデーを少量生産している。
ワイナリーから見た景色は、牛が草を食むばかりの牧草地で牧歌的なものであったが、10年後に見た景色は、動物病院や住宅などの建物が増えていて、現実に引き戻される感覚がした。
近所にあった日用品屋さんは、オーナーが、レジェンドと言われていた中国人からインド人に変わっており、大好きだったオーストラリア名物のビーフパイを販売していた場所には、チェーン店のガソリンスタンドが大きな顔をして建っていた。
10年もあれば、当たり前だが、いろんなことが変わっていた。
ワイナリーで経験したさまざまな出来事は、私にとって、オーストラリア生活の足がかりになる体験だった。私が初めの半年間を過ごしたBed & Breakfastのホームステイ先も売り払われて、現在はリタイヤされている。もう訪れることはないだろう。
手元にあるコルクスクリューを、久しぶりに太陽の下に出してみた。
2002年当初は、オーストラリアワインのまだ多くがコルクを使っていたので、コルクスクリューを使って、一生懸命に開け方を覚えた。だんだん指も切らなくなった。
しかしそのうちスクリューキャップが主流になり、ひねれば簡単に開くようになって、コルクスクリューの出番はめっきりなくなってしまった(その分、コルク臭のするワインも消えた)。
私たちの、オーストラリア生活の初期を象徴するようなコルクスクリュー。
使うことはもうほとんどないけれど、捨てることもないだろう。
ほんの少し前の出来事だと思っていたことが、気づいたらすっかり過去だったと思い知らされたけれど、「受け入れられ、努力してきた」ことを心に、これからの日々を過ごしていこうと思っている。
これが決して、走馬灯を見ているわけでないことを祈る。
6.2.2021
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
手作りのゆたかさ

家庭料理で文化交流
オーストラリアに足を踏み入れたのは、2002年。
初めの半年間は、夫と離れてのホームステイ生活でした。
私の滞在は、家庭料理の文化交流を目的としていましたので、必然的にステイ先で日本食をふるまう機会が多くありました。
山の中の一軒家のような場所で、手に入る日本料理用の食材は限られており、アジア食材店も車で1時間以上かかる場所にありました。
それでもホストファミリーは、すでに味噌やみりん、醤油といった調味料を持っており、私は滞在初期から和食を作ることができました。
ただし和食といっても、白ネギや蓮根やごぼう、たけのこといった野菜類は、簡単には手に入りません。
大根もなかなかお目にかかれない野菜ですが、ラッキーなことにステイ先の近所では売られていました。
ホストファミリーは、新しい食材に挑戦するタイプの人たちでした。
でも大根は食べたことがなかったそうなので、思わず腕まくりをしましたよ。
はじめは大根おろしにして、ハンバーグの和風ソースとして使いました。
常にかたまり肉しか調理しないご家庭だったので、ハンバーグというひき肉料理に難色を示されましたが、かたまり肉をミンチにすることで納得してもらいました。
大根おろしはさっぱりとした後味で、喜んでもらえたと記憶しています。
次に、大根自体の美味しさを味わってもらいたいと思い、干し椎茸とともに風呂吹き大根風の煮物にしました。
米のとぎ汁で下茹でをしていると、独特の匂いにびっくりしたホストマザーが鼻をひくつかせてキッチンにやってきました。
しかし、夕食で一口食べてみると
「あら美味しい」
大根からジュワッとしみでる出し汁とともに、あっさりクセのない味がお気に召していただけた様子。
好まれない匂いの記憶が、帳消しになった瞬間でした。
それから、よく作ったのは巻き寿司です。
こちらの人にとって、巻き寿司は健康的な食べ物という認識で、スーパーには寿司用のお米や海苔などが、国際食品コーナーに売られていました。
照り焼きチキンやツナマヨ、スモークサーモンでお寿司を作りましたが、これらは手に入りやすい食材であり、また食べやすいため、20年近くたった今も我が家の定番となっています。
寿司巻きはちょうど良い文化交流のアクティビティになり、ご近所さんや家族を招いて寿司パーティーを開きました。
巻き簾を使って巻き寿司を作るのは、在住日本人でも得意でなかったりします。
それこそ、初めて挑戦するオージーの皆さんとは、
「できるの?」
「どうやるの?」
ってやいのやいの言いながらつくります。
ちょっといびつに巻き上がったお寿司を食べるのは、とても楽しい時間でした。
それから、ホストファミリーのお孫さんが遊びに来ていた時は、椎茸、鶏肉、にんじん、カブで炊き込みご飯を作りました。
まだ離乳食明けと言ってもおかしくない年齢のお孫さんでしたが、醤油味の炊き込みご飯が口にあったようで、何度もおかわりをしてくれたのが嬉しく、私の記憶に残っています。
肉じゃが、牛丼、鶏の照り焼き、かぼちゃの煮物、ほうれん草のおひたし、蛇腹きゅうりの酢の物、お味噌汁、チャーハン…滞在中は、日本の家庭でごく一般的に作られる、このような料理をつくりました。
私たちから見るとフツーの料理でも、オーストラリアで披露すると文化交流になるという面白さ。
逆に、オーストラリアでは一般的な、オーブンでかたまり肉と野菜を焼くロースト料理の夕食が、私には新鮮に映りました。


手作りをするということ
滞在の初めから「積極的に料理をする」という環境でしたから、その後夫と再び合流してからも、手作りに抵抗のない生活が続きました。
実際のところ、手作りを余儀なくされるのは「海外に移り住んだ日本人あるある」かもしれません。
大都市やケアンズのように日本人が多く住む地域には、日本食のレストランや食べ物屋さんは存在します。
また、アジア食材店、日本食材店もあります。
しかし、現実的に値段が高い。
そして、自分の好みの味かどうかは相性があります。
故郷の味を恋しがるなら、自分で作ってしまう方が手っ取り早い。
ありがたいことに、こちらで勤め人をしていれば、性別関係なく大体定時で帰れます。
毎日、料理をする時間がとれるのです。
夫は、私の出産を機に本格的に夕食作りを始めました。
上の子が15歳になる今では、バターと小麦粉でホワイトソースを作れるようになっています。
これまでも、ラーメンの麺とスープの両方にチャレンジしたり、納豆も作りました。この前は、炊いた餅米を麺棒でついてお餅にしていました。
私は、パンやケーキ、おまんじゅうなどのお菓子をよく作ります。
もちろん出来合いの食べ物を買うこともありますし、ケーキ屋さんのスイーツも大好きです。
作る過程を知っている分、余計に美味しく感じますし、ありがたいなと思います。
時々考えるのです。
もし日本で生活をしていたら、ここまで自分で作ろうと思っただろうか?
大学生の頃、一口コンロの狭いキッチンで、友人が器用に揚げ物の夕食を作っていました。
素晴らしいと思いながらも、私は揚げ物を自宅では作りませんでした。
外食で食べることが多く、スーパーなどでも簡単に手に入るからです。
今度は同じ友人が、手ごねパンの生地をテーブルにペタペタ打ちつけていました。
私はまたもや感嘆しながら、「パンは時間がががるうえ、すぐそこの店で簡単に買えてしまうしなあ」と思っていました。
結婚してからも、仕事帰りの夫と赤暖簾で待ち合わせたり、中華屋さんで夜ご飯を食べることが多くありました。
作ってみたいなあという気持ちはあっても、便利さに流されていたように思います。
「誰かが用意してくれた便利さ」があったからこその生活でしたが、日本を出て恋しくなってようやく、「自分で作ろう、やってみたい」という思考を得ました。
食べるものだけでなく、アクリルたわしや石けん、化粧水などにも挑戦してきました。
ホームステイ中、オーストラリア人のホストマザーは、自分のツーピース・スーツを縫っていました。
ホストファーザーは、もともと木材の仕事をしていたそうですが、自宅に木材加工場を持ち、タンスなどの家具を作っていました。
住んでいた家と、家にある家具のほとんどを自分たちで作ったと聞いています。
当たり前のように手を動かす人の中に身を置いて、私の考え方が自然と変化したのかもしれません。
私は県境にある田舎で育ちました。
自宅で調理される食事は、主に家庭菜園で採れた野菜。
梅干しも漬物も自家製。
汲み取り式のトイレ。
私が多感な中高生の頃に、バブルの好景気がやってきました。
様々な消費を促すたくさんの広告が、私たちの周りにあふれていました。
知らず知らずのうちに
「なんでも手作り=田舎=古臭い=なんだか恥ずかしい」
というイメージを持ってしまっていたようです。
様々なものを「自分で作ってみよう」と積極的に思えるようになった今では、自分が欲しいと思うものを自分で作り出せるということは、とても豊かなことだと感じています。
誰も盗むことができない、大切な財産です。
そしてそれは、「自分でコントロールできること」でもあります。
私にとって海外に出るという行動は、単に「居心地の良い環境から離れた」だけではなく、「自分軸で行動できる」きっかけを得るものであったと、しみじみ思っています。

5.2.2021
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
朝が好き

朝が好きだ。
30才を過ぎる頃までは朝寝坊だったので、昔の私を知る人はびっくりするかもしれないけど、朝が好きだ。
5:45の目覚ましアラームが鳴る1時間くらい前から、お腹の空いた飼い猫が二匹ともベッドへやってくる。
ベッドの上をもぞもぞ歩いたり、私の指をなめたり、そばでクルンと横たわったりして私が起きるのを待っている。
なんとか目を覚まし、朝一でネコたちに餌を与え、猫のトイレ掃除をして庭に出ると、運が良ければとても綺麗な朝焼けが見られる。
近くで遠くで、鳥たちのさえずりも聞こえる。
それだけで、今、この瞬間に起きていてよかったと思う。
結婚当初、夫は朝早くに出勤することが多かった。
まだ日本にいた頃だ。
夫より早く起きて朝ごはんの準備をする、というのがいわゆる「主婦・パート」の私に期待される役割だったのかもしれない。
しかし、私はその辺りはルーズで、自分の都合で起きていたし、夫もその辺りは気にしないタイプの人でたいへんありがたかった。
おかげで「早起きをして夫の面倒を見なければ」という義務感や切迫感にとらわれることがなかった。
オーストラリアに来て夫とは別々になって、6ヶ月間のホームステイ中は、毎日のルーティンがなんとなく決まっていた。
朝7時に起きて、ホストファミリーと一緒に朝食を作る。
午前中のモーニングティー、ランチ、アフタヌーンティー。
夕方5時過ぎからは夕食作り。
そのまま10時ごろまでリビングでのんびり過ごして、自分の部屋へ行く。
これの繰り返し。
英語は苦手だったけど、毎日同じ時間に起きて、同じルーティンで生活するって思ったより快適なんだな、ということに気づく。
生活の枠組みが決まっていることに対する息苦しさはなくて、
『今日は、空いた時間に何をしようかな?』
って考えることができた。
(手芸のクロスステッチとか、料理本を読んだりキッチンを借りて料理を一人で作ってみたり、お手伝いをしたり、ごくたまに英語の辞書を開いてみたりといった、自分の収入のための仕事をしない、若いのにおよそ俗世を離れたような暮らしだった。)
夫と合流し子供が生まれると、今度は責任感が出てきて朝起きられるようになった。
小学生の夏休みの朝のラジオ体操。
5年生までは、ほぼ起きられた試しがなかったのに、6年生になって自分の地域を任されたとたん、毎朝起きて、みんなの前で体操ができるようになっていた。
あの時とちょっと似ているなと、ひとりごちた。
相変わらず、夫は自分のことは自分でして出勤していたので、朝ご飯の後、ぽっかりと時間が空いた。
ひまだし、毎日ベビーカーを押してお散歩に出ていたら毎日のルーティンができで、そうなると子育て中の生活でも精神的に余裕が生まれることを覚えた。
下の子が3才になり、ホテルの客室清掃の仕事を始めてからは、二人の子供たちを、幼稚園と小学校の学童へ預けるために、はじめのうちは朝6:45に家を出ていた。
さすがにこの頃は朝早く起きられて嬉しいというよりも、ひたすら義務感で起きていた。
自分の立てたスケジュールをそつなくこなすために、早く起きていた。
当時3-4才と7-8才くらいの子が、6時に起きて45分後に家を出る生活に付き合ってくれたことは、今考えると奇跡的に思えるし、感謝しかない。
いつも同じ時間に子供たちを車に乗せて走っていると、日の出の時間の変化がよくわかった。
蒸し暑い夏から朝晩が肌寒い季節に移り変わる時、東からの太陽がまぶしくて車のサンバイザーを下ろす日々がはじまる。
ホテルには6年半在籍していたので、毎年、サンバイザーを下ろしながら
「いよいよ気持ちのいい季節が来るな」
と、まぶしさに目を細めながら思っていた。
5:45に目覚ましアラームが鳴る今、起きてから少しのんびりする時間がある。
そのおかげで猫のお世話をしたり、そのついでに日の出の綺麗な空の色をカメラに収めることができる。
休みの日なら、そのまま海を見に行くことだってできる。
20代の頃のように、夜、無理をするのが辛くなってきた今、朝はエネルギーに満ちた「希望」の時間だ。
だから、私は朝が好きだ。
4.1.2021
DAYS / Tsukie Akizawa Column
Green and Gold
ハイスクールのドラマ

Improvisation night
昨夜は、息子の通うハイスクールへ行ってきた。
オーストラリアのハイスクールは、基本的に中高一貫だ。
11、12歳から17、18歳までの生徒が通う。
5月生まれの息子は、日本であれば今年中学3年生だが、こちらでは高校1年生となる。
学年は1月始まりのため、特に1月から3月の間は日本とオーストラリアで2学年も違うことになり、分かっているのにいつも驚いてしまう。息子が小学校に準備学年として入学した時は、たった4歳だった。
ハイスクールに話を戻そう。
息子の友人がドラマ(演劇)のイベントに出演するから観に行きたいという。
11歳の娘も観たがったので、私もついていくことにした。
ハイスクールの講堂でおこなわれた、Improvisation night。
即興劇だった。
学校でドラマを習っている生徒のうち、年齢の高い子たちがチームに分かれて、その場で選んだお題のドラマゲームに挑戦し、点数を競う。
まだ年齢の低い生徒は、事前に練習してきたオリジナルの寸劇を、そのドラマゲームの合間に披露していた。
実際にどんなゲームが行われていたかというと、
・同じ内容のストーリーを、「激しく」「ネガティブに」「ロマンチックに」などと色合いを変えて演じるもの
・演技を続けながら参加する人数を一人ずつ増やしていき、全員で演技したらまた一人ずつ減らしていくというもの
・演技をしながら、サポーターのパントマイムを見てキーワードを推理し台詞に使うもの
などなど、大人顔負けの内容だった。
私も小・中学校では、文化祭の出し物やクラブ活動で劇に参加したことはある。
日本の学校で、演劇に参加したことのある人は少なくないだろう。
それでも演劇を専門的に習ったことのない私にとっては、ただただ生徒たちの達者な様子に圧倒されるばかりだった。
そんな昨夜のイベントだったが、彼らにとっては観客の入った公開レッスンと言えなくもないだろう。
なぜなら彼らの「本番」といえば、市の劇場で開催予定のミュージカルだからだ。
2年前に「雨に唄えば」を観に行った時、彼らは堂々とした演技で観客を圧倒していた。
ミュージカルだから、歌が上手いのは当たり前。
ロマンティックな演技すらこなす。
ダンスチームの踊りも素晴らしかったし、ステージ上では実際に雨も降って、地元紙の話題になっていた。
本当にみんな、放課後はそこら辺を歩いている高校生なのだろうかと何度も思った。
おまけに地元のラジオ番組に出演した時は、受け答えの明瞭さにも驚かされた。
どれだけしっかりしてるんだ。
そう言えば、「ハイスクールミュージカル」というディズニー映画を観たことを思い出した。
英語圏では、達者な演技をする高校生というものは一般的な存在なのかもしれない。
Programs of Excellence in 2022
一緒に昨夜のドラマを見たいと言った娘は、現在こちらの小学6年生。
娘の場合は11月生まれなので、日本でも4月から6年生であるのは同じ、現在11歳。
今、6年生はハイスクールのお受験シーズン真っ最中。
と言っても通常、校区内の公立学校には受験をしなくても通うことができる。
ただ、先に書いたドラマのような活動に参加したい生徒は、エクセレンスプログラムと呼ばれる課外活動の受験が必須となる。
またこの受験は、校区外の学校へ越境入学したい場合の一般的なルートともなっている。
少なくともケアンズではそうだ。
学校によって科目に多少の違いがあるが、息子の通うハイスクールのエクセレンスプログラムには、STEM(学問)、ミュージック(合唱・楽器)、スポーツ(サッカー、ホッケー、バスケットボール)、美術、演劇、ダンスがあり、いくつでも受験できる。
ドラマを見たいと言った娘は、このドラマの受験に参加する。
クラス担任との面談時にドラマ受験の話をしたら、「クラスではおとなしいから想像ができない」と言われたが、クラスで一人ずつ行う発表に比べたら、みんなで演じるドラマの方が恥ずかしくないそうだ。
それを聞いて、素晴らしい演技をする役者さんが、ひとたびコメントを求められるとモゴモゴしてしまう様子を思い出してしまった。
まだこれからの娘と、すでに実力のある役者さんを同じラインに並べるのは、親バカ以外のなにものでもないのだけれど。
「演技を習う」
日本だったら子役タレントさんをイメージしてしまうが、ドラマはケアンズのポピュラーな習い事のひとつとなっている。
自己表現力、記憶力、胆力、発想力、応用力などが鍛えられるからだろうか。
将来、どんな職業についたとしても役に立つのかもしれない。きっとそうだ。
娘のドラマの受験では、ひと段落分の文章を覚えて発表するのが当日の課題。
課題の用紙はすでに娘に渡してあるので、自分なりのペースで進めて欲しいと思っている。
昨夜の、見る側は面白かったけれど、演じる方は簡単でない即興劇を見た後でも、娘は受験のやる気を無くしていなかったので、頼もしいなと少し思った。
















































